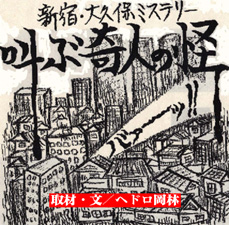
タイトル■叫ぶ奇人の怪
書き手 ■ヘドロ岡林
これはノンフィクションである。
叫ぶ奇人……、この怪物は実在する!
不夜城・新宿大久保に生息する
このミステリアスな怪物の正体に迫るべく
取材を重ね、その様子をリアルタイムで
報告していくのが、この企画の主旨だ。
繰り返す。“この怪物は実在する”!!
>バックナンバー
◇◇ 第三話 ◇◇
俺は侍ニッポン。タトゥーなんか怖くない!
奇声に怯えながら眠りについたが、
目覚めたときには、
そんな出来事などすっかり忘れてしまっていた。
なにしろ、いよいよこれから本格的に、
新生活が始まるのである。
近々、ベッドも届く。
それを予定通りここに配置すれば、
寝ながらテレビを見れるだろうか。
ベッドカバーは何色にするべきか。
壁時計やらCDラックやらの小物はどこでどんなのを買おうか。
それやこれや、考えることがいっぱいで、
その空想がまたこの上なく楽しいもんだから、
些細な悩みなど頭から離れていってしまったのかもしれない。
まだ始まったばかりだったが、
一人暮らしというのは気楽なものだな、と思った。
何時に寝ても、何時に起きても、
誰からも文句を言われない。
自堕落になろうと思えばいくらでもなれる。
一応、俺、フリーライターという名の自営業者なのだが、
まったくもって売れっ子じゃないので、
毎日、締切りに追われるようなことはない。
遊ぼうと思えばいつでも遊べる。
なにしろ歩いて10分ほどの場所に、歌舞伎町があるのだ。
俺はまず、引っ越し当初の数日間、
夜に眠るのがもったいないという感覚に支配された。
こんなに近くに歌舞伎町があるのに、寝てる場合か?
ひとたびそう思うと居ても立ってもいられなくなり、
たとえそう思ったのが深夜の2時であろうが、
ツッカケを履いて、ツカツカと街へ出かけてしまう。
セクシー気分の夜ならば、
わざわざお風呂に入り、ムースで髪を固めてから、
革靴を履いて、コツコツと街へ出かけたりもした。
だからと言って、毎回セクシーな場所へ遊びに行くわけじゃなく、
ただ散歩して、いろんな飲食店などを覗いて、少しずつテリトリーを固める。
そんな巡回行動を繰り返した。犬が電柱に小便するのと一緒だ。
そして歩きくたびれて、明け方、日刊スポーツを買って家に戻り、
めざましテレビを見ながら眠りにつく。そんな日々が続いた。
どう考えてもアベコベである。
普通の人が寝ている時間にお出かけし、
普通の人が出かける時間に家に戻り、
普通の人が働いてる時間に睡眠する。
そして夜に目覚め、またぞろお出かけする。
まるでおミズのような生活だ、とも一瞬思ったが、
それとも何かが決定的に違う。
おミズの人は夕方出かけ、それから仕事をして帰るのだが、
俺の場合、外にいる間はビタ一文稼ぎを生み出しておらず、
むしろ、ゼニやらなんやらをいたずらに放出しているだけ。
で、家に帰ってから、寝ているのだ。
いったい、いつ働いてるんだ?
こんな生活を続けていたら、
あっという間に貯金がなくなってしまうだろう。
これがフリーランスの厳しいところだ。
自堕落のツケは全部自分に回ってくる。
タイムカードなどないのだから、
自分の時間は自分で管理しなければならない。
でも、楽観視していた。
この昼夜逆転現象はおそらく、引っ越し当初特有の
ハイな精神状態がもたらす病気みたいなもんだろうと思っていた。
旅行に行って、夜遊びせずに眠るのはもったいない。
その感覚に近いのだろう、と。
環境に慣れればやがて気持ちも落ち着くだろうし、
そうなれば仕事にも集中できるようになるだろう、と。
ところが、1週間経っても2週間経っても
ちっとも気分は落ち着かなかった。
なぜか?
まず、同じマンションの住人たちが、
俺に輪をかけたようなデタラメ人間ばかりであることが、
徐々に明るみになってきたのだ。
引っ越して間もないころ、
俺は洗濯物を回収している最中に、
うっかりベランダからハンガーを落としてしまった。
下を覗き込むと、1階の庭が見える
(1階だけはベランダではなく、ちょっと広めの砂利庭になってる構造だ)。
ハンガーは、そこに落っこちていた。
たかがハンガー、くれてやると思ったが、
今後、何かもっと大事な物を落としてしまったときに
回収に行けないのも困ると考え、挨拶がてら、取りに行くことにした。
103号室の呼び鈴を鳴らす。
出てきたのは、推定年齢30前後、故・三浦洋一に似た上半身裸の男だった。
その肩のあたりにはビッシリと、お釈迦様かなんかの入れ墨が入っていた。
「丐丕丗丞丐凧?」
外国人だ。中国人だろうか?
「丐丕丗丞丐凧!!!???」
怒っている。おそらく「なんの用だ?」と言っているのだろう。
「アイムソーリー、ハンガー、ハンガー、プリーズ…」
俺は咄嗟に、手で二等辺三角形を示しながら
そう答えたが、まったく通じていない様子。
仮に彼が英語を知っていたとしても、
このセンテンスとボディーランゲージでは何も理解できなかっただろうが。
「ハンガーを落としまして…。キャンニュースピーク、イングリッシュ?
ハンガー、フォーリンダウン イン ユアガーデン。分かります?」
敵意はございませんという媚びた笑みを必死で浮かべ、
混乱した頭そのままに、英語と日本語をメガミックスしつつ、
「あっちに」「ガーデンに」と、庭のほうを指差した。
その時、部屋の内部をチラっと見たのだが、
薄暗い室内のド真ん中に全自動の麻雀卓があり、
そこには2人の男が座っていた。
サンマーのまっ最中だったみたいだ。
暑いからか、その2人も上半身裸で、
しかも、これまた肩やら背中にビッシリとタトゥーが入っていた。
やがてそのうちの1人が、重い腰を上げてこっちに歩いて来た。
逃げたい気分になったが、逃げてもしょうがない。
なにしろここは、俺のマンションなのだから。
その男は、ベンガルの若いころのような顏。
年齢は25歳ぐらいだろうか。俺より明らかに年下だ。
彼は日本語が少し理解できるようで、
やがて事情を察したような顔で庭に向かい、
手にハンガーを持ってこっちへ戻って来た。
なぜかニヤニヤと微笑を浮かべ、右手で鷲掴みにしたハンガーを
トン、トン、トン、と左の手の平にぶつける仕草を繰り返しながら、
こっちにだんだん近付いて来た。
「サンキューベリーマッチ!」
俺は頭を深々と下げた。
で、頭を上げたら、コツンと何かが頭に当たった。
ハンガーだ。
そう。
さっきのトン、トン、トンは、
俺の頭を叩くための助走行為、予行演習だったのだ。
むろんそのお仕置きは、
大人が子供を優しく叱るような
「こ〜らっ!」「めっ!」というニュアンスだから、
痛くもなんともなかったのだが、
それでも心は傷付いた。
俺は奴らにナメられたのだ!
これは、まぎれもない事実だろう。
奴らが何者かは分からない。
入れ墨、麻雀とくれば、その筋の人間なのかとも思うが、
その筋であろうがどの筋であろうが、
ここは日本だ!
なのになぜ、日本人であるこの俺が、外国人にナメられなければならないのか?
お取り込み中に邪魔が入ったのだから立場としては向こうが優位だが、
それにしても、初対面のベンガル野郎に頭をぶたれるほど
悪いことをしたとは思えない。
要するに奴らは、俺のことをハナから子供扱いというか、絶対的な安全パイとして
ナメ切っていたのだ。だから、あんな仕草を平気でできたのだろう。
年下のくせに!
そんなに俺って、弱そうなのだろうか?
家に戻ってから鏡を見てみたりした。
やはり、痩せ過ぎなのかもしれない。
でも考えてみたら、こういう敗北感は、
このとき初めて味わったことではない。
中学時代にただ歩いているだけでカツアゲされたり、
高校時代にバイト先の先輩に呼び出されて脅されたり、
社会人時代に飲み屋で隣席の男に絡まれたり…。
その都度、俺は、理不尽な思いにかられつつ、
ニヤニヤ笑いでごまかしながら、戦わずして屈服してきた。
情けない話だが、
それが俺なのだとしか、言いようがない。
喧嘩するのがイヤなのである。
殴ると相手を殺してしまう、それが怖い、ということではなく、
殴られて俺が死んでしまうのが怖いのだ。
でも、それでいいと思っている。
本当は、いついかなる場面でも相手を恐れぬ
安岡力也のような勇者でありたいと思うが、
それはルックス的にもフィジカル的にもマインド的にも
無理なことなのだろうと、とっくの昔に悟り切っている。
武道派の道は諦めている。
だから俺、この件についても、実はそれほど傷付いているわけではない。
この手の屈辱には慣れっこなのだ。
読んでいないことを大前提として、
挑発的なことを言うならば、
1階のアイツらなんかちっとも怖くない。
いや、怖いことには違いないのだが、
その手のコワモテとの距離感の取り方は、永年の経験から学んでいるつもり。
だから、そんなに怖くない。
ハイエナは、ライオンより弱いが、ライオンに食べられることはないのだ。
1階の入れ墨ファミリー対策としては、
とりあえず、ベランダから物を落とさないこと。
これさえ気を付けていれば、末永く共存できるだろう。
…などと思っていた矢先、
もっと厄介な人たちが隣に引っ越してきた。
(つづく)