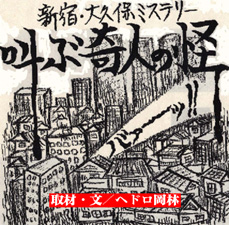
タイトル■叫ぶ奇人の怪
書き手 ■ヘドロ岡林
これはノンフィクションである。
叫ぶ奇人……、この怪物は実在する!
不夜城・新宿大久保に生息する
このミステリアスな怪物の正体に迫るべく
取材を重ね、その様子をリアルタイムで
報告していくのが、この企画の主旨だ。
繰り返す。“この怪物は実在する”!!
>バックナンバー
◇◇ 第四話 ◇◇
隣人はニダニダ笑う
引っ越してまだ間もない、ある日の昼下がり。
届いたばかりのベッドの上でウトウトしていたら、
玄関の扉がいきなりガチャッと開いた。
うん?と思い、目を開けて玄関を見たら、
何者かが「あっ…!」と小声を上げ、
そ〜っと扉を閉じている最中だった。
顔は見えなかったが、
扉が閉まるその刹那、チラッと見えた服の裾と、
チラッ聞こえたその声から、
それが中年女性であることはなんとなく分かった。
部屋を間違えたのだろう。
放っておけ、と思った。
なにしろこっちは、お昼寝の真っ最中なのだ。
わざわざ身を起こし、鍵を閉めに行くのも面倒臭い。
そしたら数十秒後に、ピンポーンと呼び鈴が鳴った。
カッタるいなぁ、いちいち謝らなくていいよ、とシカトを決め込んだが、
もういっぺん、ピンポーンと鳴らしやがったので、
不機嫌な表情を作ってから、ドアを開けた。
そこにはやはり、中年のオバサンが立っていた。
オバサンの後ろにも誰かいるようだが、
俺、眼鏡をかけていなかったので、よく見えなかった。
「なんですか?」
ぶっきらぼうにそう聞くと、オバサンは弾んだような口調で、
「あのおっ…、すいませんがっ。もしよろしかったら、
部屋をちょっと見せて欲しいんですけどっ…」
と言う。
「部屋を見せるって…、その前にアナタ、誰なのよ?」
俺はちょっと怒った口調でそう聞いた。
「アッ、ごめんなさいっ!ごめんなさいっ!申し遅れました。
アタシ、不動産の者です。で、この子がねっ、今度、このマンションに
引っ越すかもしれないから、参考までに、ちょっと中を見せてもらえたらと…」
後ろに隠れていた人物が、ヒョコッと顔を出し、
ちょっとバツが悪そうな感じで、俺に会釈した。
若い女だ!
俺、眼鏡をかけていないと、視力0.1以下なのだが、
わずか2mほどの近距離だから、
男か女か、若いか年寄りか、ぐらいは識別できる。
ただし、どんな顔をしているのかは、
ぼやけてしまってほとんど見えない。
でも、服装の雰囲気や、髪型の雰囲気は悪くない。
ひょっとしたら、可愛いいのかもしれない、
という雰囲気を感じさせるシルエットだ。
この子のためなら、
協力してあげてもいいかな、と思った。
ただし俺、寝起きで髪がボサボサだろうし、
上、ドンキホーテで買ったらあっという間に
首元がヨレヨレになったヘインズのTシャツ、
下、フィンランドというサウナからかっぱらって来て以来
3年ぐらい穿き続けているぶかぶかのトランクス姿だから、
このままの格好で、部屋案内などしたくない。
俺は咄嗟に、こんな馬鹿げた提案をした。
「部屋、見せてもいいですけど、
俺、その間、寝てるから、勝手に見て下さい。
で、終わったら終わったって、言って下さいよ」
そして、布団にすっぽり潜り込んだ。
「いいですよー!」と叫ぶ俺。
「じゃ、失礼しますね」と答えるオバサン。
もしかしたら部屋に入ってくるのかも…と思ったが、
靴を脱いでいる気配はない。
2人は玄関から部屋を眺めているだけのようだ。
「ふぅん」とか「へぇ」とかいう、わざとらしい感嘆の声が聞こえる。
全部オバサンの声だ。お前が住むわけじゃないだろ!と布団の中で思った。
そもそも俺の部屋は何の変哲もないワンルームだし、
感心するような家具は何一つ置いていない。
「終わりましたぁ。ありがとうございましたぁ(……カチャ)」
出て行った。
もう終わりかよ!
たったの15秒だぜ。
それで何が把握できたというのか。
その程度の確認なら、何もわざわざ人が住んでいる部屋を観察しなくても、
これから借りるかもしれない空き部屋をジックリ見ればいいじゃないか。
分かった!
おそらく、こういうことだろう。
あの不動産屋のオバサンは、本当は、
現在空室の302号室にお客を案内するつもりだったのに、
隣の303室(すなわち俺の家)のドアをウッカリ開けてしまい、
そこに人が寝ていたもんだから、驚いて、瞬間的にドアを閉めちゃったのだ。
で、すぐに、部屋を間違えたことに気付き、
そのまま逃げるのはヤバイと思ったのだろう。
何かお詫びを言うべきだ、と。
しかしその一方で、オバサンは、
もし室内の人(すなわち俺)が何も気付かずに熟睡していたとしたら、
「さっきはごめんなさい」と謝ってもなんのことだか話が通じず、
「なんだお前は!そんなワケの分からないことを言うために俺を起こしたのか!」
という具合に、話が変にこじれてしまう可能性を恐れたのではないか。
で、オバサンは、呼び鈴を鳴らす前の数十秒の間に、
後者の熟睡ケース対策として、
何かもっともらしい訪問理由を用意しておくべきだと、考えたのだ。
不動産だから、「部屋を見せて欲しい」。
よし、これで行こう。これならそんなに不自然じゃない。
で、恐る恐る呼び鈴を鳴らしてみたら、反応がない。
そこでオバサン、「これは寝てるぞ!さっきの件はバレてない」
と安堵するとともに、急に強気になって、もう一度ベルを鳴らした。
おそらく、そんなところではあるまいか。
部屋を見たいだと?
ウソつきめ!
「ふ〜ん」だの「へぇ」だの
下手な芝居、しやがって!
だが俺、オバサンを責めるつもりはない。
ウソつきで、下手な芝居をしたという点において、
俺もまったく同罪だからである。
もしオバサンの後ろにいた客が、
若い女ではなく、むさくるしい男だったら、
俺はさっきのように部屋を公開しただろうか?
答えは否だ。
「アナタ方ねぇ、失礼じゃないですか?人ん家のドア、勝手に開けたり、
部屋を見せろと迫ったり。まったくどういう神経してるんですか?」
ぐらいのことを言い放って、ドアを勢いよく閉めたかもしれない。
つまり、気前よく部屋を公開するという俺の行動は、
これから隣人になる可能性を秘めた若い女に対し、
「俺って気さくな好青年ですよ。治安が悪いと言われているこのあたりにも、
こんなに素朴な人がいるんですよ」ということをアピールするための、
偽善と下心に満ちた安っぽい芝居だったのだ。
でも、もしあそこで俺が、無愛想な対応を続けたり、
オバサンを叱りつけたりしていたら、
彼女は「こんな恐い人の隣になんか住みたくない!」と契約をためらい、
すぐさま違うマンションを探し始めたと思う。
そのことを瞬時に悟った俺は、不意に訪れた赤の他人に対し、
頭も尻も全部隠しながら部屋を丸ごと公開するという、
無警戒極まりない、超人的なお人好しを瞬間的に演じてみせたのだ。
われながら、過剰演技だったと思う。
しかし、この誘致作戦が功を奏したのだろうか。
数日後、ガタガタゴトゴト、家具が搬入される音と、
若い女のはしゃいだような喋り声と笑い声が、隣の部屋から聞こえてきた。
1人ではなく、少なくとも2人いるようだ。
しばらく耳を澄ましていて分かったのだが、彼女らは韓国人だった。
会話の語尾で乱発される「ニダ」で、それは分かった。
だが、そこにいるのが、
この前、下見に来た子なのかどうかは分からない。
仮に顔を見たところで、それは分かりようがない。
なにしろ、あのときは眼鏡をかけていなかったので、
どんな顔なのかを確認できなかったのだから。
ま、この際、なんだっていい。
若い女が隣に引っ越してきた、という事実に変わりはないのだから。
あ〜、なんだかとっても楽しい気分になってきたぞ!
一人暮らし、最高!
「バァ〜〜〜〜ッ!」
むむっ…、アイツだ。
まだ懲りずに、叫んでいたのか。
でも悪いけど俺、今はそれどころじゃないんだ。
「バァ〜〜〜〜〜〜ッ!」
ふふっ。
いいよ、分かったよ。
好きなだけ叫べよ。
キミが何者かは知らないけど、
気が済むまで叫ぶがいい。
でもちょっと今は、
キミに構ってるヒマはないんだ。
ごめんね。
「バァ〜〜〜〜〜〜〜ッ!」
ひょっとしてキミ、
俺のことを祝福してくれているのか?
んなわきゃ、ねぇか。ふふふ。
「バァ〜〜ッ!」
「バァ〜ッ!」
・・・・・
・・・・
・・
・
この日の叫びは、
割と規則正しいテンポで、何度も何度も発せられていたように記憶する。
声のトーンに呪われたようなニュアンスはなく、
かと言って能天気なニュアンスもなく、
たとえるならば、光化学スモッグ警報のように、
ヌボーッと、機械的に鳴り響いていたような感じだった。
前回、聞いたときはあんなに無気味だったのに、
不思議なもので、この日は何度聞いても不快感はなかった。
そのうち、気にならなくなり、
そのうち、聞こえなくなっていた。
もう叫ぶ奇人のことなんか、
どうだっていいと、このときの俺は思っていたのかもしれない。
世間一般ではこういう状態のことを
色ボケと言うのだろう。
だが、しかし、この浮かれポンチな気分は、長くは続かなかった。
お隣に越して来た韓国ガールズのハチャメチャなライフ・スタイルに、
俺は翌日から悩まされることになる。
(つづく)