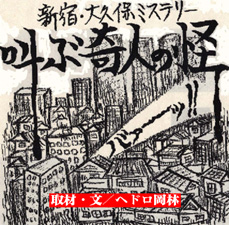
タイトル■叫ぶ奇人の怪
書き手 ■ヘドロ岡林
これはノンフィクションである。
叫ぶ奇人……、この怪物は実在する!
不夜城・新宿大久保に生息する
このミステリアスな怪物の正体に迫るべく
取材を重ね、その様子をリアルタイムで
報告していくのが、この企画の主旨だ。
繰り返す。“この怪物は実在する”!!
>バックナンバー
◇◇ 第六話 ◇◇
6年間、叫び続けた我が友
♪ズズチャッ、ズチャッツ、チャッツ、チャ〜
♪ズズチャッ、ズチャッツ、ジャラララ〜ン(ダガゴロゴロゴロ………ドン!!!!!!)
♪ズズチャッ、ズチャッツ、チャッツ、チャ〜
♪ズズチャッ、ズチャッツ、ジャラララ〜ン(ダンダンダン、ドドドドドン!!!!!!)
♪2 minutes to midnight,
The hands that threaten doo〜〜〜〜〜m.
♪2 minutes to midnight,
To kill the unborn in the wom〜〜〜〜b.
♪ズズチャッ、ズチャッツ、チャッツ、チャ〜
♪ズズチャッ、ズチャッツ、ジャラララ〜ン(ダガゴロゴロゴロ………ドン!!!!!!)
♪ズズチャッ、ズチャッツ、チャッツ、チャ〜
♪ズズチャッ、ズチャッツ、ジャラララ〜ン(ダンダンダン、ドドドドドン!!!!!!)
♪2 minutes to midnight,
The hands that threaten doo〜〜〜〜〜m.
♪2 minutes to midnight,
To kill the unborn in the wom〜〜〜〜b.
♪midnight……!!!!!!!!!!!!
♪midnight……!!!!!!!!!!!!
♪midnight……!!!!!!!!!!!!
♪all night……!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
♪midnight……!!!!!!!!!!!!
♪midnight……!!!!!!!!!!!!
♪midnight……!!!!!!!!!!!!
♪all night……!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
……………シーン。
アイアン・メイデンの破壊力は、想像以上だったようだ。
「悪夢の最終兵器」というタイトルそのままに、
曲が終わると同時に、
さっきまであんなにうるさかった隣室は、
まるで人が死んでしまったかのように、シーンと静まり返ってしまった。
うむ、分かればいいんだ。
戦い済んで、日が暮れて。
昨日の敵は、今日の友。
これからは、仲良くやっていこうじゃないか。
そんなことを心の中で呟きながら、
忌わしいCDをステレオから取り出し、ケースに収めた。
そして、思い出したついでに、高瀬に電話をした。
半年ぶりに彼と喋った。
大久保に引っ越したこと、
ベランダからの眺めが抜群だということ、
近所に奇妙な叫び声を上げる人がいること、
1階にマフィアっぽい連中がいること、
隣に韓国ガールズが引っ越してきたこと、
彼女らがうるさいからCDで黙らせてやったこと、
そのCDはお前から随分前に借りたCDだということ、
などの近況を面白おかしく報告した。
高瀬は、「CDを返せ」とは一言も言わず
(たぶんもう、アイアン・メイデンのことはあまり好きじゃないのだろう)、
「その隣の子、可愛いの?タレントで言えば、ダレ風?」ということ
ばかりを盛んに聞いてきた。
彼は昔から、人の話をロクすっぽ聞かない奴だったが、
その点は、今もまったく変わっていないらしい。
「だから、『ちゃんとは見てない』って言ってんじゃん!
俺、眼鏡かけてなかったし、そもそも今、隣にいるのが、
その下見に来た子かどうかも分からねぇんだよ!」
「じゃあ、俺が審査する。行く行く!遊びに行く!」
「だから、もういいよ、隣の女は。それよかさぁ、お前に分析して欲しい
ことがあるんだよね」
高瀬は間違いなく馬鹿だが、しかし、単なる間抜けではないということは、
幼少期からずっと一緒に遊んできた俺は、よく知っているつもりだ。
奇妙なもの、おかしなもの、ミステリアスなものへの好奇心が強く、
それがどうでもいいことであればあるほど、
サラッと流さず、それにいつまでも執着するようなところが高瀬にはある。
古い話になるが、俺と高瀬は小学生の時、
同じ野球チームに所属していた。
そして6年間、ほぼ毎朝、
学校に行く前の6時から7時までの“朝練”で、
キャッチボールのパートナーを勤めてきたのだが、
その最中によく、「ウォエエエエ〜ッ!」という苦しそうな叫び声が、
街のどこかから聞こえてきた。
朝練の時間帯はまだ交通量や人通りが少ないため、
そういった大きな叫び声は、遥か彼方まで響き渡るのだ。
その都度、高瀬はその声にまっ先に反応し、
「ウォエエエエエ〜ッ!」と真似をしながら球を投じ、
俺もそれに呼応するように「ウォエエエエ〜ッ!」と言いながら球を投げ返した。
やがてそれが伝染し、チーム全員が「ウォエエエエ〜ッ!」と言いながら
キャッチボールをするようになり、
やがてコーチに叱られるのだが、それでも高瀬は懲りることなく、
コーチが遠ざかったころを見計らって「ウォエエエエ〜ッ!」と叫んで球を投げ、
コーチが「誰だ!」と振り返ると、高瀬は俺を指差して、俺がコーチに叱られる。
そんな茶番を幾度となく繰り返した。
やがてその「ウォエエエエエ〜ッ!」は、
特定の誰かが叫んでいるのではなく、
どこかの二日酔いのオヤジが、自宅のトイレか道ばたでゲロを吐いている
声だということがコーチ陣の入れ知恵によって定説と化し、
やがてチームの誰もが「ウォエエエエエ〜ッ!」には反応を示さなくなったのだが、
高瀬だけはいつまでもいつまでも、結局6年間、
その声に反応し、真似を繰り返していた。
練習中のみならず、学校にいる時も、何か機会があるごとに、
あるいはなんの脈絡もなく、「ウォエエエエエ〜ッ!」と叫んで、俺を笑わせた。
そして、これも小学生時代の話だが、
地元の文房具屋に一緒に行った時に、
高瀬が消しゴムのパッケージの「字消し」という文字を見つけ、
それを指差しながら、一人で爆笑していたことがある。
何が面白いのか?と聞くと、
「重次(しげじ)、重次の逆!ジゲシ、ジケシ!」
と言って、笑い転げている。
重次とは、俺の父親の名前である。
以後ずーっと彼は、
「ジケシ、この前、歩いてたよ」
「ジケシ、この前、図書館にいたよ」と、
実の息子からすれば「だからどうした。俺は毎日、家で見てるよ」
としか答えようがないニュースを、実に嬉しそうに、逐一報告してくれた。
(ある年令に達した頃から、「ジケシさん」と敬称が付くようになったが)
子供のころは、そうやってただ、面白いことを直感レベルでいち早く察知し、
それを馬鹿みたいに反復するだけの高瀬だったが、
大人になってからは、この子供じみた瞬発力と粘着力に、
年相応の鋭さというか、独自の洞察力や分析力も加わったようだ。
お互い、社会人になりたての23歳のころ、
2人でホテルニュージャパンの焼跡に潜入しようとしたことがある。
ところが、鉄条網を乗り越え、裏山を下り、
建物の一歩手前に差し掛かったあたりで、
敷地内にいた野良犬(番犬?)2匹に襲撃されるというハプニングがあり、
慌てて逃げ戻る最中、俺は眼鏡を紛失し、
高瀬は鉄条網に引っかかってスーツをビリビリに破いてしまった。
なんとか2人とも敷地外に逃げ切ったのものの、犬の鳴き声に気付いたのか、
どこからともなく警備員がやって来て、俺たちは路上で、
「中に入ったのか?入ったのなら不法侵入だぞ!」と、
20分ほど尋問を受けるハメになった。
結局、「入ってない!」とシラを切り通し、なんとか解放してもらったのが、
車で自宅に帰る途中も俺は、犬に嚼まれそうになった恐怖と、
警察沙汰になりそうになった恐怖と、メガネを失くしたショックで、
しばらく茫然自失の体だった。
だが、そんな中、高瀬は、
「あの警備員、絶対に呪われてるよ。何度も何度もおんなじこと言ってるしさ。
(肝試しでホテルの建物の中に不法侵入した奴らを一晩、10階の踊り場に閉じ
込めてやった、翌朝、見に行ったらそいつらがオシッコを漏らして泣いていた、
とか、肝試しの最中にあの犬に襲われて足の指を食いちぎられた奴もいる、
とかいう、本当だか嘘だか分からない話を確かに警備員は繰り返していた)
要するにアイツ、話し相手が欲しかったんだろ。
警察に言う気なんか、たいしてなかったんだよ。
だって俺たち、どう見ても、入ったのバレバレじゃん。
アイツ、サドだよ。俺たちをイビリたかったんだよ。
で、怖がる反応を見て楽しんでたんだよ。
途中でアイツ、ニヤニヤ笑ってたの見た?
あんなとこでずっと一人で警備してるから、おかしくなってんだよ。
呪われてんだよ。コェ〜!アイツが一番、恐ぇ!」
と、俺とはまったく違う部分にビビり、
短時間の観察のみで人をサドだと勝手に分析し、
そして、その警備員の顔マネ、声マネを、もういいよ!ってぐらいに繰り返した。
奇妙なものに敏感に食い付き、しかもしつこく、時に鋭い。
そんな彼が、“あの声”に反応しないわけがない。
今は昨日までの俺と同じく、韓国ガールズに御執心のようだが、
“あの叫び声”を実際に聞けば、必ずやこの男、食い付いてくるはず !
そして、なんらかの、直感レベルの分析を下してくれるはず!
高瀬を自宅に呼ぶことにした。
(つづく)