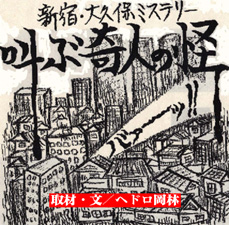
タイトル■叫ぶ奇人の怪
書き手 ■ヘドロ岡林
これはノンフィクションである。
叫ぶ奇人……、この怪物は実在する!
不夜城・新宿大久保に生息する
このミステリアスな怪物の正体に迫るべく
取材を重ね、その様子をリアルタイムで
報告していくのが、この企画の主旨だ。
繰り返す。“この怪物は実在する”!!
>バックナンバー
◇◇ 第八話 ◇◇
鳴かないペリカン
高瀬がやって来た。
約束通り、頑張って起きて、
昼過ぎに我が家にやって来た。
「隣、いる?」
これが、開口一番だ。
半年ぶりに俺に会ったというのに、
高瀬はまずまっ先に、
隣の韓国ガールズのことを聞いてきた。
俺は高瀬を家の中に招き入れつつ、
咄嗟に、こう嘘を付いた。
「いや、顔を見たんだけどねぇ、ブスだよブス。
全然、可愛くない。見る価値ないね」
高瀬は、それでもなお未練があるのか、
「タレントだと、ダレ風?」と聞いてきた。
俺は、ウ〜ン…と5秒ぐらい考えてから、こう嘘を付いた。
「もたいまさこみたいな感じ。ああいう、地味〜な感じ」
しつこい高瀬の執着を、断ち切らせるための嘘だ。
嘘も方便、ってやつだ。
さてここで、重荷にならない程度に、さらっと本題を切り出しておくか。
「でさぁ、前にチコっと話したけど、声ね。声。
無気味な叫び声を検証してほしいんだよね」
高瀬は人んちの冷蔵庫を勝手にまさぐりながら、こう答えた。
「どっから聞こえるの?」
「ベランダのほう。どこかは分らないけど、しばらくすれば聞こえるよ」
思惑通り、高瀬はベランダに出た。
よしよし。
が、人んちだと思って、
隣室のベランダを覗き込むようなマネをし始めたので、
「それだけはやめろ!」と制した。
「負い目を作りたくないの。だから、そういうことしないでくれ!」
「あっ、そう」
ちょっと残念そうな顔をした高瀬だったが、
左側の高層ビル群を発見するや、嬉しそうに大声を上げた。
「スゲぇなぁ、コレ!スゲぇ眺めだなあ!」
ベランダから上体を乗り出し、
馬鹿デカい声でそう叫んでいる。
このころ俺は、すでにその眺めには慣れ切ってしまっていて、
もうまったく感動などなかったのだが、
「だろ?凄いだろ?」と言いながら、
一緒にベランダに出て、あれが都庁で、あれが沖雅也が飛び下りたビルで、
あれが確か、東京モード学園のビルだと思う。で、あれが……と、
長ったらしい案内をしてあげた。
それもこれも、ベランダという“特等席”で、
高瀬にあの声を聞かせてやるための時間稼ぎだ。
さぁ、奇人よ叫べ!今こそ叫んでくれ!
「なんか他に面白いもんないの?面白いもん」
ヤバい!
奇人が叫んでくれないもんだから、
高瀬の関心が他のものへ移ろうとしている。
ポーン!タッタッ……チャッ!(カーテンを遮る音)
高瀬はまるで背泳のスタートのように
ベランダの冊をグイッと胸元に引き付けてから、
ポーン!と弾き、
素早くベランダから消え去ると、
今度は室内の物色を開始した。
「なんだこれは!なんだこれは!なんだなんだなんだ、これは!」
高瀬がニヤニヤ笑って、部屋の一角をまさぐり始めた。
あぁ、しまった!と思った。
そのころ俺は、アダルトビデオ批評の仕事をやっていて、
我が家のテレビの小脇には、
大小各メーカーから届けられた
サンプルビデオが大量に転がっていたのだ。
ちなみに俺たち2人は、
幼なじみであると同時に、古くからのAV仲間でもあった。
お互い板橋の同じ団地に住んでいたころはよく、
池袋で一緒にビリヤードをやって、終電を逃すと、
家まで1時間ほどかけて歩いて帰ったのだが、
その途中、要町にあるレンタルビデオ屋に立ち寄るのがお決まりの行事だった。
そこでお互い1本ずつ、好きなAVを借りるのだ。
で、お互い御近所同士だから、
1週間レンタルの間にそれを交換して、
ジャンケンで負けたほうが2本とも返しに行く、という、
セクシャル&リーズナブルな関係を長いこと続けていたのだ。
そういえば一度、こんなこともあった。
いつものように要町でAVを借り、
板橋の団地に辿り着いてから、
公園のブランコでしばし談笑し、
「じゃ、3日後あたりに(交換しよう)」と言って、
高瀬と別れたその30秒後、
自転車に乗った警察官が俺に背後から追い付き、
急ブレーキをかけて職務質問してきた。
近所で痴漢事件が起きたのだという。
俺、何も悪いことをしていないので、
「あぁ、そうなんですか。誰も怪しい人は見てませんよ」
などと呑気に応対していたのだが、
なぜか続々とパトカーが集結し、
「車を見るな!後ろを向け!壁に手を付いて後ろを向け!」
と高圧的に言われたのでその通りにすると、
後ろ姿をヘッドライトで照らされ、
「(パトカーに乗ってる)被害者の女性が、
貴方で間違いないと言っている。署まで同行願えますか」
と言われたのだ。
当然、俺、怒り狂って吠えまくったのだが、
なにしろそこは俺の自宅から目と鼻の先であり、
すでに何人かの住人が窓から顔を出し始めたので、
ここで騒ぐのは得策じゃないと思い直し、
「署まで行ってもいいけど、その代わり、アリバイを証言できる
友達も一緒に呼んでくれ。俺は職務質問される30秒前まで、
その友達と一緒にいたんだ」と要求した。
で、俺と高瀬はそれぞれ違う取調室に連行され、
かわるがわる、延々と、2人の刑事から取り調べを受けた。
何時に、どこで、何をしたのか…という1日の足取りを根
掘り葉掘り聞かれ、それに洗いざらい答えるのだが、当然、
AVを借りたことについても隠すことなく告白した。
恥ずかしかったが、怒りのほうが上回っていたので、
「刑事さんだって、AVぐらい見るでしょ? ね?
見たことないとは言わせませんよ。見ないほうが異常ですね」
などと挑発的なことを言ってみたりした。
すると刑事はこう言った。
「カバンの中、見せてもらえるかな」
「いいですよ、どーぞ、どーぞ」
俺、必要以上にふんぞり返ってそう答えたものの
カバンから取り出されたビデオのタイトルを見て、青くなった。
なんとそれは、俺が借りた覚えのない
“痴漢モノ”のAVだったのだ!
そう、それは高瀬が借りて、高瀬が最初に持ち帰るはずのものだったのに、
うっかりどこかで、俺のものと入れ違えてしまったようなのだ。
この後、取り調べ室の緊迫感が一気に高まったことは言うまでもないが、
ともあれ、明け方近くになって、俺たちはやっと無罪放免となった。
その帰り道、
「いやー、ホントに悪かったねー。助かったよ」
と高瀬に礼を言いつつ、
「そっちでは、どんなこと聞かれたの?」と聞くと、
彼は力強く、冗談抜きの真顔でこう答えた。
「バヤシ(高瀬は俺のことをこう呼ぶ)はどんな奴だって聞かれたからさぁ、
『あいつは昔から確かに変態だし、めちゃくちゃエロい奴だけど、
そんなこと(痴漢)は絶対するような奴じゃない!』って言ってやったんだ」
なんたる愚直さだろうか…。
取り調べが長引いたのも無理はない、と思った。
しかしその発言は、長年の交流により確固たる信頼関係を築いて
きたAV仲間としての、揺るぎのない、嘘偽りのない、
裏切りのない、心中覚悟の弁護であったように思えた。
刑事の心には響かずとも、俺の魂は揺さぶられた。
「われらAV仲間」の心の結束は、
これによって、より一層強まったように思う。
その尊い同志である高瀬が、今こうして、
俺の目の前でAVの山を発見し、嬉々としている。
そして、当然の権利であるかのように
「ちょっと見せろよ!」と言っている。
「見るな」とは言えないだろう。
いや、言おうと思えば余裕で言えたのだが、
ここで機嫌をそこねられたら元も子もないと思った。
「いいけど、音をちっちゃくしてね。近所に聞こえちゃうから」
と答えた。
近所に聞こえちゃうから、というのは建前で、
奇人の声が聞こえなくなっちゃうから、というのが本音だった。
・・・・・・・・
しかしそれにしても、何本見れば気が済むのだろう。
早送りしながらではあるが、
高瀬は次から次へとビデオを差し込み、
次から次へとイジェクトして、
「これは使える」「これは使えない」などと小声でつぶやき、
ビデオの山を2つに分け始めている。
そしてスキあらば、テレビ本体のボタンをカチカチ押して、
ボリュームを勝手に上げたりしている。
俺は呆れたようにベッドに横たわりつつ、
リモコンをがっちり握りしめ、
そんな高瀬の動きを監視し続けた。
結合部を夢中で眺める高瀬の後頭部を
俺は複雑な気持ちで眺めていた。
違うんだよ、そんなものを見てもらうためにお前を呼んだんじゃないんだよ。
頼む、鳴いてくれ!
俺をヨロつかせたあの日のように、
底抜け最大限のボリュームで、
オウムのように、ペリカンのように、
「バァ〜ッ!」と一発、鳴いてくれればいいんだ。
そうすれば、この高瀬も振り向くはず。
「アァァァァ、腹減ったぁ!メシメシ、メシ食いに行こ!」
高瀬はやおらそう叫んだかと思うと、すでに靴を履き始めている。
本能のままに生きているこの手の野獣タイプを
思惑通りに動かすのは難しい。
今さらながらではあるが、そんなことを痛感した。
結局、高瀬は、焼肉をたらふく胃袋に詰め込み、
「使えるビデオ」をたらふくデイパックに詰め込んで、
「眠い」と言って帰って行った。
役立たずめ!
しかしこの日、一番思惑通りに動いてくれなかったのは、
高瀬ではなく、奇人である。
高瀬が部屋にいる間、
俺はベッドに横たわりながら、左耳だけは常にアウトドアに傾けていた。
いつ鳴っても聞き漏らさぬよう、常に注意を傾けていた。
だが、いつもは快調に叫んでいる時間帯なのに、
その日に限って、ただの一度も叫び声が聞こえて来なかったのだ。
いや、まぁ、しかし、そうは言っても、
奇人を責めるのもお門違いだろう、と思った。
奇人と俺は、何も約束をしていない。
これは、俺が勝手に、一方的に、期待していたことなのだ。
そう、たとえるならばこれは、
雨、雨、降れ降れ、という雨乞いと、ほぼ同レベルの期待だったのだ。
雨が降らなかったからと言って空に文句を言ってもしょうがない。
当日、雨が降ると予想した天気予報士に文句を言えば
ちょっとはスッキリするだろうが、
奇人の元気予報士は誰あろう、この俺なのだから、
責められるべきは、俺である。
だが、そんな下らないことで自分を責める気にもなれない。
なんだか、イライラした。
雨が降ると思ってビニール傘を持って出かけたのに、
曇り空から晴れ間が覗いてきたかのような、
そんなイライラ感が募った。
もし、そんな時、もう邪魔だから要らねぇやと、
傘を本屋かなんかの傘立てに捨てたら、どうなるのか。
もうその本屋には引き返せないあたりに来てから、
急にドシャ降りの雨が降り始めるに決まってる。
イヤな予感は的中した。
役立たずな高瀬を駅まで見送り、
家に戻ると、奇声の集中豪雨が俺を待っていたのだ。
「バァ〜〜〜ッ!」
「ブォアァァァァァァァッ!」
「バ〜〜〜〜〜〜〜〜ア〜」
「バァ!」
いろんなバリエーションで、なんだか上機嫌に叫びまくっていた。
まるでそれは、
「ざまぁみろ」言っているように聞こえた。
(つづく)