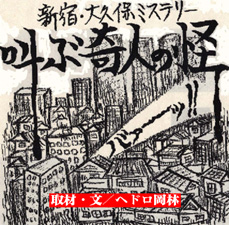
タイトル■叫ぶ奇人の怪
書き手 ■ヘドロ岡林
これはノンフィクションである。
叫ぶ奇人……、この怪物は実在する!
不夜城・新宿大久保に生息する
このミステリアスな怪物の正体に迫るべく
取材を重ね、その様子をリアルタイムで
報告していくのが、この企画の主旨だ。
繰り返す。“この怪物は実在する”!!
>バックナンバー
◇◇ 第九話 ◇◇
もう声が聞こえるなんて、言わないよ絶対
高瀬に分析を仰ぐイベントは、完全に企画倒れに終わった。
あと数時間、待ち合わせの時間を後ろにズラしていたら…!
あと数時間、家に居てくれれば…!
という具合に、「たら」「れば」を言い出したらキリがない。
そういう運命だったのだと、諦めるしかなかった。
まぁ、運がなかったのだ。
でも、何も慌てる必要はちっともなくて、
それ以後も頻繁に家に遊びに来てくれさえすれば
いずれは彼も「バァ〜ッ!」という叫び声を耳にすることが
出来たと思う。
彼の分析を仰ぐのは、実はそれからでも遅くなかったのだ。
だが、彼は彼で、仕事も恋人も持つ身。
実際問題、次に家に来られるのは、いつの話か分からなかった。
それが子供の頃との、友人付き合いの変化である。
子供の頃はそれこそ毎日、朝から晩まで一緒のメンバーで遊び続けたものだが、
大人になると、なかなかそうはいかないものだ。
仕事があるから、家が遠いから、その他の付き合いがあるから、
などなど、理由は複合的だろうが、
たとえお互いヒマでヒマで、
毎日一緒に遊びたくても、
毎日は一緒に遊ばないと思う。
それが大人同士の距離の取り方であり、遠慮であり、エチケットであるからだ。
俺も高瀬に「来週も来い!」とは言えなかった。
なんだか、そういう考え方はつまらないなー、と一抹の寂しさを感じた。
と同時に、この企画倒れから、俺は一つの教訓を得た。
もう自分からは、奇人の話題を出すべきではない、という教訓だ。
俺がどんなにクドクド説明したところで、
実際に聞こえないものには誰もほとんど興味を示してくれない、
ということを学んだのだ。
高瀬ほどの人物でさえそうだったというのは、
少なからずショックであったが、
でも、その事実を早いうちに知っておいて良かったと思った。
今回は、高瀬だったから助かった、とも言えるのだ。
たとえば、招いた客が、
まだ俺とはそれほど親しくない人物であった場合を想定してみる。
事前に俺からクドクド説明を受けたが、ちっとも叫び声が聞こえてこない。
すると、その招待客は、どんなことを思うだろうか。
心の中をシュミレーションしてみる。
(おいおい、ちっとも聞こえないぞ)
(つーか、そんなの別に聞きたくないんだけど…)
(岡林さん、なんだか焦ってるぞ)
(それって単なる、岡林さんの幻聴なんじゃないの?)
(てことは、この人、シャブでもやってんのか?)
(あるいは、私の気を引くための嘘?)
(いずれにせよ、岡林さんって、頭がちょっとおかしいのかも…)
(岡林さんとは、関わらないほうがいい…)
てな具合に、決して口には出さないだろうが、
心の中でセイ・グッバイされてしまう可能性が非常に高いと思う。
子供の頃、
「UFOを見た!」「幽霊を見た!」と盛んに言ってる奴は、
ほぼ例外なく、みんなから馬鹿にされ、最終的には孤立していた。
それとまったく同じ状況下に自分を追い込む危険性を秘めている。
それが「叫ぶ奇人の怪」であると悟ったのだ。
(つづく)