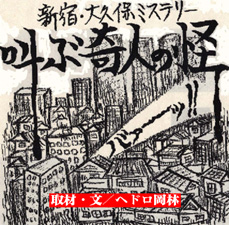
タイトル■叫ぶ奇人の怪
書き手 ■ヘドロ岡林
これはノンフィクションである。
叫ぶ奇人……、この怪物は実在する!
不夜城・新宿大久保に生息する
このミステリアスな怪物の正体に迫るべく
取材を重ね、その様子をリアルタイムで
報告していくのが、この企画の主旨だ。
繰り返す。“この怪物は実在する”!!
>バックナンバー
◇◇ 第十三話 ◇◇
ビッグ・ビジネス引き受けた!
しかし何事も、なかなか思惑通りには行かないものだ。
2000年、5月ごろ。
俺は一人、ヘドロ工房でワープロのキーボードを叩きながら、
そんなことをボンヤリと思っていた。
まず一つに、お部屋づくり。
引っ越して1年が経ち、必要な家具や備品は一通り出揃った感があるが、
なにやらどうも、理想とは程遠い部屋が出来上がりつつある。
「なんか違う」とも言えるし、「なんもかんも違う」とも言える。
冷静に見れば見るほど、「こんなはずじゃなかった…!」と頭を抱えたくなる。
原因は分かっている。
イメージをしっかり固めてから、お部屋づくりをしなかったからだ。
俺は当初、部屋を作るにあたって、
こんな部屋が格好いいかも…、というイメージをたくさん抱え過ぎていた。
イメージ1、未来世紀ブラジルに出てくるような、SFテイストの部屋にしたい。
イメージ2、ニューヨークにある探偵事務所のような、渋いテイストも取り入れたい。
イメージ3、香港にある観光案内所のような、賑やかなアジアンテイストも捨てがたい。
この3つのテイストがほどよく同居した空間など、まずあり得ないのだが、
当時の俺は、そこのところをよく理解していなかった。
好きなものを適当に集めていけば、
最終的にはどうにか調和するんじゃないかと、高をくくっていたのだ。
そう、俺は30歳まで、
両親に与えられた団地の一室で、
両親の洋服ダンスや母親の鏡台に四方を囲まれながら
(ついでに言うなら両親の愛に包まれながら)、
インテリアにはまるで頓着せずに、頓着のしようもなしに生活してきた男。
お部屋づくりに関しては、まったくのビギナーだったのである。
そして、ビギナーならではの浅はかさで、
ちょっとよさげなものを見つける度に、
「おっ、このゼットライトはSFっぽい」
「おっ、この壁時計はニューヨークっぽい」
「おっ、このポスターは香港っぽい」
と、次から次へと家具や備品を無計画に衝動買いし、
それらこれらを一つずつ並べていったら、
なにやらワケの分からない、
色彩もコンセプトもまるで統一感が取れていない、
オシャレさのかけらもない、
不細工で居心地の悪い部屋が出来上がってしまったのである。
ある日、その窮状を世田ヶ谷のオシャレな部屋に住んでいるデザイナーに相談したら
、
「部屋を作る際は、何か1色、ベースカラーを決めないとダメだよ」と言われた。
そんなのは、まったく決めていなかった。
だが、もう手遅れだろう。今さら全部の家具を買い替えるわけにはいかないからだ。
一番ショックだったのは、ウチに遊びに来た人に、
「お前の部屋は、まるで『気になる野菜』だね」と言われたことだ。
その人いわく、「オレンジだの、緑だの、黄色だの、なんだか野菜じみたいろんな
色のものがアチコチに転がっていて視覚的に落ち着かない、気が散ってしまうから、
気になる野菜」なのだという。
上手いこと言うと思ったが、笑えなかった。
俺はそんな路線を目指したつもりなどまったくなかったからだ。
俺が目指していたのはむしろ、そういうベジタブルな軟弱さとは対極にある、
スタイリッシュで、一本筋の通った、男らしい部屋だった。
だが、どう贔屓目に見ても、それは失敗だったと言わざるを得ない。
俺がインテリアにこだわる理由はニつあった。
一つは、部屋で年がら年中仕事をしているわけだから、少なくともその空間は、
自分好みの「城」である必要があると思った。居心地が良くないと、仕事の能
率が落ちるような気がしたのだ。
ニつ目は、そういう素敵なお城に、素敵な女性を連れ込んで、
ウットリさせたいという企みがあった。実はこれが一番重要だった。
部屋のムードでまずウットリさせ、その後、ベランダから見える西新宿の夜景
でウットリさせ、続いて、俺の会話でウットリさせ、
最後にダメ押しとばかりに、俺のベッドテクニックでウットリさせる……。
密かにそんな展開を夢見ていた。
ところが、現実はと言うと、
素敵とはまったく言いがたい部屋の中で俺はこうして働いており、
肝心要の素敵な女性も、この部屋にはただの一人も訪れていない。
そもそもその素敵な女性というのが、一体誰なのかもサッパリ見当が付かない状況だ。
しかし、何もかもが思惑通りにはいかない中、
唯一の救いは、こうして仕事をやれていることだ。
まがりなりにも、フリーランスとして1年やってこれた。
たった1年ではあるが、これは嬉しいことだった。
時にはあまりの多忙さゆえ、せっかく発注が来たのに、
「できません」と断ったことも。
それはよくないことだと分かっていた。
「一度断ると、そこからはもう二度と、仕事が来ないものと思ったほうがいい」
と、フリーランスの先輩から聞いていたのだ。
そんな折、1つの大きな商談が俺に持ちかけられた。
というと響きがいいが、具体的に言うと、
「エロ本丸ごと1册分の原稿を書いてほしい」
という依頼があったのだ。
俺は迷った。
120ページあるのだという。
それをたった5日間で上げろというのだ。
物理的には、絶対に一人では出来そうにない量だったが、
「誰かに手伝ってもらっても構わない」と言われたので、
俺は、先の先輩の言葉を思い出しつつ、
「分かりました。やってみます!」と、思いきってこれを引き受けることにした。
引き受けたはいいが、さて、どうしたものか。
手伝ってくれそうな人物を、頭の中で検索してみた。
エロセンスがあり、
なおかつヒマで
なおかつ金に困っており、
なおかつ文章力がある男。
この4つの条件を完全に満たす該当者は誰も思い浮かばなかったが、
一人、当たってみる価値がありそうな男がいた。
同じ大久保エリアに住む、通称・ポンちゃんだ。
2つ年下のポンちゃんは、
かつて同じ風俗情報紙の編集部で1年間だけ一緒に働いていたことのある元同僚で、
以後、ずーっと遊び友達を続けて来た。
俺が大久保で部屋探しをしていた際にあれこれアドバイスをしくれたのも彼である。
そのポンちゃんが先日、俺に電話をかけてきて、
「働いていたゲーム屋が潰れて、職を失くした」とボヤいていたのだ。
ポンちゃんは、エロセンスに関してはまったく申し分がなく、
もしまだ再就職先が決まっていなければ、ヒマで金にも困っていることだろう。
問題は、文章力だ。
彼は編集部所属だったものの、職種はカメラマンだったのだ。
とりあえず電話をしてみた。
するとポンちゃんは、まだ次の仕事が見つかっておらず、
俺の持ちかけたこの話にも「できればやりたい!」と食い付いて来た。
だが案の定、「ちゃんと書けるか分からない」と文章力については本人も不安を抱いていた。
俺としては、ぜひとも気心の知れたポンちゃんにこの仕事を手伝ってもらいたかったが、
肝心の文章があまりにもヘタクソだと、それを直したりするので二度手間になって、
余計に時間を食ってしまう。
だから、とりあえず、簡単な作文テストを実施してみることにした。
「今からウチに来て、試しに少し書いてみなよ。それで書くのが辛かったり、
読んで見て俺がダメだと判断したら、お互い正直に言えばいいじゃん?ね?」
10分後、ポンちゃんが自転車に乗って我が家にやって来た。
作文テストという言葉を聞いてビビったのか、かなり緊張している表情だった。
知り合って10年近くになるが、そんなポンちゃんの顔は初めて見た。
テストは、キャプション書きだ。
キャプションとは、写真の横に付ける説明文のことだ。
1枚の写真につき、100文字。
これを5枚分、書かせてみることにした。
「じゃ、ここ座って。ワープロ、使えるでしょ?」
「そんなの、使えるわけないじゃん。俺、パソコン持ってないもん…」
ポンちゃんの顔が曇った。
俺もその言葉を聞いてかなり不安になったが、あえてそれを悟られまいと、
「じゃ、手書きでいいよ。原稿用紙にさ、鉛筆で書いてよ」
と努めて明るく言った。
その取引先は、データ入稿でなくてもOKなのだ。
それでもポンちゃんは、女性の全裸写真と原稿用紙を交互に見つめながら、
「……いったい、どういうこと書きゃいいんだよ」
と言って、絶望的な表情になった。
女性器の写真を目の前にして、これほど深刻な顔をしている男も珍しいと思った。
俺はそんな彼をリラックスさせようと、
「とりあえずさ、便所の落書きと思えばいいよ。ポンちゃんがね、この女にどんなこと
をしたいのかを正直に、ありのまま、下品に書き殴ってくれればいいから。多少、文章
は(多少)荒くてもいいから、いやらし〜〜〜く、ネチっこくね。ね? 分かるでしょ?」
ポンちゃんは、うんともすんとも言わないから、
分かってるんだか分かってないんだかよく分からない。
大丈夫なのだろうか?
これ以上、俺が何かを言ったら余計にプレッシャーがかかると思い、
「じゃ、俺、ちょっと寝るから、終わったら起こしてよ」
と優しく告げ、ベッドに横たわって目を閉じた。
もちろん、寝たフリである。
心配で心配で寝てなんかいられない気分だったのだ。
ところがポンちゃん、いつまで経っても椅子に座る気配がない。
俺の家の仕事机の椅子は、座るとギギギギギッという音がするから、
目を閉じていても分かるのだ。
テストはもう始まっているというのに、いったいどこで、何をしているのか?
不安になって、薄目を開けて見て、驚いた。
そして思わず、感動のあまり、爆笑しそうになってしまった。
なんとポンちゃん、じゅうたんの上で、
ヨガみたいなポーズでテストを受けていたのである!
座禅を組んだまま上半身を前に90度倒し、
ヒザ先の床で頬付えをつく姿勢……
と言えばお分かりいただけるだろうか。
床に置いた原稿用紙のすぐ真上に、覆いかぶさるように顔があり、
左手はずっと頬杖を付いたままだが、
時折、思い付いたように右手で鉛筆を走らせては、消しゴムで消したり、
またしばらく両手で頬杖を付いて考え込んだりしている。
体の固い俺から考えれば、
そんな体勢は苦痛以外のなにものでもなく、
考え事や書き物をするには最も不適切なスタイルに思えるのだが、
実は、ポンちゃんがこの格好をしているのを見るのは、
このときが初めてではなかった。
前に誰かん家に一緒に遊びに行った時に、
ソファーがあるにも関わらず、
わざわざ床でこのヨガポーズをして、
見上げるようにテレビを見ていたから、
「なにやってんのお前、苦しくないのか?」と聞いたら、
「この格好をしてると一番リラックスできる。子供の時からずっとそう」
という意外な答えが返ってきて、
ふーん、変なの、と、思ったことがあったのだ。
なぜ俺が、試験中のポンちゃんを見て
感動したかお分かりいただけただろう。
つまりポンちゃんは、
不意に突き付けられたエロ作文テストという、
ワケの分からない緊張状態の中、
なんとか自分の力を最大限に振り絞ろうと、
自分が最もリラックスできるポーズを取って、
本気で大奮闘してくれていたのである。
それはとても感動的な姿なのだが、
取り組んでいるテストの内容を考えると、
やはりどうしても、見ているほうとしては、
とてつもない笑いがこみ上げ来てしまうのだ。
俺は、にやけた顔を隠すために、寝返り打った。
ビリッ! クシャクシャクシャッ! シュッ!ポン!
原稿用紙を丸めて投げ捨てる音が聞こえた。
どうやら、
ヨガポーズもむなしく、
作文は上手い具合にはかどっていないようだった。
俺は目を閉じながら、こう思った。
(ごめんね、ポンちゃん、無理言って)
(そんなの出来なくて、当然だよ)
(もう、ほどほどのところでギブアップしてくれて構わないからね)
(つづく)