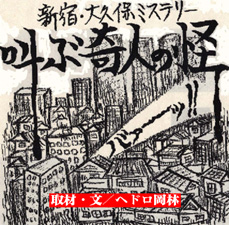
タイトル■叫ぶ奇人の怪
書き手 ■ヘドロ岡林
これはノンフィクションである。
叫ぶ奇人……、この怪物は実在する!
不夜城・新宿大久保に生息する
このミステリアスな怪物の正体に迫るべく
取材を重ね、その様子をリアルタイムで
報告していくのが、この企画の主旨だ。
繰り返す。“この怪物は実在する”!!
>バックナンバー
◇◇ 第十四話 ◇◇
ビッグ・ビジネス安請け合い!
ポンちゃんが厳しいとなると、
他に誰か、この仕事を手伝ってくれそうな人はいるのだろうか?
俺はベッドに横たわり、目を閉じながら、
頭の中で、次候補を検索し続けた。
現役バリバリの同業者の知り合いは、何人もいるが、
果たして、こんなムチャな仕事を引き受けてくれるだろうか?
俺としては、120ページのうちのせめて1/3、
40ページぐらいを誰かに振りたいと思っている。
最低でもそれぐらい誰かに手伝ってもらわないと、締め切りに間に合いそうにない。
いや、それでも正直言って、キツい。
できれば半分の60ページぐらいを、誰かにお任せしたいところだ。
しかし、そんな人は、誰も思い浮かばない。
皆それぞれにレギュラー企画の取材や執筆を抱えていたりして、
それどころの状況じゃないというのは容易に想像が付いた。
仮に、運良く、「今ならポッカリ暇だよ!」という同業者がいたとしても、
その人が、エロビジネスをよしとするかどうか、という問題が残されている。
「そんなのやりたくない」と言われればそれまでだし、
そんなこと言われたら俺が悲しくなってしまう。
となると、同業者以外の、気心の知れたエロ人間を当たるべきか。
学生時代の友人、むかし同じ職場にいた友人…。
何人か思い当たるフシはあったが、しかし、
そいつらが、文章が書けるかどうかはポンちゃん同様まったくの未知数だし、
これから5日間、ポッカリ暇だという保証はどこにもない。
むしろその確率は、限りなく低いと言っていいだろう。
どうするべきか。
とりあえず、片っ端から当たってみて、
ちょっとずつ何人かに押し付けてみるか。
いや、それじゃあまるで、マルチ商法にハマって、焦りまくってる奴みたいだ。
そんな人材探しだと、きっと何かが破綻する。
麻雀のメンツ集めと違って、
相手がタコであればあるほどこっちは大助かり、というものではない。
焦って、出来もしない人間をかき集めて、
仕事の質を落としてしまったら、元も子もない。
金が絡んでいるだけに、それが原因で友情にもヒビが入りかねない。
だったらもう、いっそのこと、
死んだ気になって、一人でやってみるか。
期限は5日間、一人で120ページ。
出来るのだろうか。
やったことないから分からないけど、
考えれば考えるほど、「それは断じて出来ない」と思えてくる。
というか、一人でやるなら、
こんなふうに今、ベッドで呑気に寝そべって考え事なんかしている場合じゃない。
とっとと起きて、今すぐ取りかからねば!
しかし、どういうわけか、体がまったく動かない。
こういう時は、無理は禁物なのかもしれない。
あぁ、なんだか俺は、とんだ安請け合いをしてしまったようだ…。
こういう時は、どうしたらいいのだろう?
5日後には、どうにか形になっているのだろうか?
・どうにかなるかな。
・・きっと、どうにかなってる。
・・・いつも、どうにかしてきたじゃないか。
・・・・・・・・・・・
考え事をしているうちに、俺は本格的な眠りに落ちてしまった。
よくあるパターンだ。現実逃避の睡眠である。
いったい何時間寝たか分からない。
ポンちゃんに揺り起こされた時、外はもう真っ暗だった。
「とりあえず、終わったんだけど…」
アゴに無精髭をたくわえたポンちゃんが、
にやけたような、バツが悪そうな表情で枕元に立っていた。
「あぁ…、おつかれさん。…いま何時?」
時計を見てアゴが外れるほどビックリしてしまったが、
「こんなに長時間かかったのかよ!」という一言は、なんとか飲み込んだ。
結果はどうであれ、その一言は間違いなく、相手を傷付けてしまうからだ。
それは、俺が人から何度も言われて
イヤな思いをしたからこそ知っている、
こういうシチュエーションにおける禁句だった。
だから俺は、平静を装って、笑顔でこう聞いた。
「どうだった? 大変だった?」
「…う〜ん、よく分からない。難しかった」
俺は枕元のSFチックなゼットライトを付け、眼鏡を装着し、
「じゃ、見せてよ。笑わないから」
と言って、400字詰めの原稿用紙を2枚、受け取った。
……むぷぷっ!
いきなり吹き出しそうになってしまった。
ポンちゃんの字があまりにも汚かったからだ。
死にかけた糸ミミズのような、そんな馬鹿丸出しの文字。
彼がこういう文字を書くということは昔から知っていたが、
今改めて、その糸ミミズがこうして一匹一匹、
原稿用紙というフォーマルな紙のマス目にキチンと収まり、
まるで標本のように並んでいる様を見たら、
なんだか無性に可笑しくてたまらなくなってしまったのだ。
「笑わないって言ったのに! 変…? やっぱダメ…?」
ポンちゃんは真っ赤な顔になり、
両手をジャブのように繰り出しながら、
原稿用紙を俺から取り上げようとしている。
「違う!違う!内容じゃない!字だよ、字!字で笑ったの。まだ読んでない!」
俺は、いきり立つポンちゃんをひとまず制し、
原稿に目を走らせようとした。
しかし、ポンちゃんが目の前でモジモジ動き回っているから、
ちっとも落ち着いて読めない。
俺が顔を上げると、ポンちゃんがその動きを止め、
許しを請う子供のような目付きで「ダメ…?」と言ってこちらを見つめる。
また読むフリをして、すぐさまパッと顔を上げると、
また同じ表情でこっちを見て「ダメ…?」と言う。
そんなことを5〜6度繰り返してから、
「進まねぇよ!」と言って2人で爆笑した。
「とりあえず、そこのソファーに座ってろ!もう二度と、俺の顔を見るな!」
そう力強く命じてから、俺は仕事机の椅子に腰掛け、原稿のチェック作業を開始した。
ちなみにここで我が家のレイアウトを簡潔に説明すると、
壁を背にする形で仕事用の椅子があり、その前に仕事机があり、
その仕事机の前面を覆い隠すような形でソファーが置いてある。
分かりにくいだろうか。
とにかく、仕事用の椅子の背もたれと、
ソファーの背もたれは同じ方角を向いているため、
両者ともに普通に前を向いて座っていれば、目が合わない配置になっている。
それでもポンちゃんはやはり、
落ち着いてソファーに座っていられないのか、
時折、クルッと体を反転させて、パソコンとプリンターの隙間から、
こっちを覗いては隠れ、覗いては隠れ、を繰り返している。
2回目までは反応してやったが、3回目からはあえて無視して、
原稿を真顔で読み始めるフリをした。
(遊びはもう終わりだぞ)という意思表示だ。
ポンちゃんもそれを悟ったのか、諦めたようにテレビを見始めた。
でも実際は彼、気が気じゃなくて、テレビなんか目に入らない心境だったと思う。
いや、そうに違いない。
なにしろ100文字のキャプションを5本書くのに、彼は5時間も費やしたのである。
よほど苦労したのだろう。それはそれはもう、大変な労力だったと思う。
ポンちゃんの頭の中は、
(これだけ頑張ったのに、「ダメだ」「使えない」と言われたらどうしよう…)
という不安感でイッパイだったに違いない。
だからこそ、俺としても、うかつなことは言えないと思った。
ハッキリ言って、
これだけの分量のものにこんなに長時間を費やしている時点で、
もう読むまでもなく、
ポンちゃんは今回の助っ人ライターとして「失格」だった。
だが、これは、企業の採用試験とはワケが違う。
「縁がありませんでした」という書面を後日郵送すればいいって問題じゃない。
受験者は俺の友人であり、なおかつその友人がいま俺の目の前で、
ハラハラしながら結果が出るのを待っているのである。
「たかがエロ作文」だが、「たかがエロ作文」だからこそ、
こちらの出方次第によっては、救いがなくなってしまうのだ。
俺はこのあとポンちゃんに、一体なんて告げたらいいのだろう?
原稿を読んでいるようなうつむき加減のポーズを取りつつ、
実は俺、原稿はまったく読まずに、そんなことばかりを考えていた。
(つづく)