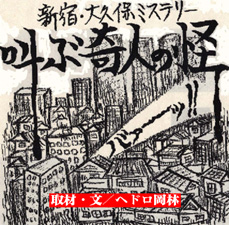
タイトル■叫ぶ奇人の怪
書き手 ■ヘドロ岡林
これはノンフィクションである。
叫ぶ奇人……、この怪物は実在する!
不夜城・新宿大久保に生息する
このミステリアスな怪物の正体に迫るべく
取材を重ね、その様子をリアルタイムで
報告していくのが、この企画の主旨だ。
繰り返す。“この怪物は実在する”!!
>バックナンバー
◇◇ 第二十三話 ◇◇
エ ピ ソ ー ド 3
「馬の霊??? なんだそれは?」と俺。
「俺もよく分からねぇ。でも、うちの母ちゃんがそう言ってた」と高瀬。
高瀬によると、こういうことらしい。
満里ちゃんがある日突然、登校拒否になったそうだ。
学校でイジメられたとか、そういう問題があったわけでもないのに、
急に家から一歩も外に出なくなり、食事もほとんど取らなくなった。
心配したお母さんが、満里ちゃんをいくつかの病院に連れていったそうだが、
「どこも悪くない」という診察結果が出るばかり。
しかし満里ちゃんの容体は待てど暮らせど良くならない。
そこでお母さんは、藁にもすがる思いで、
とある神社に満里ちゃんを連れて行ったそうだ。
するとそこの神主が、
「彼女は動物の霊に取り憑かれている」と言ったのだという。
そして、「私にはどうすることもできない」とも。
そこで、この神主に紹介された霊媒師のところへ連れて行くと、
「これは『埼玉の馬の霊』だ」との診断を下され、
除霊の儀式(詳細は不明)を受けたのだという。
なんだそりゃ?という感じだが、
高瀬いわく、
「そしたら治ったらしいよ。
ちゃんと満里ちゃん、元気になって、学校に行くようになったんだって」
めでたし、めでたし?
いま思い出しても胡散臭い話なのだが、
当時中学生だった俺は、この話を聞いて、「ふ〜ん…」としか答えられなかった。
「埼玉の馬の霊」という、
やたら具体的かつ迫力満点なフレーズに恐れおののき、絶句してしまったという感じだ。
納豆好きの純朴少女が、ある日突然、
何の因果か、邪悪な霊のターゲットにされる。
その理不尽さにただただ恐怖し、茶化すことなどできなかったのだ。
この話を俺に伝える高瀬自身も戸惑っているようだった。
ニュースソースが他ならぬ「自分の母親」なので、
そんなの嘘だろ!と一笑に付すことができなかったのだろう。
俺は念のため、家に帰ってから自分の母親に
「満里ちゃんが除霊してもらった話、知ってる?」
と聞いてみたら、こんな答えが返ってきた。
「知ってるけど、人に言っちゃダメよ。もう解決したことなんだから」
もうその話題には触れないで!ワケが分からないんだから!と母親の顔には書いてあったが、
あえて「お母さんは、本当の話だと思う?」と聞いてみたら、
「信じられないけど、金村君のお母さんがそう言ってるんだから本当なんじゃないの?
そういう不思議なことって、ひょっとしたらあるかもしれないでしょ」
というような答えが返ってきた。
まったく同感だった。
世の中には科学では解明できない不可解なことが本当にあるのかもしれない、
と思うしかなかった。
それまでテレビの心霊特集などを見てもいまいちピンと来なかった俺だが、
いざ身近な顔を知っている人間がこうして怪奇現象に巻き込まれたとなると、
それを頭ごなしに否定する気にはなれない。
むろん、いまだもって、半信半疑ではあるのだが……。
(エピソード文中、一部仮名)
◇ ◇ ◇
……という長ったらしいエピソードを粘着質に語りかけ
(web上でも半年もかかってしまったが)、
ポンちゃんを笑わせ、ビビらせ、絶句させてから、俺はこう言った。
「だからね、霊媒師ってのも、あながちインチキとは限らないと思うんだよね。
ホンマモンが、どっかにいてもおかしくないと思うわけ。たとえばそれが、
この大久保にいたって、おかしくはないと思うんだよね。だろ?」
ポンちゃんは「おかしくない!」とわざと大袈裟に同調しつつ、
「しっかし、その金村って一家は、呪われてるな。
妹を脱がせる話といい、納豆といい、馬の霊といい、
どれもこれもロクでもない話ばかりじゃないか。
ひょっとしたら全部、岡林が悪いんじゃないのか?
一休さん歌わしたりするから、そんなことになっちゃったんだよ。金村、可哀想!」
と言って、俺を責め始めた。
俺の責任なのか? いや、そうだとは思いたくない。
仮にそうだとしても、20年以上前のことだからもう時効だと思いたい。
金村一家のその後の安否に思いを馳せ、
気分が一瞬ドンヨリしかけたが、ここで曇った顔をしてしまうと、
ポンちゃんに付け込まれてしまい、話がまたあらぬ方向へと脱線してしまう。
とっとと話題を本筋に戻そう。
こういう時は、真面目な顔して真面目な話をするに限る。
「でね、仮に奇人が外資系の霊媒師だとしよう。
じゃあ、そいつは何人(なにじん)なんだ?……って話だよ。
『バァ〜ッ!』という言葉の意味。実は俺、これについては、
ちょっとした調査を進めてたんだよね」
と言って、俺はパソコンの電源を入れた。
(つづく)