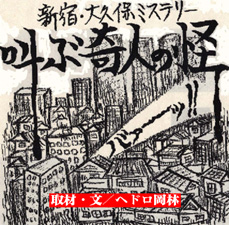
タイトル■叫ぶ奇人の怪
書き手 ■ヘドロ岡林
これはノンフィクションである。
叫ぶ奇人……、この怪物は実在する!
不夜城・新宿大久保に生息する
このミステリアスな怪物の正体に迫るべく
取材を重ね、その様子をリアルタイムで
報告していくのが、この企画の主旨だ。
繰り返す。“この怪物は実在する”!!
>バックナンバー
◇◇ 第二十六話 ◇◇
ピッ(1)ピッ(1)ピッ(0)
ピッ(1)ピッ(1)ピッ(0)………トゥルルルルル…、トゥルルルルル…、トゥルルルルル…
「はい、警察です」
「あ、もしもしっ、ちょっと相談したいことがあるんですけど、いいですか?」
「なんでしょう」
「あの、事件ってわけじゃないんですけど、事件かもしれない…ってことが近所でありまして」
「どうぞ、おっしゃって下さい。あ、その前にお名前と現住所ちょうだいできますか?」
「あっ、岡林と言います。住所は新宿区北新宿×−×−× ××××です」
「電話番号は、いま通知が出てる番号でいいのね? これ、ご自宅から?」
「あっ、そうです。はい」
「で、なんでしょう? おっしゃって下さい」
「あのですねぇ、近所で奇声が聞こえるんですよ。どこから聞こえてくるかは
よく分からないんですけど、
その、なんちゅーか、ただならぬ気配の奇声なんです」
「喧嘩か何かですかね?」
「いや、喧嘩じゃないと思います」
「今も聞こえるんですか?」
「いや…今というか、もうかれこれ1年以上前から断続的に聞こえてくるんですよ」
「1年以上ッ?? ……えーっと、なんて叫んでるのか分かります? 助けを求めてるの?」
「あのですねぇ、ちゃんとした日本語じゃないんですけど、『バァ〜ッ!』って…」
「はいっ?」
「ですから、『バァ〜ッ!』って…。
このへん、外国人も大勢住んでるから、ひょっとしたら外国語かもしれないんですけど……」
「で、なに。それはあれじゃないんですかね。酔っぱらいとかじゃないんですかね?」
「いやぁ、たぶん違いますね。なんちゅーか、苦しそうな時とかあるんですよ」
「病気か何かじゃないの?」
「いやっ、う〜ん、それはなんとも言えないんですけど、とにかく、ちょっと心配というか……。
なんか苦しそうな時とかもあるから、ひょっとしたら、監禁とか」
「…うん??」
「ほら、新潟でこないだあったじゃないですか?
あの、少女が何年間も監禁されてたって事件が。僕の考え過ぎかもしれませんけど、
もしそういうのだとしたら一刻も早く手を打ったほうがいいんじゃないかなと思って、
こうしてお電話さしあげたんですよ。
いや、もしかしたらね、なんでもない可能性ももちろんあるんですけどね。
ま、そのほうがね、平和なほうがいいんですけどね…(シドロモドロ)」
「えーと、えとえと、ちょっといい? ちょっといい? 若林さん…じゃなくて岡林さんだっけ?
ちょっと落ち着いて聞いて欲しいんですけど、貴方はなんで、それが監禁だって分かるわけ?
なんか具体的な証拠というか、怪しい連中を見たとか、そういうことはあるんですか?」
「いやっ、まったくないです。…けど、それこそ長期に渡って、子供の頃から監禁されていれば、
まともな言葉を発することができないんじゃないかと。まぁ、これは今、友達と話してて、
その可能性もあるってことになって、一応こうしてお電話させて頂いてるんですけど……
その友達も今、横にいるんですけどね」
「……う〜ん、正直、おっしゃってる意味がよく分からないなぁ………」
「(この言い草にカチンと来て)ですからぁ、僕もなんだかよく分かんないですよ!
確かに分かんないですけど、万が一、ってことがあるじゃないですか。
だから電話してるんですよ!」
「えーと、岡林さんでしたっけ? 岡林さん。う〜ん…………、
今みんな出払っちゃってるんだよなぁ、どうしよっかな。
……えーっと、本日は何時頃までご自宅にいらっしゃる?」
「ずっと居ますよ」
「あっ、そう。じゃあいっぺんね、うちの署の者をね、今日中にそちらへよこすから。
そこでね、どういう状況なのか具体的に説明して貰いたいんだけど。
で、その変な声出してる人はご自宅から見える場所にいるのかな?」
「いやっ、まったく。僕、1年以上ここに住んでるんですけど、声の主は一度も姿を
現してないんですよ。だから怖いんですよ。怖いというか、かなりの近所迷惑なんですよ!
(実はそれほど迷惑してないのだが嘘をつく)」
「……じゃあ特に今のところ事件は起きていないのね? 声が聞こえるだけなのね?」
「ええ、そうですけど、でも迷惑なんですよ。みんな気味悪がってるんですよ!(とまた嘘をつく)」
「……じゃあですねぇ、え〜っと、今から1時間以内にね、署の者をそちらへよこしますから、
そこでね、今おっしゃったことをね、もう一度説明して貰えますか? ちょっとね、私が行けるか
どうか分からないから、たぶん違う者が行くことになると思うからね、そこでね、分かりやすく
説明してあげてよ。ね? じゃあ、署の者が来たらね、よろしくお願いしますよ」
「……あ、はい。では(ガチャ)」
────1時間20分後
ピンポ〜ン! ピンポ〜ン!
俺「はいっ! もしもし」
刑事A「あ、警察の者です。お邪魔してよろしいでしょうか?」
俺「あッ、どうぞ。どうぞ。今開けます!」
カチャッ…
刑事A「お邪魔します」
刑事B「あ、お友達もいらっしゃるの?」
ポン「あっ、どうもご苦労様です(ひきつり気味の照れ笑い)」
刑事A「ある程度、お話は聞いたけど、その声ってのはどこから聞こえてくるんですか?」
俺「ベランダのほうですね。どうぞ、どうぞ。お上がり下さい。こっちです、こっちです」
────ベランダにて事情をザックリ説明
刑事A「ふ〜ん、で。それはどういう声なの?」
俺「『バァ〜ッ!』です」
刑事B「えっ?」
俺「いやっ、…ちょっと違うかな。『ブォァアアアッ!』かな」
刑事B「…ホントにそんな声なの(笑)?」
俺「ええ、本当ですよ。なぁ、ポンちゃん(と言って盛んに同意を仰ぐ)」
刑事B「どっちのほうから聞こえるのかな?」
俺「この……たぶん下のほう…か、それとも正面のマンションのあの左側の裏側あたりだと
思うんですけど、はっきりとは分からないんですよ…。
僕らもいろいろ調べてるんですけど、サッパリで」
刑事B「マンションの裏側って……あんなところに監禁したって逃げられるでしょ(笑)」
俺「いや、だからあそこだとは断定してないじゃないですか。
ホント、どこだか分からないんですよ。声が反響するから」
刑事B「……それにしてもいいとこ住んでるねぇ。ここ家賃いくら?」
俺「8万2000円です」
刑事B「高いなぁ! 学生さん?」
俺「いえ…、一応、社会人ですけど」
────ベランダで雑談数分
刑事B「………全然聞こえないねぇ」
俺「おかしいなぁ(と言って無意味にベランダから下を覗き込む)」
ポン「さっきまで聞こえてたのになぁ。アイツ、お巡りさんが来てるからビビッてるのかなぁ
(などと精神的余裕のなさから、つまらない冗談を言う)」
刑事A「……………」
────それから10分経過。結局奇声は一度も聞こえず、4人は室内に戻る
刑事B「ところで今日は平日だけど、お2人は何をしていたの?
さっきお仕事やってるって言ってたよねぇ」
俺「…ええ、自営なんですよ。家でやってるんですよ」
刑事B「あっ、そう。ここで? ふ〜ん………」
────饒舌な刑事Bを尻目に、刑事Aは無言で室内をキョロキョロ
刑事A「……これ、本物?(と言って、室内の壁に飾られたモデルガンを眺める)」
俺「いや、まさかー。そんな部屋にお巡りさんを呼ぶわけないじゃないですかぁ(と
言って自分で笑う)」
刑事A「(まったく笑わず、むしろ憮然。そして今度は床に転がっている無数のエロ
ビデオに気付き)……こういうの、好きなんだ?」
俺「嫌い…じゃないですけどね、まぁ、それも、仕事絡みというか……(ヘドモド)」
────帰り支度をする刑事2人
俺「お疲れさまでした。なんか、無駄足になっちゃったみたいですいませんねぇ……」
刑事B「(靴を履きながら)うん? ああ、いいですよ。またなんかね、あったら電話して下さいよ」
俺「あっ、はいっ。その時は必ず(二度と呼ばねぇ)」
刑事B「……うん? この紙、Aさんの?
(と言って、玄関に落ちていたクシャクシャの紙切れを拾い、無造作にそれを広げようとする)」
俺&ポン「あっ! ちょ…ちょっ…ちょっと、それは…!」
刑事A「うん………? 見られちゃマズいものなの?」
俺&ポン「……って、わけでもないけど……」
刑事A「…………じゃあ、見せてもらうよ!」
バオーーーーーーーーーーーーーーン!!!
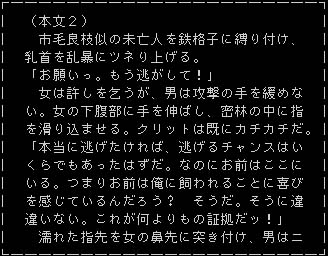
(ポンちゃんが床に丸めて捨てた熟女凌辱モノのボツ原稿用紙)
刑事A「……キミたち、一体全体、いつもここで何をやってるんだ?」
刑事B「ちょっとお2人、悪いんだけど、署までご同行願えるかな?」
◆ ◆ ◆
「……みたいなことになりかねないから、警察には言いたくないッ! 警察はダメだッ!」
と俺は叫んだ。
ポンちゃんは笑い転げている。
「いいじゃん、いいじゃん、それはそれで面白いじゃん!
かけようよ、警察に! 警察最高ぅッ!」
などと叫びながら踊るように立ち上がり、
ベッドの脇にある俺の携帯電話を素早く奪い取ると、
ピッ(1)ピッ(1)ピッ(0)とボタンを押し、
その数字が表示された画面をわざわざ俺に見せつけてから、
発信ボタンを押すフリを何度も何度も繰り返し始めた。
ここが自分ん家じゃないのをいいことに、
どんなハプニングも大歓迎!とんでもないことが起きれば最高!
とばかりにはしゃぎ回るポンちゃんが非常にうとましく思えたので
(俺が逆の立場だったらまったく同じようなことをしたに違いないのだが、
ここは俺ん家なので話は別なのだ)、
「はいはい、わかった、わかった。返して、携帯」と冷たく言うと、
「アッ、間違って押しちゃった!繋がっちゃう。あとは岡林よろしく!」
と言って携帯を投げてよこす。
画面を見てみたら「110」の数字が本当に呼び出し中の点滅をしていたので、
慌てて電話を切ってからポンちゃんの弛んだケツを思いきり蹴飛ばした。
「警察はダメだっつってんだろ! このドアホ! 超馬鹿!」
ポンちゃんは「イテテテテ…」と言いながら
痔持ちの老人のように顔を歪めながらゆっくり床に座り込み、そのまま沈静化した。
まったく反省などしていないに違いないが、
とりあえず俺が2歳ばかり年上だということもあり、
こういうお仕置きをされた後だけは、従順になったフリをするのである。数時間だけ。
ところで、言うまでもなく、上記の警察とわれわれのやりとりはすべて空想だ。
最悪の展開を想像して、
面白可笑しく大袈裟にポンちゃんの前でそれを演じてみせたに過ぎないが、
実際に通報した場合も、ここまで酷くはないにしても、
これに近い展開になるのはなんとなく目に見えている。
どうせ奇人は鳴かないのだ、そういう“ここ一番”という時に限って!
そして、藪蛇になるのがオチなのだ。
そうに決まっている。
だから警察には言いたくないと思った。
いや、というよりも、
俺が発掘したとっておきの“宝物”を
そうやすやすと国家権力などに譲ってたまるか!
という思いのほうが強かったかもしれない。
ポンちゃんの尻の痛みが引いた頃に、ちょっと優しい声で、
「どうやるかはさておき、まずは自力で調べるべきだな。
俺とお前でなんとかさ、知恵を絞ってさ、奇人の正体を突き止めようぜ」
と提案したら、ポンちゃんはちょっと嬉しそうに微笑んで
(俺の怒りが早くも引いていることに安堵して笑みがこぼれただけかもしれない)、
黙ってコクリと頷いた。
かくしてその翌日あたりから、
われわれはさっそく“自力調査”めいたことを始めるのだが、
すぐさまそれは、とんでもない方向へ脱線していくことに……。
(つづく)