第二講 馬装について
さて、今回は馬に乗る時につける「馬装」についてお話しましょう。
馬装とは、何を指すのでしょうか。皆さんはたぶん、鐙や鞍、手綱などの名前は知っているでしょう。馬装とは、それら馬につける馬具のことです。
まずはこの図を見てください。
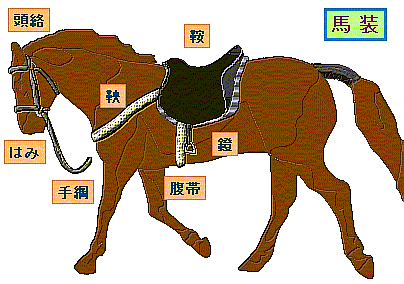
大体何処にどんな馬具をつけるかが、これでわかるでしょう。では、一つずつ軽く説明してゆきます。
- 頭絡(とうらく)
- 面繋(おもがい)ともいいます。物によって形が違いますが、「額革」、「頬革」、「鼻革」、「顎革」、「項革」で構成されています。これに「はみ」と「手綱」がついて1セットです。ちなみにもっと簡素(主に素材は布や紐で、一体型)で「はみ」の無いものを「無口」といいます。騎乗用馬具ではなく、手入れをするために牽いていく時などに使います。その時に繋ぐ紐を「引き手」といいます。
- はみ
- 下図を見てください。
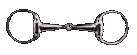
この真ん中の金属棒を、馬の前歯と奥歯の間――ここは隙間が空いています――にくわえさせ、両端の輪に頬革や手綱を繋ぎます。この部分が轡(くつわ)です。馬にとって一番嫌いな馬具がこれでしょう。 - 手綱(たづな)
- 馬を制御するための馬具です。
- 鞍(くら)
- 人が乗る為、そして馬の負担を減らす為の馬具です。下にゼッケンと呼ばれる敷布を敷きます。これに最低「腹帯」、「鐙」がついていないと役に立ちません。
- 腹帯
- 鞍を固定する為のものです。馬にとっては、「はみ」と同じか次くらいに嫌な馬具でしょう。これをちゃんと締めないと鞍が安定せず、人馬双方にとって不愉快な事になります。
- 鐙(あぶみ)
- 「鐙革」で鞍に装着します。これに足を入れて身体を安定させます。
- 鞅(むながい)
- 主に鞍の装着を補助します。
ざっと説明しましたが、おおよそわかりましたか? 色々と細かい用途などは中級で述べたいとおもいます。時間になりましたので、本日はここまで。
それでは皆さん、さようなら。