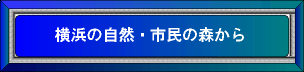
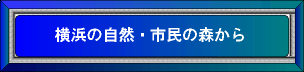
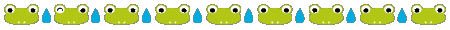
 | 
|  |
ドングリが落ち始める頃、燕、サシバ、不如帰に代わり、北から鴨などがやって来ます。九月中旬、横浜栄高校を少しあがった尾根道上空を、燕が二三十羽輪を描くように飛び回っていました、もうすぐ南へ渡るのでしょう。(97年)
青いドングリが落ち始めているのにまだツクツクボウシがないています。 9月末になって、麓の日野中央あたりにもモズが姿を見せ始めました。10月末に元港南環境センターの裏山から瀬上池へ下る途中の休憩所で、桜に止まっているカシラダカをみつけました。 この近くに20メートルくらいの椎の木があますが、この頃になると実を見つけることは困難です。野鼠もリスも人も食べられるこの実が大好きらしく、落ち葉をかき分けようやく一つ見つけることができました。
横浜自然観察の森にもツブラジイやスダ椎が多く木の下で実を沢山見つけることが出来ます。他のドングリは10月の初め頃は未だ青く熟していないので落ちていません。実は他のドングリより小さく椎の葉と比べると大きさがよくわかります。
 | 
|  |
瀬上池の上流から馬頭の丘休憩所を経て梅沢休憩所を周り円海山へ戻ってくる道筋には、常緑広葉樹のアラカシの縦縞模様のはいったそしてときには帽子のようなへたをかぶった実や、落葉広葉樹のコナラの実のドングリがたくさん落ちています。丸くて独楽を作れるクヌギのドングリは少なめですが円海山の元NTT施設があったあたりで見かけることが出来ます。瀬上池下の広場の東屋の側でたわわになったサルナシの実があり、見上げるとリスがそれが巻き付いている木の枝を伝わって逃げていきました。
この前の台風で、梅沢休憩所の近く、相当広く木を伐採した東電の鉄塔工事現場あたりでコナラの倒木を沢山みました。森が切り倒されたため周りに大きな影響がでたのではなかったのではないでしょうか。コナラは途中から折れているわけではなく、本の根がもろい岩状の土から浮き上がって全体が引き抜かれたみたいに倒れていました。柔らかい土と硬い土の間に雨が入っため強い風ではがされてしまったようです。一本の鉄柱を建てるのにその面積の数十倍の木々が伐採された景色はなんともやりきれないものです。倒木の何倍もの木々、太い桜などが切り倒されているのを見ると元に戻るのには何十年もかかるのではないでしょうか。
9月の終わり頃に目立つ赤い実を付けるのはクサギです。薄暗い森のなかでよく目立ちます。にたような実をつけ黒い種がのぞいているゴンズイやマユミもあります。
2002年10月の半ばに久しぶりに横濱自然観察の森を訪れました、鳶が2羽上空をぐるりと輪を描いていました。アキニレ、ノブドウ、ヤシャブシ、トベラの実などが目立ち始めています。帰途初めてイヌガヤに気が付きましいた、赤い実が沢山なっていて西日が差し込んでいなければ気が付かなかったことでしょう。今年はシロダモが沢山赤い実を付けています。
 |
 |
 |
10月の下旬ともなるとこの森の木々も所々で色づき始めます。前日の雨のせいかドングリが沢山落ちています。アカガシの実はとても綺麗でコナラの実に比べるとやはり赤みが多くやや大柄であるなどと両方手のひらに載せてみると比較出来るが個々に見ても判定するのは難しいです、落ちているところで木を見ているから判るだけです。
2000年の今年は柿が生り年らしくビワ程度の実を鈴なりに付けているのが幾分色づいてきていて青空に良く映えています、熟すのを小鳥やリスが待っているかのようです。近くの5メートル以上もあるシロダモも上から下まで赤い実を見事に付けています。
ふとその横をみるとムラサキシキブの実があります、木をみると実に高くて大きい、10メートルちかくもあります、ムラサキシキブがこんな高木になるとは始めて知りました、上方が色鮮やかに実を沢山付けていたので気が付きましたが幹だけ見ていたら解らないと思いました。人の背丈位のものが普通見られるものなのでこんなに高くなるものと解り嬉しくなりました。クサギも赤紫の花のような実を沢山付けています。そういえばいつも薄桃色の実を鈴なりにつけるマユミは去年に続きことしも実を付けていませんでした。
11月中旬になると落葉が始まりました、よく目立つのは黄色く色づいたいわゆるモミジ形のハリギリの葉です。コナラの葉もドングリに混じり少しずつ落ち始めています。
下旬には瀬上池の周りのイロハモミジが鮮 やかに色付き池の面に映えとても綺麗です、昼過ぎ南から程良い光の差すので葉を透過し鮮やかな色になります。池上流の草地の日溜まりではこの時期でも白や黄色の小さな蝶やアキアカネを見ることが出来ます。
馬の背休憩所の近くでマユミの実が鈴なりになって見事に桃色に色付き、少し離れてみると新芽か花の蕾のように見えていました。そこから瀬上池へ下る道の途中に真っ赤に色づいたヤマハゼの葉が落ちていて手に取ったところ後でかぶれてしまいました。ハウチワカエデの葉も落ちていましたがそのあたりは高木が多くてその木を認めることが出来ませんでした。
横浜栄高校から海上保安庁通信所までの途中沢山のヤマブドウが紅葉しそして実をつけていました。(97年)次の年の(98年)夏は沢山青い実をつけていたのに稔る前に皆落ちてしまい秋には赤い実を付けた木を見つけることが出来ませんでした。
98年11月の中旬アキグミの小さな実が赤く色づき始めました。横浜自然観察の森や氷取沢から金沢自然公園へ行く途中などでこれをよく見かけることが出来ます。
久しぶりにひようたん池を訪れました、二羽しかいなかったカルガモが四羽になっていました、(96年)98年は鴨も4羽いて計8羽いる日がありました。
 |
 |
 |
ハマヒサカキは気味の悪いほど花も実もびっしりつけるのですが今年は一段と多く、白い小さな花も沢山咲いて、黒熟した実もありました。
3メートル位のグミの木が小さな赤い実を沢山付けていました、広場に同様な木が3本ありますが実を付けているのはこの1本だけてした、小鳥がやってこないところを見ると、未だ熟していないのでしょう。
トベラも黄色になった実を沢山付けていて、所々実が割れていて赤い種が見えています、ムラサキシキブの10メートルくらいの高木があり、見上げると実が沢山付いています、実が豊かなときは鳥やリスでなくても嬉しくなります。
今年は黄葉も綺麗で、コナラが特に良いです。イロハモミジも紅葉し始めました、ヤマウルシも全体が紅葉しているので緑の木立に映えて実に見事です。麓のニシキギ、ドウダンツツジ、モミヂバフウ、カツラ、ケヤキなど植樹された木々も今年は色が鮮やかですが、森の木々も同様でイロハモミジなどこれからが楽しみです。
以上は2002年までの観察記録です、もうすぐ平成も終わりますがこの時代の横浜の森をいくらか記録できたように思います。(主として2002年頃迄の記録)
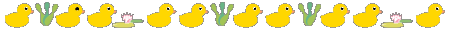
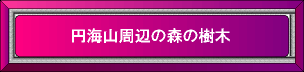
文中で触れた樹木写真のページへ