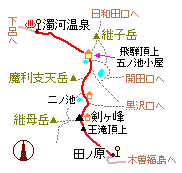|
No.111-1木曽の 御嶽山3067m その1 平成12年(2000年)9月15日〜17日 |
||
第1日=JR高山本線下呂駅-《バス》-濁河温泉 第2日=濁河温泉〜湯の花峠〜のぞき岩〜八合目(お助けの水)〜飛騨頂上・五の池小屋 第3日=五の池小屋〜賽ノ河原〜二ノ池〜剣ヶ峰〜八丁ダルミ〜王滝頂上〜八合目(石室小屋)〜田の原-《バス》-JR中央本線木曽福島駅 |
 飛騨道・八合目  飛騨頂上(翌朝撮影) |
30分ほど登って「のぞき岩」でまた中休止。眼前に望めるはずの摩利支天山は霧の中だ。
標高2450m、八合目の「お助け水」でも中休止。ここではナナカマドが赤い実をつけていた。木々の背丈が段々と低くなってくる。
* 御嶽は我が国の植物帯の垂直分布の標準緯度に位置しているとのことで、低山帯(標高500m〜1500m)、亜高山帯(標高1500m〜2500m)、高山帯(標高2500m以上)と、マニュアル通りに植生が変化するのが分かりやすくて面白い。亜高山帯のおもな樹種はコメツガ、(オオ)シラビソ、ナナカマド、ダケカンバなどで、高山帯になるとそれらの原生林を抜け、灌木化しているダケカンバ、ミヤマハンノキ、ウラジロナナカマド、そしてハイマツなどの明るい山稜になる。火山性の岩石でガレている標高3000m前後の山頂部になると、流石に植生は限られてきて、コメススキやオンタデなどが疎に生える荒涼とした風景に移りゆく。
ゴロ石の目立つ稜線近くまで来て、ついに本降り。嵐の状態になってきた。雨と風と霧にもみくちゃにされながら、飛騨頂上・五の池小屋へ着いたのは午前11時丁度。外気温摂氏約8度。それほど寒くはなかったが、もはや予定のコース(継子岳や摩利支天山への往復)を続ける気力はなかった。小屋の中で、濡れた衣類を乾かしながら、ただひたすら時間の経過を見守ることになった。
 * 五の池小屋: 昨年建て替えたばかりで、今夏から営業を開始したという五の池小屋は、まだ白木の匂いのする快適な空間を私達に提供してくれた。この日の宿泊客は男女4人のパーティーと私達だけ。畳も寝具も真新しくて、食事もタップリで美味しい。味噌汁など、私は4杯もお代わりをしてしまった。小屋番は市川典司さんとおっしゃる30歳の、無口だが好感の持てる青年と、そのスタッフだった。
* 五の池小屋: 昨年建て替えたばかりで、今夏から営業を開始したという五の池小屋は、まだ白木の匂いのする快適な空間を私達に提供してくれた。この日の宿泊客は男女4人のパーティーと私達だけ。畳も寝具も真新しくて、食事もタップリで美味しい。味噌汁など、私は4杯もお代わりをしてしまった。小屋番は市川典司さんとおっしゃる30歳の、無口だが好感の持てる青年と、そのスタッフだった。木曽側の山小屋が、すべて8月いっぱいでクローズしてしまっていたので、やむを得ず、飛騨側の唯一の山小屋である五の池小屋(10月15日まで営業)を利用するしかなかった、というのが今回のコース取りの理由だが、結果オーライだったようだ。
第3日目(9/17): 風は幾分収まったようだが、雨なお強く、霧も深い。心配していたカミナリは鳴っていないようだ。朝食後、意を決して小屋を出る。午前6時35分だった。小屋下の間近に碧い水を湛えた五ノ池が、時折薄ぼんやりと見えている。
 剣ヶ峰山頂  王滝道を下る |
どこをどう歩いたのかよく分からない。火山性の岩礫とハイマツのなだらかな山稜を登ったり下ったり、賽ノ河原と呼ばれる広々としている(と思われる)処を通過したり、とにかく標柱やペンキの道しるべだけを頼りに、脱コースに注意しながら、休み休み黙々と歩いた。幸い、寒さは今日もそれほどではない。
水の流れる音が聞こえてきたと思ったら、ひょっこりとコバルトブルーの二ノ池畔へ出た。標高2905mに位置するわが国最高位の湖沼だ。人の気配のない二ノ池小屋の脇を通り、池を左から巻いて暫く登ると剣ヶ峰の山頂直下で、ここには山小屋の剣ヶ峰旭館が建っている。戸が開いていたので、土間へ入って一休み。この小屋は、奥の方に管理人らしい人影はあったが、矢張りしーんとしていた。
立派な石の階段を登り詰め、御嶽の最高峰・剣ヶ峰の頂上へ着いたのは午前8時25分。ここもホワイトアウトだった。
雨と霧の山頂を早々に辞して、秩父大滝村出身の普寛(ふかん)行者によって1792年に開かれたとされる王滝口の登山道をひたすら下る。森林限界付近の背丈の低いダケカンバ林は素敵だったが、道端の草花は季節が殆ど終わっていて、ほんの少しのアザミが目立つ程度だ。
この下山道では数名の白装束姿とすれ違った。祠ごとに手を合わせる信者の姿を目の当たりにして、やっぱり御嶽は修験道の山・霊山なんだと改めて感心した。ここでは白装束の講登山者が主で、私達一般ハイカーは従であることに留意しなければならない。…悪天候にもかかわらず歩いてしまった私達夫婦も、もしかしたら百名山教に取り憑かれてしまった「信者」なのかもしれないが…。
標高約2200メートルの田の原へ下り着いたのは午前10時55分で、10時40分発の木曽福島行きのバスには間に合わなかった。雨はまだ降っている。
田の原観光センターの食堂などで時間を過ごし、午後1時発のおんたけ交通バスに乗車。乗客は私達を含め3人だけ。睡眠は充分のはずだったのだが、何時の間にか眠っていたようだ。ふと目が覚めたら木曽福島の駅前だった。時計を見たら午後2時25分。雨は上がっていた。
均衡のとれた大きくて美しい山、御嶽。そして、銅像と祠だらけの、修行の霊山でもある御嶽…。私達にとっては遠い山だった。何時か…、私達がもっと歳をとって自由になって、そして充分に健康であったときに、天気の良い日を狙って必ず登ってみるべき山だと思う。しかし、それは一体いつの日になることやら…。歳をとるほどに自由になると思ってきたのだが、実際はその反対で、“しがらみ”が益々増えてきそうな予感がしている…。

賽ノ河原から剣ヶ峰を望む(後日撮影)
このページのトップへ↑
ホームへ