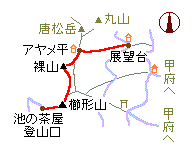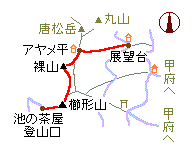 |

原生林を進む

ギンリョウソウ

櫛形山(奥仙重)山頂

サルオガセ

裸山の草原にて

裸山山頂
|
なだらかな頂稜に深林の幽趣を見た
JR中央本線甲府駅-《タクシー1時間20分》-池の茶屋登山口〜櫛形山(奥仙重2052m)〜バラボタン平〜裸山2003m〜アヤメ平〜櫛形山林道・展望台-《タクシー1時間》-甲府草津温泉(入浴)-《タクシー10分》-甲府駅 【歩行時間: 2時間50分】
→ 地理院地図(電子国土Web)の該当ページへ
甲府盆地のどこからでも見える櫛形山(くしがたやま)。長くてなだらかな頂稜(北から南へ丸山1625m、唐松岳1856m、裸山2003m、奥仙重2052m)が和櫛の背の形に見えるのがその山名の由来であるらしい。東洋一とのうたい文句の山頂部周辺のアヤメの群生地はあまりにも有名だ。故田中澄江さんはその晩年の著書「新・花の百名山」の櫛形山の項の冒頭で・・・十年前に「花の百名山」を出版し、その年の七月に櫛形山に登り、アヤメ平を一面の紫に染めるアヤメの大群落を見て、「あっ、しまった」と思った。櫛形山こそ、その中にあげたい山であった。・・・と述べられている。
というわけで、この櫛形山は、北岳や仙丈岳などの南アルプス北部への山行の行き帰りなどに、車窓から仰ぎ見ていつも気になっていた山だった。今回、日帰りではあるけれど、アヤメの咲き始めた櫛形山へ登ることができて溜飲の下がる思いがした。アヤメの群落は勿論ステキで美しかったけれど、それ以上に私達が驚いて感動したのは、その山稜部に広がる原生林の神秘的な趣きだった…。
今回は私達夫婦のほかに友人2名、総勢4名のパーティーだ。甲府駅で「スーパーあずさ3号」を降りて、駅前からタクシーに乗り甲府盆地を西へ進む。梅雨の中休みだろうか、晴れ間も出ていて、進行方向には南アルプスの山々がよく見えているし、右手には八ヶ岳、振り返ると奥秩父連山も見えている。ところが、残念なことに肝心の櫛形山の山頂部には横長の厚い雲がかかってしまっていて、あの独特な和櫛の背の大きな山容が望めない。少し不安な気持になったけれど、今日の甲府市の降水確率は0パーセント。地元タクシーのベテラン老運転手を交えての車中での会話が弾む。
池の茶屋林道終点の登山口へ着いたのは午前11時10分頃だった。先週からアヤメが咲き始めているとのことで、駐車場や終点近くの路上はマイカーやハイキングツァーの小型バスなどで大混雑。トイレには女性たちの長い行列ができていた。ここは既に標高1800m以上ある。数ある櫛形山登山コースの中で最も山頂に近い登山口だ。薄霧に日差しが遮られ、じっとしていると半袖のTシャツのみでは少し寒い。タクシー料金11,700円を支払ってゆっくりと歩き出す。
緑鮮やかな原生林のゆるやかな道を登る。カラマツが徐々に少なくなり、亜高山性のダケカンバ、コメツガ、シラビソが目立ってくる。 太い根幹の形の良い老木や苔生した倒木の様子など、霧のベールに包まれて幻想的であり神秘的でさえある。ここは前衛とはいえ、間違いなく南アルプスだった。人影は思ったほど多くなく、道端にはミヤマキンポウゲ、ヤマオダマキ、シロバナノヘビイチゴ、グンナイフウロなどが咲いている。真白な腐生植物のギンリョウソウ(銀竜草)も咲いている。歩きながら、何だかうれしくなってきた。
「いい景色だね」 と何回も私たちは同じ言葉を繰り返す。
汗の出始めた頃、三等三角点を過ぎ、少し登り返して深林に囲まれた櫛形山の最高峰(奥仙重2052m)へ着いた。歩き始めてから僅か50分だった。標柱の立つ山頂広場から少し離れたオオカメノキの木の下で、4人が車座になって憩う。気温摂氏約13度、微風、と絶好のコンディション。1時間近くの大休止になってしまった。
おもむろに腰を上げ、原生林の稜線を北へ進む。木々の葉や、所々に現れる草原や、林床のシダ類などの「緑のシャワー」を、上から下からたっぷりと浴びる。なんか、私達の身体も緑色に同化してしまいそう…。
林が幾分疎になってくると、あちこちの枝々に薄緑色のとろろ昆布のようなものが張り付いて垂れ下がっている。地衣類のサルオガセだ。本当かどうかは分からないけれど、このサルオガセは、深山の仙人じゃないけれど、霞(かすみ)を食って生きているそうだ。田中澄江さんは櫛形山のサルオガセについて「老いたる山姥のすがれおどろに乱れた髪の毛のようにも見えて無気味であり…」と記述されている。僭越ながら、当を得て面白い表現だと思う。
奥仙重からゆっくり歩いて約45分、裸山の山頂一帯には草原が広がり、お目当てのアヤメが群落して咲いていた。周辺をぐるっと一回りして、アヤメを心行くまで観察した。思っていたより可愛らしいアヤメたちで、威張っていない瀟洒なその姿に、矢張り感動してしまった。西面に見える筈の南アルプスの主峰たちは厚い雲の中だったけれど、南東方向の御坂の山々や富士山はよく見えている。
裸山の鞍部に戻り、アヤメの草原に名残りを惜しみながらアヤメ平へ向かう。
事前の情報で分かってはいたのだが、アヤメ平のアヤメはまだ咲き始めたばかりで、花の数も裸山のそれよりはずっと少なかった。小休止の後、下山は北尾根コースを辿る。下るにしたがってダケカンバやコメツガが少なくなり、ミズナラやイヌブナやカエデ類などの落葉広葉樹の雑木林になってくる。午後4時丁度、アヤメ平から約1時間、東面の開けているアスファルトの櫛形林道へひょいと出た。予約したタクシーの、あのベテラン老運転手が待っていた。ここは展望台(みはらし平)というだけあって、なかなかの景色だ。甲府盆地の奥には大菩薩嶺、左方は奥秩父の山々、右方には帽子(笠雲)を被った富士山も見えている。老運転手が、私たちに気を遣って、それらの景色の説明を長々としてくれた。
今年の4月1日、町村合併して発足した南アルプス市(日本で初めてのカタカナの市)を東へ横切り、甲府の街へ向かう。沿道の農園には出荷間近のモモがたわわに実っていた。老運転手の勧めに従って、甲府市街にある銭湯「草津温泉」で汗を流してから帰路につく。さっぱりした身体とほどよい疲れで、満ち足りた気持だった。梅雨時の日帰りとしては、これ以上は望めないほど素晴らしいハイキングだったね、と、皆で云い合った。
 甲府「草津温泉」: 甲府市街にある入浴料350円の温泉銭湯。櫛形山下山地の櫛形林道展望台からのタクシー代は8,340円、甲府駅までは880円だった。営業時間は6時から21時まで。建物の外観はちょいとダサいが、驚いたことに源泉掛け流しの超本物。湯量と泉質は申し分ない。帰宅してから調べてみて分かったことなのだが、ここは温泉好きの「通」などには有名な処であるらしい。利用客は地元の人がほとんどだが、山帰りのハイカーたちもけっこう訪れているようだ。泉質は含芒硝重曹食塩泉でとてもやわらかい感じがした。源泉48℃。ほとんど無色透明無味無臭(薄い褐色?)。メインの石呂風と源泉の湯と水風呂の3つの浴槽があるが、源泉の湯は私には熱すぎた。戦前からの営業とのこと。感じの良い番台のおばちゃん、など、所謂なつかしの町の「銭湯」だ。タオルと石鹸とシャンプーは必携。 甲府「草津温泉」: 甲府市街にある入浴料350円の温泉銭湯。櫛形山下山地の櫛形林道展望台からのタクシー代は8,340円、甲府駅までは880円だった。営業時間は6時から21時まで。建物の外観はちょいとダサいが、驚いたことに源泉掛け流しの超本物。湯量と泉質は申し分ない。帰宅してから調べてみて分かったことなのだが、ここは温泉好きの「通」などには有名な処であるらしい。利用客は地元の人がほとんどだが、山帰りのハイカーたちもけっこう訪れているようだ。泉質は含芒硝重曹食塩泉でとてもやわらかい感じがした。源泉48℃。ほとんど無色透明無味無臭(薄い褐色?)。メインの石呂風と源泉の湯と水風呂の3つの浴槽があるが、源泉の湯は私には熱すぎた。戦前からの営業とのこと。感じの良い番台のおばちゃん、など、所謂なつかしの町の「銭湯」だ。タオルと石鹸とシャンプーは必携。


頂稜に広がる原生林
|

裸山のアヤメ
|

*** コラム ***
櫛形山からアヤメが消えた?!
この数年後の平成18年(2006年)ころから櫛形山のアヤメが急速に減っているようです。平成21年(2009年)7月6日の、本ホームページのBBS(掲示板)に、常連の篠ちゃんから次の投稿がありました。
“・・・(アヤメを)期待して出掛けたのですが残念な事に絶滅してしまって株さえ見当たりませんでした。宿根が腐ってしまい絶えてしまったそうです。キバナノアツモリソウも絶滅してありませんでした。・・・”
これを読んで私達夫婦は大変なショックを受けました。あんなに大群落していたのに…、まったく信じられません。
シカやイノシシなどの食害、気象条件、土壌の変化など、その原因には諸説あるようです。これが自然の成り行きなのだとしたら、それは仕方がないことなのかもしれません。自然の変化って、ときには残酷なものですね…。[後日追記]
* 南アルプス市は櫛形山のアヤメ群落の保全に取り組み、防護ネットを設置するなどしているようです。かつては凡そ3000万本が自生していたとされるアヤメを復活させるのは、並大抵のことではないと思います。…アヤメ(アイリス)の花言葉…「hope(希望)」に添えて。[H21年7月]
|
このページのトップへ↑
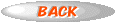 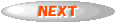

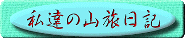
ホームへ
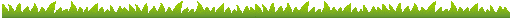
|