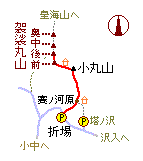

後袈裟丸
|

折場登山口

袈裟丸山を望む

賽ノ河原を通過

トウゴクミツバツツジ

避難小屋を通過

八反張を通過!
|
展望とツツジのミステリアスな名山
《マイカー利用》 折場登山口〜つつじ平〜賽の河原〜小丸山(小袈裟)1676m〜避難小屋〜前袈裟丸山1878m〜八反張〜後袈裟丸山1910m 《往復》 【歩行時間: 7時間】
→ 地理院地図の該当ページへ
日光白根山2578m〜皇海山(すかいさん・2144m)と連なる群馬と栃木の県境尾根の辺りを足尾山塊と呼んでいるが、その南端にどっかと聳えるのが袈裟丸山だ。その大雑把な位置関係は、赤城山の後ろ(北東側)の山、と云ったほうがわかりやすいかもしれない。
袈裟丸山というのは、六林班峠から南へ向かって連なるいくつかのピーク[男山1857m、法師岳1950m、奥袈裟丸(彦岩岳)1961m、中袈裟丸(奥袈裟丸)1903m、後袈裟丸1910m、前袈裟丸1878m]の総称であるらしく、袈裟丸連峰と呼んでも差し支えないようだ。登山地図(昭文社)では一等三角点の置かれた前袈裟丸と中央に聳える後袈裟丸(あとけさまる)をそれぞれ単独で袈裟丸山と表記してあったが、各ピークの呼称については若干異同があるようで、この山も少々ややこしい。
この山域はアカヤシオなどのツツジ類の名所でもあるらしい。その花の旬と思えるこの時季に、未明の東京から、私達夫婦は意気揚々とマイカーで乗りつけた。
渡良瀬川に沿って国道122号線を遡上して、わたらせ渓谷鉄道の沢入(そうり)駅の少し手前を左折して林道へ入る。塔ノ沢登山口へ続く道を右へ分けて間もなく、沿道の未だ薄暗い森の中に5〜6匹のシカの群れを発見して眠気が吹っ飛んだ。車を止めてシカとにらめっこ。シカたちは痩せていておどおどしていて、間もなく山の中へ逃げていった。この山域では昨年からニホンジカを除いて狩猟鳥獣捕獲禁止になっていると聞く。つまり、植生に食害をもたらすシカは狩猟の対象になっているのだ。助手席でずっとウトウトしていた佐知子も既に目を覚ましている。
「あんなにビクビクして、人間がよっぽど怖いのね」
「この山にはシカがたくさんいるから、シカが食べないツツジ類が繁殖しているのかなぁ」
「シカのおかげでツツジ見物ができる、ということかしら…」
実際のところ、肉食獣のニホンオオカミが絶滅してしまったので、(ふえすぎたシカなどの)頭数の調整は人間がやるしかないのかもしれない。独善的だが、アンブレラ種(森の生態系の頂点)はタカでもなければクマでもなく、矢張り人間(ヒトではない!)だと思う。なんと云ったって地球上では人間が一番えらいんだから…。あぁそれにしても、その(個体数)調整役の「猟師」は、ハイカーの若者たちと同じように、今の日本の山では絶滅危惧種になっている…。
* この数年後、山に若者が戻ってきました。山の若者の絶滅は、寸前のところで回避されたようです。(後日追記)
なんて愚にもつかないことを考えたりしながら運転していたら、折場登山口(標高約1180m)の駐車スペースに着いた。ここには東屋やトイレなどもあり、先着の車が4〜5台ほどすでに駐車していた。支度をして歩き始めたのは午前5時45分頃、お天気は上々で気分爽快だ。
ミズナラ、ヤマモミジ、リョウブ、コシアブラ、シラカバ、ダケカンバ、ブナ、カラマツ…、などの明るい樹林を登る。林床のササはミヤコザサだ。咲き始めたヤマツツジが新緑の森に真紅のアクセントをつけている。ヒガラが群れて飛び交い、ウグイスが盛んに囀っている。
歩き始めて40分足らずで北西側が大きく開けた稜線(弓ノ手尾根)へ出た。斜面は一面のササ原で、赤城山や目差す袈裟丸山方面の展望がすこぶる良い。眼下の深い谷間では、ナメ滝が一条の白線になって沢音を響かせながら流れているのがよく見える。思わず道端にどっかと腰を下ろして、コンビニのおにぎりで朝食だ。
勾配の緩やかになった清々しい尾根道を進むとツツジ名所の「つつじ平」や「賽ノ河原」を通過する。トウゴクミツバツツジが多少は咲いているのだが、お目当てのアカヤシオは極めて少ないようだ。所々にその花びらが落ちているが、花期を過ぎてしまったのかもしれない。追い越していった地元のハイカーが言っていたが、今年のアカヤシオの花はやや不作だったとのことだ。
私はどっちでも同じようなものだと思っているのだが、佐知子に云わせるとミツバツツジよりもアカヤシオのほうがずっと気品があって優雅な花色であるとのことだ。シロヤシオは咲き始めで、レンゲツツジはまだ硬い蕾だ。その盛期には山腹が真っ赤に染まるというが、どうやらツツジたちの花期のハザマに私達は来てしまったようだ。これはちょっと残念だった。
若葉の緑が鮮やかなカラマツ林を抜ける。徐々にコメツガが目立ち始め、亜高山帯の雰囲気になってくる。樹林の隙間からも充分な山岳展望を得ることができるが、小丸山の山頂からは尚一層のすばらしい景色が広がった。特に北側の、袈裟丸連峰の右奥にそびえる皇海山や庚申山、更にその奥の日光連山などが私達にとっては珍しいアングルで、山座同定も楽しかった。
小丸山から少し下った平らで広い鞍部には簡易トイレやベンチがあり、鉄製の小さな避難小屋が建っている。カマボコ型で黄色いペンキが塗ってあるので、一見するとテントのようだ。辺りはコメツガも交じるが、殆どダケカンバの美しい純林だ。それがまだ芽吹く直前の冬枯れの状態で、太陽の光が林内に燦々と差し込んでいる。何時までも歩いていたい、素晴らしいトレイルだ。
急な坂を登り切ると前袈裟丸の山頂で、ここには一等三角点の標石がでんと置かれていて、周囲では数組のハイカーたちが休憩していた。南面と東面が開けていて赤城山や安蘇山塊の山々などがよく見えているが、北面の展望は樹林の隙間から垣間見る程度だ。ここで菓子パンを齧ったりサーモスの熱いコーヒーを飲んだりして中休止してから、意を決して更に北へ向かう。少し進むと大きく前方の視界が広がって、雪を貼り付けた谷川連峰や武尊山や至仏山、それに日光白根山や男体山などもよく見えている。
前袈裟丸から先のこの道は、じつは、一応「通行禁止」とはなっているのだが、ハイカーたちの殆どは前進して後袈裟丸の山頂を目差す。風化の進む痩せ尾根の鞍部(八反張)を通過するのが危険、という役所の判断だと推察するのだが、注意して歩けば問題ない、と私達も実感した。実際、アズマシャクナゲの咲き始めているこの区間の尾根歩きは楽しいものであった。
後袈裟丸山の山頂は展望もあり憩える空間だったが、郡界尾根コースから登ってきたと思われる大パーティーが合流して、前袈裟丸にも増して大賑わいだった。足元は、ここもミヤコザサが繁茂している。菓子パンの残りを口に咥えながら狭い山頂をウロウロする。辺りの樹種はコメツガ、ダケカンバ、アズマシャクナゲ、などで、なんとヤマザクラが未だ咲いていた。端っこに群馬県勢多郡東村(2006年に合併して現在はみどり市)の立派な案内板があって、この山が“弘法大師や信仰にまつわる伝説が多いミステリアスな山”であることが書かれてあった。
たっぷりと山頂の空気を楽しんでから、ゆっくりと踵を返して来た道を下山する。復路でもツアーの団体など、大勢の中高年ハイカーとすれ違った。折場登山口の駐車場に戻りついたのは午後3時頃だった。朝は4〜5台だったのが、ざっと勘定してもほぼ満杯の15台以上は駐車していた。
平日だというのに、この山のこの賑わいは、それこそミステリアスだった。しかし、この山がツツジと展望に恵まれた名山であることを納得してみると、さもありなんと思う。人気の山にはそれなりの理由が必ずあるもので、蛇の道は蛇、である。
  水沼駅・温泉センター: 袈裟丸山登山の帰路に立ち寄ったのが「わたらせ渓谷鉄道」の水沼駅(群馬県桐生市)に併設されている日帰り温泉施設。つい先月(2009年4月26日)、民間へ経営を委託してリニューアルオープンしたという。駅のホームに沿った細長い待合室がそのまま温泉施設、といった感じの、なんとも珍しいロケーションで、そういう意味では情緒たっぷりだ。チラシによると、泉質は含二酸化炭素-ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉(弱酸性低張性冷鉱泉)で、源泉(猿川温泉)は赤城山東麓にあるとのことだ。加熱・循環で無色・透明・無味・無臭。内湯は石タイル貼り、外湯は岩風呂風。今回の私達は利用しなかったが、隣接する食事処もある。入浴料500円。(この後、600円に値上げ) 営業時間は10:00〜22:00。(この後、10:30〜19:00に変更) 水沼駅・温泉センター: 袈裟丸山登山の帰路に立ち寄ったのが「わたらせ渓谷鉄道」の水沼駅(群馬県桐生市)に併設されている日帰り温泉施設。つい先月(2009年4月26日)、民間へ経営を委託してリニューアルオープンしたという。駅のホームに沿った細長い待合室がそのまま温泉施設、といった感じの、なんとも珍しいロケーションで、そういう意味では情緒たっぷりだ。チラシによると、泉質は含二酸化炭素-ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉(弱酸性低張性冷鉱泉)で、源泉(猿川温泉)は赤城山東麓にあるとのことだ。加熱・循環で無色・透明・無味・無臭。内湯は石タイル貼り、外湯は岩風呂風。今回の私達は利用しなかったが、隣接する食事処もある。入浴料500円。(この後、600円に値上げ) 営業時間は10:00〜22:00。(この後、10:30〜19:00に変更)
山旅の汗を流すにはもってこいの大切にしたい施設だが、「民営」になったばかりの割には未だ「公営的」な無気力感が漂っていた。
★ 水沼駅温泉センターは、この後「駅の天然温泉・水沼の湯」として2025年4月にルニューアルオープンしたようです。ネット情報によりますと、入浴料は1,350円(休日は1,550円)、営業時間は9:00〜21:00、とのことです。う〜ん、ご時勢かなぁ…、大分高くなってしまったようです。[R8年1月:追記]

| 3つの山頂を征服! |

小丸山の山頂
|

前袈裟丸の山頂
|

後袈裟丸の山頂
|


弓ノ手尾根から赤城山方面を望む
|

賽ノ河原付近から袈裟丸連峰を望む
|
このページのトップへ↑
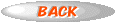 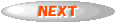

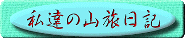
ホームへ
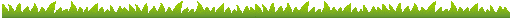
|












