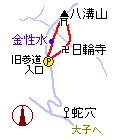|
No.135 八溝山(やみぞさん・1022m) 平成14年(2002年)2月10日 |
|||||
《マイカー利用》 …大子温泉(泊)-《車》-旧参道入口〜日輪寺〜八溝山(八溝嶺神社)〜高梨家屋敷跡(鉄水)〜金性水〜旧参道入口 【歩行時間:
1時間50分】 |
 日輪寺  山頂展望台  金性水 |
駐車スペースもトイレも案内板もある旧参道入口から手袋をつけて歩き出したのは午前9時35分。地図で調べると、ここは既に標高約760メートル。少し寒い。まず少し下ってから登りが始まる。暫らくは美しい杉林が続く。枯れたワサビ田を過ぎ、暫らく歩いて日輪寺(坂東札所第二十一番・天台宗)で両手を合わせる。腐沢(くされざわ)林道を横切り、尚も整備された山道を登る。
辺りは何時の間にか落葉広葉樹が主体の自然林(奥久慈県立自然公園・八溝山冷温帯性植物群落保護林)へ移り変わっている。イヌブナ、クマシデ、アカシデ、ヤマザクラ、オオモミジ、ヤマモミジ、リョウブ、コシアブラ、ブナ、ミズナラ…と、針葉樹のモミやツガ等も少し交ざる。ツガについては当地がその分布の北限であるらしい。林床の笹はミヤコザサだろうか、冬に現れる葉縁の白いくまどりが美しい。日陰の部分などに残雪が目立ち始めるが歩行に支障はない。
ひょっこりと再びアスファルトの車道へ出ると、その前が日本武尊や源頼朝が祈願したといわれる八溝嶺(やみぞみね*)神社だった。八溝山の一等三角点はその裏奥の狭いスペースにひっそりとあった。休み休みゆっくりと歩いて山頂着は午前10時50分。ここは茨城、栃木、福島の県境。そして八溝山は茨城県の最高峰。微風、曇天、気温は摂氏マイナス約8度、人影はない。
山頂からの展望は周囲の樹林などのため限られているが、その代わりコンクリート造りの立派な(お城みたいな)展望台がある。利用料一人100円を門番のオジサンに支払って、さっそく展望台へ上ってみた。流石に有料だけのことはある。曇ってはいたが四方の山々などがよく見渡せた。遠くには那須や日光の連山も見えている。…天守閣から天下を睥睨したような快感を味わうことができたが、風が強く、何といっても寒すぎる。早々に静かな山頂を辞して下山の途についた。それにしても、大子町町営のこのお城の展望台、確かにスゴイけれど、ちょっとやりすぎでは…。
復路はブナ、ミズナラ、イタヤカエデ、ノリウツギ、ホオノキ、シデ類、などが疎らに入り交じる冬枯れの明るい自然林(雑木林)を下る。茨城県内では珍しい樹木として、山頂付近のオオイタヤメイゲツ、オヒョウ、ダケカンバ、オノオレカンバなども見ることができた。中部地方では標高1500m以上の亜高山帯に自生するダケカンバがここでは標高900m辺りから観察できるのが面白い。北方系と南方系の樹種が入り乱れるこの森は、学術上からも貴重な存在であるらしい。
途中、鉄水のベンチで大子町のコンビニで買い求めた菓子パンなどをかじったり、金性水(きんしょうすい)の美味しい水で喉を潤したりして、旧参道入口へ戻ったのはお昼の12時40分頃だった。尚、大子町の説明板によると、鉄水や金性水などの涌き水(八溝川湧水群)は日本名水百選に選ばれていて、茨城自然百選の一つでもあるとのことだ。沢には日本特有のムカシトンボの幼虫が多く生息しているらしい。
八溝山は大きな山塊で、環境庁の「ふるさといきものの里」にも認定されている自然の豊かな処だけれど、山頂まで車道が通じ、車で登れる山、と云うのが少しオモシロクない。まあ、山歩きに関しては贅沢を言えばキリはないのだけれど…。

* 八溝山の山頂展望台は、この後(H21年4月現在)、無料になったようです。[後日追記]
 山頂近くの雑木林 |
 八溝嶺神社(展望台より) |
|
*** コラム ***
Asamoriさんが独自に調べたところ、『茨城県大百科事典(茨城新聞社)』では「やみぞみねのじんじゃ」となっているそうで、地元の久慈郡大子町役場や茨城県神社庁からの回答によると「やみぞみねじんじゃ」と発音する、とのことでした。 私は慌てて訂正して本ページを更新しましたが、このページをアップしてから既に6年以上が経っています。試しにGoogleで検索してみましたら「八溝嶺神社 やみぞみね」では57件、「八溝嶺神社 やみぞね」では350件がヒットしました。つまり「やみぞね」が主流になってしまっていたのです。そしてなんと、その検索結果のトップは本ページでした。6年間も間違った情報を流し続けてしまった罪は大きいと感じました。本ページを参考にして記述されたサイトもたくさんあるはずです。 HPを運営することの社会的責任は、矢張り少なくはないと思います。お詫びして訂正いたします。 Asamoriさん、貴重なご指摘、本当にありがとうございました。[H20/04/17 Tamu] * その後(本コラム欄をアップしてから1年9ヶ月後)、再びGoogleで検索してみましたら、「八溝嶺神社 やみぞみね」では231件で、「八溝嶺神社 やみぞね」では567件がヒットしました。年月の流れとともに総体的に件数が増えたのは何となく理解できます。嬉しかったのは、その比率に“改善”の痕跡があったということです。本コラム欄が多少は影響したものと、我田引水です。[H22/01/26現在] * さらにその後、Googleで検索してみましたら「八溝嶺神社 やみぞみね」では655件で、「八溝嶺神社 やみぞね」では532件がヒットしました。ついに逆転したようです。ひとまずホッとしました。[H23/07/02現在] * さらにまたその後、同5870件と1790件という結果でした。もう完全に逆転しています。それにしても、ネズミ算的な凄まじい増加件数ですね。今度はそれに驚きました。[H26/12/16現在] * この後、Googieの検索手法が変化したらしく、どちらも同じくらいのヒット数で、その内容もまちまちでした。かなり曖昧でメジャー本位の(メジャーに牛耳られた…商業ベースの)検索結果になりつつあるのは、矢張りなぁ…とは思いつつも、ちょっと悲しくて残念な気分です。[後日追記] |
このページのトップへ↑
ホームへ