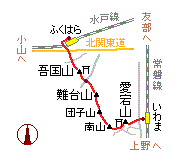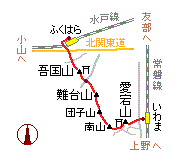 |

愛宕山へ向かう

愛宕神社に参拝

南山展望台

難台山の山頂

吾国山の山頂

吾国山のブナ林

吾国山を振り返る

麓の水田地帯
|
名残り尽きない思いを大切に…
JR常磐線岩間駅〜愛宕山293m(愛宕神社)〜乗越峠〜すすきヶ原〜南山382m〜団子石峠〜団子石〜団子山432m〜大福山〜鼻の下〜獅子ヶ鼻〜天狗の奥庭〜屏風岩〜難台山553m〜すずらん群生地分岐〜429m峰〜道祖神峠〜吾国山518m〜ブナ・カタクリ保護林〜JR水戸線福原駅 【歩行時間:
6時間】
→ 地理院地図(電子国土Web)の該当ページ(愛宕山)へ
上野発午前7時30分のJR常磐線「特急フレッシュひたち5号」に乗り、石岡で普通列車に乗り換え2つ目の、小さくて静かな岩間駅に降りたのは8時44分だった。ここは茨城県のほぼ中央に位置するのだが、東京圏から意外と近いことにまず驚いた。常磐線を利用したのは11年前の男体山(奥久慈)登山以来のことで、私達夫婦はこの方面の交通にはとんと疎いのだ。
しかしのんびりとはしていられない。今日のトレイル(愛宕山〜難台山〜吾国山)は距離が長く、低山縦走ながら累積標高差は1000m近くあるのだ。何時ものようにのほほんと歩いていると日が暮れてしまう。準備体操もそこそこに、道標に従って急ぎ足で愛宕山の表参道へ入り、アスファルトの坂道をショートカットする土の道を進む。案内図によると、この一帯(愛宕山周辺)が「あたご天狗の森公園」で、お花見の名所であるらしい。その季節には大勢の人でにぎわうというが、今は何処も彼処も未だ閑散としていて、ぽつんぽつんと2株、早咲きの河津桜だけが七分咲きで気を吐いている。梅の花は終わりかけていて、今の季節はウメとソメイヨシノの狭間にあるようだ。
昔日の面影を残す「女人禁制」と彫られた石碑を横目で見て、大きな石鳥居を潜って石段を登る。1/25000の地形図を見ると、愛宕山の四等三角点257.8mは愛宕神社がある山頂293mから200mほど東に外れた処にあるようだ。今回は先を急ぐので三角点の標石探しはやらないで、愛宕神社に丁寧にお参りする。
西へ石階段を下ると愛宕神社の広い(無料)駐車場で、北西の方向に難台山(なんだいさん)がどっしりとした山容で横たわっている。「難台山はでっかいね。吾国山(わがくにさん)はあのもっと先かぁ…。う〜ん、遠いねぇ…」 などと話しながら地形図と見比べていたら、売店関係のオジサン(スカイロッジの管理人さんかも)に 「スパッツはもってきたかね?」 と声をかけられた。 「もってこなかったですけど…」 と返事したら、「数日前に降り積もった雪が、特に北側の斜面に多く残っているので気をつけなさい!」 と注意された。そして 「ここからの縦走だと福原駅までは正味5時間だよ」 と教えてくれた。おまけに当地で発行している分かりやすいハイキングマップ(パンフレット)をいただいた。朴訥だが親切なオジサンだった。しかし、積雪15センチと聞いて佐知子が少しビビっている。私もちょっとため息で、村上春樹流に言うと「やれやれ」だ。この大駐車場の少し先(乗越峠)からが本格的な登山道になる。とにかく先を急ごう。
「見晴しの丘」への道は左に見送って、こじんまりとした「すすきヶ原」を通過して南山の展望台で一休み。腹が減ったのでここで弁当の半分を食べる。ここからの展望は南面が特に素晴らしく、田園風景や街並みの奥には霞ヶ浦の水面がぼんやりと光っている。そして右手の木々の隙間からは迫力の近さで筑波山が見えている。2台の立派な双眼鏡が備えつけられていて食指が動いたのだが、有料だと思って覗いてもみなかった。あとで分かったことだが無料だったらしい。せこい自分たちに腹が立つ。
団子山とか大福山とか、食欲をそそる山名のピークを通過する。道は広いが、けっこうきついアップダウンだ。よっぽどこまめな人が名付けたのではないかと思われるが、「団子石」とか「鼻の下」とか「獅子ヶ鼻」とか「天狗の奥庭」とか「屏風岩」など…、そこそこの巨岩とか展望箇所が次から次へと現れるので飽きない。筑波山の右手には足尾山から加波山へ続く山並みもよく見えている。
ここまででチラッと同定のできた主な木本はコナラ、シデ類、ミズキ、ヤマザクラ、ホオノキ、ウラジロノキ、ウリカエデ、ヤシャブシ、ニガキ、リョウブ、アカマツ、シラカシ、ウラジロガシ、アカガシ、スダジイ、ヒサカキ、ミヤマシキミ(蕾)などで、林床の主は未だ赤い実をつけているアオキだ。つまり明るい天然林が主流で、鬱蒼としたヒノキの植林地帯が案外と少ないのが嬉しい。積雪はそれほどでもなく、まずは一安心だ。
今回コース(東筑波連峰)の最高峰でもある難台山553mの山頂に着いたのは午後1時近くで、小さな石祠がある小広い空間に陣取って、ここで弁当の残りを食べた。「難台山城跡と難台山の戦い」と題した古びた説明板がまず目に付いたが、擦れている小さな字でごちゃごちゃと書いてあり、ほとんど判読不明だ。1380年代(南北朝時代の後半)にこの辺りで戦があったらしい。金属製で六角形の立派な(でも分かりにくい)展望盤もあるが、樹林に囲まれていてそれほど見晴らしはよくない。
食後、難台山山頂周辺の樹木をざっと観察してみた。主だった樹木には名札がぶら下がっているので同定は楽だ。コナラ(ミズナラだったかも)、ヤマザクラ、クマシデ、イヌシデ、リョウブ、ヤマボウシ、エゴノキ、アカメガシワ、ネジキ、ヤマツツジ、ヤマウルシ、…など、それぞれにユニークな冬芽が面白い。林床の主役はミヤコザサだ。少し奥にがっしりとした樹形の常緑広葉樹が2株ほどあったが、よく見てみたら、なんと暖温帯の代表樹のタブノキだった。この地も何百年とほっぽっておくと、カシやシイやこのタブなどの照葉樹が森の覇権を握るに違いない。
この難台山から北へ下る急斜面は特に残雪が多く、トラロープは張ってあるのだがちょっと苦戦した。ゆっくりと慎重に一歩ずつ進み、「すずらん群生地」への道を右に分け、さらにピークを2つほど越えて、アスファルトを横切る道祖神峠でも一休み。そして広い急斜面を懸命に登り返し、吾国山の山頂に辿り着いたのは午後3時頃だった。常日頃の鍛錬不足がたたり、私達の体力と気力はこの辺りでヘロヘロになってきていたが、ここから先にはもうピークはなく、時間的な見通しがついてホッとした瞬間でもあった。
石垣に囲まれた土塁状の吾国山の山頂には、ちいさいけれど立派な田上(たがみ)神社が建ち、その左脇には一等三角点の標石が雪面から頭を出している。特に神社の裏手からは展望がよく、八郷(やさと)盆地が“航空写真のように”見え、その左手には今さっき登ってきた難台山が大きく聳え、右手には相変わらず筑波山や加波山がどっしりと構えている。
ゆっくりと西側へ下山を開始するとすぐ、数株の老ブナが寂しそうに林立する「吾国山のブナ林」を通過する。ブナの後継樹は当然のことながら育ってはおらず、ここのブナも筑波山のブナ同様に他の優先種に淘汰される運命にあるのだろう。規模も小さく、今にも消えそうなブナ林に見えた。案内板などに書かれてある「ブナの原生林」のネーミングは、いくらなんでも大袈裟すぎると思う。何故か近くに(山野には自生するはずのない)大きな老イチョウの木があったが、これも“原生林”にはそぐわない不自然なものに見えた。今やこの地の気候風土に適合しないブナ林を、強引に保護して残すというのは如何なものなのか。「未練を断ち切って、ここのブナに引導を渡してあげたい。それが自然なことだと思う…」 と私が呟いたら 「名残り尽きない思いを大切にするのって、いいことだと思うわ」 と佐知子が小さな声で反論した。“自然保護”って、本当に難しい。
あと一月もするとその花の盛期になるだろう「吾国山のカタクリ群生地」を通り過ぎ、標高差にして約450mを、丁目石に案内されてゆっくりと下る。“春”を探しに出かけたのだけれど、山中で咲いていた花はまだほとんどなくて、“冬”を探しに行ったみたいになってしまった。だからなおさら、田園風景の里道にそっと咲いていたホトケノザやオオイヌノフグリがとても可憐で美しく見えた。
北関東自動車道のガード下をくぐり、JR水戸線の閑静な福原駅に着いたのは午後4時40分頃だった。たっぷりと歩いたせいもあるが、とても充実した気持ちだった。
福原駅のホームで電車を待っていたとき、まだ明るかった空が急に暗くなり、細かい雨が降ってきた。風も出てきて寒くなってきたけれど電車はなかなか来ない。「春の小糠雨かしら…」 と佐知子が耳元で囁いた。
* 笠間アルプス: 今回私達が歩いたのは、愛宕山の南麓から吾国山北麓まで直線距離で10km(歩程:約16km)ほどの小さな山域で、筑波山地の東側にあることから「東筑波連峰」と呼ばれています。2019年4月に出版された「関東百名山(山渓)」の該当項(難台山)を読んで知ったのですが、最近ではこの東筑波連峰を笠間アルプスと呼ぶようになってきたようです。国内の低山アルプスは、益々増加傾向にあるようです。(後日追記)


難台山へ向かう
|

振り返って吾国山を望む
|
このページのトップへ↑
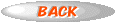 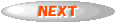

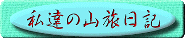
ホームへ
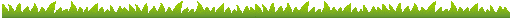
|