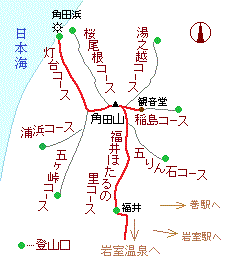|
新潟の名低山を登る-その2 No.492 角田山(かくだやま・482m) 令和7年(2025年)4月14日(月) |
||||
|
花と眺望の人気者 4月14日=弥彦温泉-《タクシー20分》-角田浜・角田岬灯台~(灯台コース)~三望平園地~角田山482m~山頂から観音堂を往復~(ほたるの里コース)・平成福寿大観音殿~福井~岩室温泉 【歩行時間: 4時間30分】 4月15日=岩室温泉9:30-《宿の送迎車で約10分》-岩室駅10:07-《JR越後線》-10:59新潟11:25-《新幹線とき318号》- 13:28東京… → 地理院地図の該当ページ(角田山)へ
* タクシー運転手さんのよもやま話: かつてこの地域に原子力発電所建設の計画があり、その関係で現在の国道460号や国道402号(日本海夕日ライン)の一部が整備されたという。その後、1996年に住民投票をきっかけに原発は建設中止となったが、その道路を利用して、私達はこうして気持ちよく角田山にアプローチしている。 閑散とした、角田浜海水浴場に隣接する角田岬灯台下の大きな駐車場で、タクシー代の6,300円を支払ってから歩き始めたのは8時10分頃だった。北西面は日本海で、ここは海抜0メートルだ。う~ん、角田山の標高482メートルをバカにはできないぞ、とこのとき思った。 階段を登って断崖絶壁に建つ角田岬灯台の真下(灯台コースの登山口)を通って、尾根道へ入る。というか、角田山から北西へ延びる支尾根の末端が海にせり出した処が角田岬灯台、という云い方もできるかもしれない。登山口としては異色で、背後の直下が大海で前方はたおやかな緑の山、という珍しいロケーションだ。 目の高さにキヅタの黒い実がゆれている。足元には雨に濡れたトキワイカリソウが美しくうなだれている。振り返ると絶景で、眼下の角田岬灯台が絵画のモチーフのように屹立している。そしてその向こうの海を隔てた佐渡島が、雪化粧の大佐渡山地の山々(金北山など)を小佐渡山地の上部に従えて、黒々と横たわっている。 四等三角点155.83m(点名:角田岬)のある小さなコブを越えて、さらに岩っぽくて細い尾根(馬の背)を登る。両脇をクサリでガードされているので安心だ。ハマダイコンが咲いている。少し進むとヤマザクラが咲いている。スミレ類(ナガハシスミレ、スミレサイシン、オオタチツボスミレなど)が群生して咲いている。ショウジョウバカマやヒトリシズカも咲いている。そしてずぅ~っと、カタクリの群生が続く。それから、この山の春の名物・雪割草(ここではオオミスミソウ)も…殆ど花期の終わりだったけれど…可憐に咲いている。トキワイカリソウも相変わらず咲いている。流石に花の百名山だ、と思った。 何時の間にか展望は木々に遮られている。ヤブツバキ(花)、シロダモ、ヒメアオキ(赤い実)、アブラチャン…、そして未だ冬枯れのコナラ、ミズナラ、カシワ(ナラガシワ?)…、林床にはチシマザサ、などの(若い)自然林の様相だ。雨は完全に止んだようだけれど、ちょっとガスってきて、三望平園地の付近は幻想的な森の景色だ。ウソ(アトリ科の小鳥)がピー・ピーと口笛を吹いている。近くに寄っても逃げないヤマガラが、ここでも私達の目を楽しませてくれる。 角田浜側からのもう一つの登山道が左手から合流する。それ(桜尾根コース)は私有地を通る非公式の登山道だからか、分岐には指導標が無いのが気になった。…その分岐を過ぎて間もなく、角田山の広くて平らな山頂部に着いた。腕時計を見ると11時10分だった。 角田山の山頂部には、三角屋根の健養亭(避難小屋)や少し離れて横山太平翁像(*)や観音菩薩立像などがある。その山頂広場のベンチに腰掛けて、菓子パンとサーモスの熱いコーヒーで早めの昼食。辺りはブナ、イヌブナ、ミズナラ、コナラ、クリ、ヤマザクラ…、などの(関東山地では標高1000m前後の植生に似た)落葉広葉樹が主役の林で、とてもいい感じだ。足元を見ると、外皮の開いたツチグリ(キノコの仲間)が、私達をじぃ~っと見上げている。 * 横山太平: 明治・大正期の実業家。現新潟市生まれ。当地の発展に大きく貢献したという。[銅像裏の注記を要約] 角田山の山頂からは東へ(稲島(とうじま)コース方面へ)少し下って、向陽観音堂を往復する。この観音堂前の広場からの広大な越後平野の眺めが…噂に違わず…素晴らしかった。少し躊躇したのだが、寄り道をしてよかったと思った。…なお、この観音堂の近くには二等三角点445.02m(点名:角田山)がある筈だが、私達には…うっかりして見落としたものか、気合が入っていなかったせいか…その標石を発見することはできなかった。 角田山の山頂部に戻って、それから南へ向かって「福井ほたるの里コース」を下る。約8コースある角田山の登山コースの中では最も距離の長い…つまりなだらかな…足にやさしいコースだという。カタクリ、スミレ類、トキワイカリソウ、キクザキイチゲなどの花たちもそこそこに咲いていて、森の景色も楽しめた。 ところが、この下山路ではぬかるんだ泥道に辟易することになる。灯台コースの上部にもぬかるんだ箇所があったけれど、この「ほたるの里コース」はそれが延々と続くのだ。スパッツを履いていなかったので、靴もズボンの裾も泥だらけになった。すれ違う地元のハイカーと思しき足元を見ると、なんと、みんな長靴だ。う~ん、それが正解かも、と思った。 下山地が近ずくと、朱色の柱が印象的な立派な建物が見えてくる。平成福寿大観音殿という御堂で、ウィキペディアの該当項などによると、檜の一木造りの巨大な(高さ8メートルの)十一面観音像が安置されているという。昭和の大作曲家・遠藤実さん(1932-2008)が寄贈されたもので、平成2年(1990年)に落慶開眼法要が行われたらしい。この日は扉が閉まっていたのでその観音像を拝顔することはできなかったが、それがチト残念だった。 平成福寿大観音殿からはショートカットの山道もあるけれど、私達は舗装道をぐるっと回って国道460号線に“着地”した。それから山谷古墳(前方後円墳)の近くを通り、のどかな(田植え前の)田園風景を楽しんだりしながら里道を小1時間ほども歩いて、岩室温泉街に着いたのは15時30分頃だった。ほどよい疲れが心と身体に心地よい…、花も展望も素晴らしい角田山に大満足だ。 翌日(4月15日)は、朝風呂に浸かったりしてゆっくりと宿を発ち…宿の送迎車で岩室駅まで送ってもらって…、一路東京への帰路に就いた。 2泊とも由緒ある温泉宿(弥彦温泉と岩室温泉)を利用して、交通には新幹線やタクシーも利用しての、贅沢な山旅だった。しかしその分、心と身体に余裕ができて、安心・安全にじっくりと、新潟の2座の名低山を堪能することができたと思う。つまり今回の私達の山旅は、特に高齢者にとってはとても良い企画だった、と自画自賛する次第です。 佐知子の歌日記より 荒海の日本海見て岬より帰国かなわぬ人らを思う 観音堂に越後平野と雪の連山ただただ眺む 麓より宿まで枯田つづきおり田植えの緑を想いつ歩く  灯台コースから佐渡島を望む ↑黒々とした小佐渡山地の奥に、雪化粧の大佐渡山地(金北山など)が見えている  観音堂前の広場から越後平野を望む
このページのトップへ↑ ホームへ |