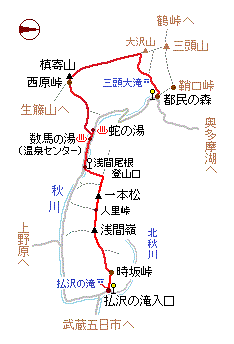|
檜原村の数馬に一泊して No.493 槇寄山と浅間嶺 令和7年(2025年)5月9日(金)~10日(土) |
|||
→ 地理院地図の該当ページ(槇寄山)へ 第2日目(5月10日・浅間嶺)=蛇の湯温泉8:50~浅間尾根登山口~猿石~一本松930m~人里峠~浅間嶺(小岩浅間)903m~浅間嶺・展望台~時坂峠~14:50払沢ノ滝入口15:00-《バス11分》-十里木~「瀬音の湯」で入浴~十里木16:13-《バス11分》-武蔵五日市駅… 【歩行時間: 4時間40分】 → 地理院地図の該当ページ(浅間嶺)へ ●プロローグ 田部重治の名著「山と渓谷」の中の一編「数馬の一夜」を読んでからずぅ~っと、つまり半世紀以上の昔から、東京都西多摩郡檜原村の数馬に一泊して山旅がしてみたかった。…そんなことを急に思い出して、妻の佐知子を誘って出掛けることにした。 ★ 田部重治(たなべ じゅうじ・1884年~1972年): 日本の英文学者で登山家。明治・大正・昭和の初期にかけて、まだ当時は未開であった奥秩父の深山や日本アルプスなどを歩き、それらを世に知らしめたのはこの田部重治氏や小暮理太郎氏などの近代日本登山史上の大先達たちでした。 ★ 山と渓谷: 1919年(大正8年)に刊行された田部重治氏の最初の山岳紀行文集「日本アルプスと秩父巡礼(北星堂)」などを収めたもので、改訂・増補されたその初版は1929年(昭和4年)に第一書房から出版されています。 この「山と渓谷」はその後、さらに再編・増補・推敲されて、ときには改題されて、新潮文庫(1948年初版)や角川文庫(1951年初版)などからも出版されています。私が若い頃に読んだのは(多分)古本屋で買った(または誰かに借りた?)角川文庫版だったと思いますが、そのときの本はもうとっくに行方不明です。後年に読み返したのは1993年8月初版の「新編・山と渓谷(岩波文庫)」で、むさぼるように読み返したのを覚えています。 なお、2011年に山と溪谷社から「山と溪谷・田部重治選集(ヤマケイ文庫)」が出版されていますが、残念なことにそこには「数馬の一夜」は収録されていません。 ★ 数馬の一夜: 田部重治氏は1920年(大正9年)4月に東京の八王子から五日市~払沢の滝~本宿「橋本屋」(泊)~北秋川~御前山~南秋川・数馬「山崎旅館」(泊)~三頭大滝~上野原、と歩いていますが、その山旅の2泊目の数馬の宿で想起したのが珠玉のエッセイ「数馬の一夜」です。…その内容を一言で云うと…“非常に謙虚で内省的で情緒的な”自然と人間(自分)を考察した数ページの超短編、ということになると思います。 それにしても昔の人は、ものすごい距離を一日で歩いてしまうんだなぁ~、と、古い紀行文を読むと何時も感心します。 以上は田部重治の著書「新編・山と渓谷(岩波文庫)」の解説欄(文・近藤信之)、及び「わが山旅五十年(平凡社ライブラリー)」などを参考にして記述しました。 『・・・今日、見てきた自然は何と素朴的なものであったろう。温かき渓谷の春は、静かに喜びの声をあげて、その間に動く人間もただ自然の内に融けている・・・』→田部重治著「数馬の一夜」より ●第1日目(5月9日・槇寄山登山) JR五日市線の終点・武蔵五日市駅前から8時22分発の路線バス(西東京バス)に乗って…多摩川の大きな支流・秋川に沿って…道筋の山麓や山腹に咲くヤマフジの淡い紫色などを愛でながら…1時間強、都民の森に着いたのは(定時の)9時半頃だった。それから懐かしの風景に一喜一憂しながら、よく整備された遊歩道(森林セラピーロード・大滝の路)を歩き、まず三頭大滝を“観光”する。…とにかくこの地は、何処も彼処も新緑だ。 植生の豊かな山域なので、植物観察をしていると10m進むのに1時間くらいはかかってしまいそうなので、見て見ぬふりをして歩みを速める。それでもふと、やっぱりカエデ類が多いなぁ…などと考えて、思わずメモを取ってしまう。クセというのはなかなか抜けないものだ。 →オオモミジ、ウリカエデ、ウリハダカエデ、イタヤカエデ、イロハモミジ、(コ?)ハウチワカエデ、エンコウカエデ、カジカエデ、マルバカエデ(ヒトツバカエデ)、ヤマシバカエデ(チドリノキ)…など、都民の森バス停から三頭大滝までの遊歩道(大滝の路)だけでもこんなに沢山のカエデ類(ムクロジ科カエデ属)が自生している。 三頭大滝から少し進むと道標のある分岐があって、右手は「ブナの路」で左手は「石山・深山の路」となっている。どちらへ進んでも“三頭山へ至る”となっていたので、深く考えずに左へ進んだ。これが後で考えると、当初の予定コースを外れていて、主稜線へ出てからの三頭山往復がきついコースを選んでしまっていたのだ。 主稜線に出た地点のベンチに腰掛けて、おにぎりや茹で卵などを食べながら、緊急夫婦会議だ。 「ここから大沢山~ムシカリ峠を超えて三頭山の山頂までは…往復1時間以上はかかりそうよ」 「う~ん、どうしよう…」 「三頭山には何回も登っているし~」 「うん。三頭山往復はあきらめよう。うん、それがいい」 という訳で、夫婦和気藹々と槇寄山(まきよせやま)へ向かって主稜(東京都と山梨県の境界尾根=笹尾根)を南下する。毎度のことで…、私達の水は常に低い方へ流れる。 ブナ、イヌブナ、ミズナラ、カエデ類、リョウブ…、などの新緑が眩しいほどに美しい。アセビの赤い新葉が花のようだ。ミツバツツジが未だ咲き残っている。木々の隙間から近隣の山々が(辛うじて)見えている。お天気は何とかもちそうだ。 殆ど展望のない槇寄山山頂のベンチでも大休止して、それから徐に下山開始。これも懐かしの西原峠を経由して、標高差で約530mを数馬上の仲ノ平へ向かって急降下。ウツギやシャガの咲く里道へ出てほっとする。 秋川沿いの茅葺屋根の宿・「蛇の湯温泉・たから荘」は、藤の花に包まれてひっそりと佇んでいる。チェックインしたのは15時10分頃だった。
とても感じのよい主人ご夫婦が取り仕切っている。露天は無く(男女別の)石貼りの内湯のみだが、大きな木枠の窓の外は秋川渓谷で、緑がいっぱいの開けた浴室だ。泉質は単純硫黄冷鉱泉とのことだが、硫黄臭は無く、殆ど無色透明無味無臭。加水、加温、循環。夕食は川魚や山菜の料理で、特にこの地(檜原村)の名物のジャガイモが美味しかった。隣りに小さなジャガイモ畑があり、多分そこで収穫したものだと思う。部屋の窓からも緑いっぱいの秋川渓谷が見下ろせて、ロケーションはすこぶる良い。とはいえ、朝食が8時からというのが、山歩きが目的の私達にはチト不満だった。もう少し早くしてもらえないものかと思う。 夕食後は、疲れていたので、早々に床に就いた。何気に、夜半から雨が降り始めたらしい。微かに聞こえる雨音を聞きながら、何時しか私達はぐっすり…。1泊2食付き一人16,150円(税込)だった。 ●第2日目(5月10日・浅間尾根縦走) 蛇の湯温泉「たから荘」の8時からの朝食を食べてからチェックアウトして、檜原街道を東へ向かって歩き始めたのは8時50分頃だった。なだらかに20分ほどもアスファルトを下って「浅間尾根登山口」のバス停を過ぎて、指導標に従って左折して林道入間白岩線を進む。と、やがて山道になり人家も途絶える。昨夜からの雨は止んだようだけれど、空はどんよりとしている。 スギ林~ヒノキ林~天然林を登り、浅間尾根に合流する。石仏(馬頭観音)の目立つ…、きょうも初夏らしい新緑の山道だ。ウグイスが鳴いている。ヤマツツジがきれいに咲いている。タチツボスミレかな、も未だ咲いている。曇天なので林縁なども薄暗いけれど、若葉の緑が妙に明るく光って見えている。これがプルキンエ現象(*)だろうか。とてもきれいだ。 * プルキンエ現象: 薄暗くなってきた山の中を歩いていると、草や木々の緑がやけにくっきりと鮮やかに、ときには光っているように見えることがありますが、これは人間の視細胞の働きによるもので「プルキンエ現象(プルキニェ現象)」によるものであるといいます。…人間の網膜の働きで、明るい場所では赤が鮮やかに遠くまで見えるのに対して、暗い場所では青(~緑)が強調されて見えるようになります。これは19世紀のチェコのヤン・エヴァンゲリスタ・プルキンエという生理学者が発見したことから「プルキンエ現象」と呼ばれています。人間を含めた自然界の現象って、ほんとうに不可解で面白いですね。[Wikipediaなどのネット情報を参考にして記述] なだらかなアップダウンの浅間尾根をひたすら東進する。 岩壁にサルの手形に似た模様があるという…しかしいくらそれを探しても判然としない…例の猿石を過ぎ、三等三角点930.23m(点名:石宮)のある一本松も通り過ぎる。途中チラッと、左手(北側)の樹林の隙間から雲を被った御前山と思しき立派な山容を見たが、この日の展望はそれっきりだった。…ガスがだんだん濃くなってくる。 案外と地味な浅間嶺の山頂(小岩浅間903m)を過ぎ、少し下って富士浅間大社で手を合わせてから、登り返して浅間嶺展望台887mへ到着。こちらの方がベンチもあるし山頂らしい趣きだったので、ホワイトアウトだったけれど、菓子パンなどを齧ったりして大休止する。私達夫婦が山の仲間たちとこの浅間尾根を歩いたのは2002年の5月で、あれからもう23年も経つんだねぇ、などと会話して往時を偲んだ。→No.140「浅間嶺」 やがて舗装道が交ざるようになり、ショートカットの山道を選んで下る。こちらにもシャガがたくさん咲いている。少数派だけれど、ガクウツギやミツバウツギも咲いている。オカタツナミソウもきれいに咲いている。 今は閉鎖されている峠の茶屋を通り過ぎ、時坂峠を経て払沢ノ滝入口バス停へ着いたのは15時の少し前だった。予定ではここから払沢の滝を見物(往復約40分)する筈だったのだけれど、15時00分のバスがちょうど着いたので、それに乗ってしまった。なんとなれば、次のバスは73分後(16:13発)なのだ。払沢ノ滝見物の楽しみは、またまた”次回”に持ち越された。 武蔵五日市駅への帰路、十里木(じゅうりぎ)バス停で途中下車する。そして秋川に架かる情緒たっぷりな石州橋を渡って…徒歩約10分で…「瀬音の湯」に立ち寄って山の汗を流した。…つまり温泉三昧の二日間でもあった。 温泉入浴後の夕食(反省会)は、「瀬音の湯」のレストランにするか帰路の何処か(例えば武蔵五日市駅の周辺とか立川駅の駅ビル内とか)、ちょっと迷っちゃうなぁ~。 ●エピローグ: なんとか降られずに済んだ今回の私達の山旅だったが、ガスが濃くて展望がスポイルされてしまったのはチト残念だった。それでも、新緑の美しさをたっぷりと堪能した二日間で、私達の身体は(きっと)緑に染まって、身体中から光を発していた…ような感覚にずぅ~っと捉われていた。 青年というか少年というか…の頃からの夢が…「数馬の一夜」の夢が…とうとう叶ったのも…私的には…とても嬉しいことだった。 佐知子の歌日記より とりどりの緑あふれる山道に樹木の精住む都民の森よ 道たがえ山頂踏めず下山して数馬への道ひたすら歩く ラクラクと二十年前は登ったが今はハアハアの浅間嶺よ 雲あつく奥多摩の山顔出さず振り返りつつ下るしかなくて * 本項と関連のあるページも参照してみてください。 |