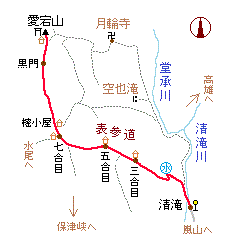|
京都の山旅日記-前編 No.497 京都の 愛宕山924m 令和7年(2025年)11月11日(火) |
|||||||
|
第2日目(11/11)・愛宕山登山=ホテル嵐山~阪急嵐山駅前6:31-《バス17分》-清滝~(表参道)~愛宕山924m(往復)~清滝-《バス》-嵯峨小学校前~サンメンバーズ京都嵯峨 【歩行時間: 5時間】 → 地理院地図の該当ページ(愛宕山)へ 第3日目(11/12)・小倉山登山=嵯峨嵐山駅前~小倉山登山 中学校・高校の修学旅行は何れも京都と奈良だった。大学生の頃は当時流行っていたデュークエイセスの「女ひとり」や渚ゆう子の「京都の恋」と「京都慕情」、そしてチェリッシュの「なのにあなたは京都にいくの」などに憧れて京都を旅したものだ。そして帰りの電車賃も使い果たしてしまって、大原三千院の近くで営業する茶店に住み込みで約1ヶ月間アルバイトをしたり…、と、ほろ苦いけれどちょっぴり甘い京都の思い出が私にはある。 社会人になってからは…、もう40年近くの昔になる昭和の終わりごろ…つまりバブル全盛のころに、勤務先の所謂「厚生旅行」で錦秋の京都・嵯峨嵐山などを観光した思い出もある。祇園では座敷に舞妓さんを呼んで宴会したりして…、バブルっていたから…。近年では…といっても7年前だけれど…武奈ヶ岳登山の折に京都見物をして、外人が多いのにびっくりしたものだ。 自然愛好家の私にとっての京都観光としては、大原の山奥や嵯峨・嵐山の自然美が特に印象が深くて、日々の生活の中でもよく思い出す。桂川に架かる渡月橋辺りの景色などは秀逸で…、それが紅葉の時季だったら最高だな、と常々思っていた。その渡月橋の北西側には百人一首で有名な小倉山(おぐらやま・296m)と、全国にある(火の神を祀った)愛宕神社の総本社を擁する愛宕山(あたごやま・924m)がある。…私達夫婦は、その何れの山にも登ったことがない…。 という訳で、新幹線やホテルの予約など満を持して、紅葉の見ごろを迎え始めた11月10日に、私達は京都へ旅立った。…そうだ京都へ行こう!
まず京都駅のコインロッカーにザックを預けて、すべて徒歩で、駅の北東方向に位置する三十三間堂と清水寺を観光する。何れも…妻の佐知子にとっても私にとっても…ほぼ60年ぶりの観光地だったが、記憶とはずいぶん違っていた。もちろん地形や建物などの位置関係に変化はないけれど、ムードというか感じというか、が違って見えたのだ。修学旅行の学生たちの姿が少ないことや、着物姿(貸衣装かな)の若い観光客が多いこと、そしてなんといっても外国人が多いこと、などがその(違って見えた)理由かもしれない。何れにしても今の京都は人種のるつぼ(サラダボウルかも)的なインプレッションで、皮肉なことにエキゾチックで異国情緒たっぷりだ。 京都駅に戻ってから地下の食堂街で遅めの昼食を摂る。私はにしんそば、佐知子はきつねうどんだ。それからJR嵯峨野線(山陰本線)に乗って、懐かしの太秦(うずまさ)を通過して、嵯峨嵐山駅で降車する。ここも外人だらけだ。 桂川に架かる懐かしの渡月橋を渡って、きょうの宿「ホテル嵐山」にチェックインしたのは午後3時半頃だった。 [この日の歩数計:25704歩] ★ホテル嵐山: 桂川の南岸の中之島(嵐山)公園に隣接した位置に建つシティホテル的なホテル。部屋の窓から渡月橋が近くに見える。私達が感動したのは、その渡月橋の奥に聳える小倉山と愛宕山も一望できた、ということだ。素泊まりで一人12,000円(税込み)の宿泊料はチェックイン時に支払う。割高な感じもしたけれど、立地条件を考慮するとさもありなんと思う。 「風風の湯」を出てから、夕食は近くの和風なイタリアンレストラン「儘(MAMA)」で、京鴨やパスタの料理とワインを楽しんだ。京都の観光地としては比較的にリーズナブルなのかもしれないが、日本に住む一般庶民の私達にとっては(値段などが)高級に感じた。(^^;) イタリアンレストランでの夕食後は、阪急嵐山駅前のコンビニで明日の愛宕山登山の行動食(朝食用のおにぎりと昼食用の菓子パンなど)を買ってから、いそいそとホテルへ戻った。ここは矢張り盆地だ。京都・嵐山の夜風は思ったよりも冷たい。 佐知子の歌日記より 日本中熊出没のニュースゆえリュックに鈴つけ京都の山へ レース地の化繊の「キモノ」を着る女子ら清水寺をチャラチャラ歩く おのおののお顔をもちて菩薩様 三十三間堂に静かにおわす なくしたと受付に言えばなななんと腕に温泉ロッカーの鍵
軽くストレッチして、清滝バス停から歩き始めたのは6時50分頃だった。まずは坂を下って、清滝川に架かる渡猿橋を渡って閑静な清滝集落へ入る。この少し上流の辺りが地形図にも載っている「清滝川のゲンジボタル生息地」だ。 愛宕山の登山口でもある二の鳥居を過ぎると人家が途絶え、いよいよ勾配がきつくなってくる。とはいえ石段交じりの広い道なので、安心安全だ。昨今のクマ騒ぎの影響か、佐知子が熊鈴をザックにぶら下げていて、それがカランコロンと鳴っている。 道端に珍しいキノコが間をおいて2種…。其々のキノコには写真入りの種名板(ヌメリスギタケとヤマブシタケ)が、その傍らに添えてある。不思議なことに、誰もそれ(貴重で美味しいキノコ)を採っていないようだ。流石に信仰の山だなぁ、と感心する。そう、この登山道は愛宕神社の表参道で、云わば神域なのだ。 お助け水(水場)、嵯峨小学校清滝分教場跡、燧(ひうち)権現跡(17丁目)、一文字屋敷跡(20丁目)、と謂れ因縁のありそうな箇所を通り過ぎ、イロハモミジ(タカオカエデ)の紅葉が美しい三合目(25丁目・茶屋跡)の東屋で小休止。其々の地点に京都愛宕研究会による詳しい解説板があり、とても勉強になる。 それから五合目(30丁目・水口屋跡)と七合目(水尾の別れ)の東屋でも其々ひと休みして、近くのお地蔵様に手を合わせる。足元が赤色の岩(チャートかも)の箇所を過ぎて少し進むと樒(しきみ)小屋があるが、ここはかつて水尾の女性たちが神木のシキミ(マツブサ科の常緑小高木~高木:別名の一つにハナノキがある)を売っていた処で、「ハナ売場」と呼んでいたそうだ。…何れにしても、休憩場所がたくさんあるのは老境の私達にとっては幸いなことだ。 傾斜がなだらかになってきて、山頂が近くになってきた。 ☆愛宕神社表参道の丁石: 愛宕山の表参道コースを歩いていると古い丁目石(丁石=町石)と地蔵菩薩像や嵯峨消防分団が設置した標識が次々と出てきます。現地の解説板によりますと、鳥居本(とりいもと)の「一の鳥居」から山頂の愛宕神社までの距離は50丁(約5.5km)だそうで、参道沿いには板碑型と地蔵型の2種類の丁石(町石)が建立されている、ということだそうです。 ☆愛宕山ケーブル: 現地の解説板やウィキペディアの該当項などによりますと、戦前までは愛宕山鉄道…嵐山駅から清滝駅までの普通鉄道路線と清滝から愛宕駅までの(当時は東洋一といわれていた)ケーブルカー…が運行されていて、かなり賑わっていたそうです。終点の愛宕駅舎は「水尾の別れ」の南東約300mの距離の支尾根上に建っていたようで、地形図の等高線を読みますと標高約710m辺りに位置していたと思われます。その(旧)愛宕駅への現在の道は荒廃しているようですが、廃墟愛好家などにはけっこう人気があるらしいです。何れにしても…、盛者必衰というか、諸行無常の響きを感じます。 ☆愛宕山の中腹で観察のできた樹木: スギ、チャノキ(登山口近く)、コナラ(どんぐり)、クヌギ(どんぐり)、イロハモミジ、オオモミジ、ミズキ、カナクギノキ(クスノキ科クロモジ属の落葉高木・私にとっては珍しい樹木)、ウラジロウコギ、アカガシ(どんぐり)、アラカシ(どんぐり)、アセビ、ソヨゴ(赤い実)、…など。愛宕山上部の、表参道沿いの大杉の並木などはとても見応えがありましたが、自然林内では老木や大木が少なくて、意外と植生は若く(貧弱に)見えました。 樒小屋(ハナ売場)を過ぎてから、スギの巨木が林立するなだらかな丸太階段の道を進み、京口惣門とも呼ばれたという黒門を通り抜け、尚も石段を登る。それから両側に石灯篭が置かれた広い道を進み、左手の社務所を通り過ぎ、またまた石段を登り、ようやく立派な愛宕さん(愛宕神社)の本殿と奥宮に参拝する。つまりここが愛宕山の山頂部だ。 累積標高差で約900mのこの愛宕神社の表参道コースは、やっぱり、老ハイカーの私達にはけっこうきつい。展望の殆ど無い山頂部だったけれど、日本三百名山と関西百名山と近畿百名山と新日本百名山と、そして落語(愛宕山)の舞台にもなった愛宕山の山頂に立てたことに、私達は充分な満足感を得た。 下山ルートについては、往復登山とするか月輪寺(つきのわでら)を経由するコースを辿るか、少し悩んだ。で、トイレもある社務所横の休憩所でアンパンなどを食べながら、緊急夫婦会議となった。その結果…珍しく…私の腰痛悪化の訴えが通り、来た道(表参道)をゆっくりと下ろう、ということになった。(^^;) ということで、来た道をゆっくりと下って、清滝バス停に下山したのは14時10分頃。14時30分発の阪急嵐山行きのバスには余裕で間に合った。 途中から満員になった阪急嵐山行きのバスを嵯峨小学校前駅で途中下車して、相変わらず外国人観光客などでごった返している嵯峨・嵐山の目抜きを再び“観光”してから、丸太町通りを約20分間ほど東へ歩いて、この日の宿・シティホテル的な「サンメンバーズ京都嵯峨」にチェックインしたのは15時30分頃だった。ふぅ~、ちょっと疲れたこの日だったかも…。 [この日の歩数計:23859歩] ☆愛宕山について(補足): 愛宕山の三等三角点889.69m(点名:愛宕)は、愛宕山山頂(つまり愛宕神社)の北方約400mの距離にあります。下山後にホテルの(山好きの)スタッフの方から聞いた話では、「そこ(三角点のピーク)まで足を延ばすと京都方面の展望が広がりますよ」とのことでした。展望箇所の少ない愛宕山だったので、それ(三角点の辺りの展望が良いこと)を事前に知っていれば…腰痛をこらえて…三角点を目指したのに~、と少し後悔しました。なお、点としての愛宕山の山頂924mは愛宕神社内にありますが、一般人は立ち入りできないそうです。 日本山名事典(三省堂)などによりますと、愛宕山は(京都盆地周囲の山々…明日登る予定の小倉山も)古生層からなる、とのことで、チャートや頁岩が多いそうです。山中で見た赤っぽい岩は、やっぱりチャートだったようです。 また、同事典の「同名漢字の山」の順位表によりますと、愛宕山は全国に121座があるそうで、第3位だそうです。ちなみに第1位は城山の298座で、第2位は丸山の187座です。 佐知子の歌日記より 愛宕山総本山にお参りし何かのご利益期待しており
このページのトップへ↑ ホームへ |