|
No.283 シダンゴ山758m(丹沢前衛) 平成23年(2011年)1月20日 |
||||
小田急・新松田駅-《バス25分》-寄〜大寺集落〜シダンゴ山758m〜タコチバ山588m〜宮地山512m〜宮地集落〜田代向-《バス21分》-新松田駅…鶴巻温泉(途中下車・入浴)… 【歩行時間:
2時間50分】 |
 大寺集落の茶畑  シダンゴ山の山頂  アセビの蕾  宮地山の山頂  田代橋から宮地山 |
道標に従って歩き始めたのは10時05分頃。そのときはうっかりして忘れていたが、欄干を順番にたたくと「お馬の親子」のメロディが流れるという、中津川に架かる大寺橋を渡る。立ち止まって上着やセーターを脱いだり、大寺の休憩所でトイレへ行ったり、暫くはアスファルトをダラダラと登る。足柄茶の産地でもある大寺の集落は、何処も彼処もひっそりとしている。振り返ると鍋割山南稜の一角だろうか、谷を隔ててやわらかく聳える山々の景色が目にやさしい。坂道にある集落だから、この地の人はさぞかし足腰が強いんだろうと思った。
集落が途絶えた辺りでくだんの女性ハイカーに追い抜かされたが、彼女の足が早いのか、それともやっぱり私が遅すぎるのか、この先とうとう彼女を追い越すことはできなかった。猪避けの柵をくぐるとそこから山道になる。丸太階段などが随所にある、広くて整備された登山道だ。
コナラ、クヌギ、ヤマザクラ、シデ類、イヌガヤなどが明るく茂る天然林(雑木林)も所々交じるが、この山の殆どは人工林のようだ。鬱蒼としたスギ林が続く。除伐などの手入れをしないで放っておいた一角では、その林床にアオキが茂り、若いカシ類(アラカシやウラジロガシなどの照葉樹)が森の覇権をこっそりと狙っている。
ホースからチョロチョロと流れる水場を過ぎ、山腹をトラバースするように大きく左へ回り込んで登っていくとスギ林からヒノキ林へ移り変わる。やがて空が開け、もう既に蕾をたくさんつけたアセビ(馬酔木・ツツジ科)の林を通り抜けると、シダンゴ山の小広い山頂へ着いた。くだんの女性ハイカーがちょうど食事を終えたところだった。
三等三角点の標石や石祠などがあるシダンゴ山の山頂はまさしく360度の大展望だった。北面の表丹沢の山並みに迫力がある。その山並みの左端には富士山が、その左半分の容姿を覗かせている。更にその左側には箱根の山々、南面には逆光できらめく相模湾。ザックを置くのも忘れて暫くの間それらの景色を楽しんだ。これ(透き通った眺望)があるから冬の山行はこたえられない。
アセビは有毒植物なので動物が食べない。つまりシカなどによる食害の心配がない。だから山頂部にぐるっと植えたものと思われるが、それが大分育ってきていて、もう少し背が高くなると展望はスポイルされてしまいそうだ。そのときは、もしかして“展望台”が必要になるかも…、と余計なことを考えてしまう心配性の私だった。
大休止の後、片富士を正面に望みながら下山開始。ヒノキ林からスギ林へと下る。少し登り返して「タコチバ山・588m」と手書きされた小さな標識のあるピークを通り越し、また下ってほんの少し登るとそこが宮地山だった。宮地山の山頂部は、その手前(南側)がコナラ、クヌギ、ミズキ、ホオノキ、イヌシデ、アブラチャンなどの天然林で、柵越しの奥(山頂の北側)が薄暗いヒノキ林になっている、なんともみょうちくりんなロケーションだった。国土地理院の地形図(1/25000図)ではタコチバ山も宮地山も山名注記のない山だ。宮地山がこれから下る宮地集落の里山であることは何となく理解できるが、タコチバ山というこれも面白い山名の由来は何だろう? [→サイト検索などで少し調べたがわからなかった。]
大寺集落よりも更に閑静な宮地の里に下り、田代橋を渡って田代向のバス停に着いたのは午後1時50分だった。1時40分発の新松田駅行きのバスが出たばかりだったので、こじんまりとしたログ調の停留場をベースに、付近を散歩などして小1時間を過ごした。待ち時間を飽きずに使うのは私の得意とするところだ。
それでも予定時間よりずっと早い進捗だったので、どうやら帰路に小田急線の鶴巻温泉駅で途中下車して、例によって「弘法の湯」で山の汗を流していけそうだ。
今回は山岳展望も楽しめて充分に森林浴もできて、安全・安心で静かな単独行だった。もう少し気合を入れて、その南西に聳える高松山801mと繋げて歩いても面白かったかもしれない。しかしまぁ本音を云うと、まだ正月ボケの今の私には丁度いいボリュームだった。アセビの花が咲く頃(春)に、できたらまた来てみたいと思う。
* シダンゴ山の山名の由来について (山頂の石碑文を要約): 震旦郷(シタンゴまたはシタンゴウ)の震旦とは中国の旧異称(=支那)である。欽明天皇の代(539年〜571年)、この地に仏教を伝えた仙人が山上にいたというが、この仙人をシダゴンと呼んだことから地名が起ったという説がある。また、シダゴンとは梵語で羅漢(仏教の修行を積みさとりに達した人)を意味し、シダゴン転じてシダンゴウ(震旦郷)というようになったともいわれている。なお、この山は寄神社(旧弥勒神社)の元宮とされている。
ちなみに、国土地理院の地形図(1/25000図)では「ジダンゴ山」となっているが、これが明らかな間違いとは言い切れないからことは複雑だ。地形からくる「地団子説」もあるそうで、この山の山名由来も謎だらけだ。
 シダンゴ山の山頂からの展望 |
 宮地山のアブラチャン |
|
・・・乗客の半分(5割)近くは眼を瞑っている。携帯電話やゲーム機などをいじっている人が3割程度、新聞や本などを読んでいる人は1割程度。残りの1割は何か考え事でもしているのだろうか、虚ろな眼で中空をぼんやりと見つめている。平日のこととて、少数派のハイカーたちは会話に興じているか矢張り目を瞑っている。・・・車外の景色を眺めていたのはどうやら私だけのようだ。一体いつの頃からだろうか、この国の人が車窓からの景色を見なくなったのは…。 私達夫婦の長男が生まれた日…、それは36年前の今頃の風の強い日の午後だった。学生結婚でまだチョー若かった私は入職一年目。その日の東京の朝、通勤電車の窓から眺めたすっきりと聳え立つ白銀の富士山を、今でもはっきりと憶えている。その時の富士山を、もしも私に絵の才があるならば、寸分違わずに描き写すことが今でもできると思う…。 つい最近では、といっても1年半ぐらい前の、尻上がりにお天気が回復してきた日の、帰宅途中でのことだった。生まれて初めて見るほどのものすごい虹を、京急線の車窓から私は発見したのだ。それは東の空一面を囲むほどの、とてつもなく大きな半円形の美しい虹だった。私は狂喜した。誰かに教えたくて車内をぐるっと見回したので間違いないと思うが、そのとき虹を見ていたのはその車両の中では私だけだった。つまり私以外の誰もその虹には気がついていなかった、というか、誰も車外の景色を眺めていなかったのだ。…結局、なんか気おくれがして、車内の誰にも巨大な虹のことは伝えることができなかったけれど…。 そのときの巨大虹は20分〜30分の間、夕まずめまで、けっこう長い時間見ることができた。駅を降りて自宅に電話して、「とにかく、今すぐに東の空を見てみろ!」 と妻に伝えた。…あとから聞いた話によると、妻はその巨大な半円形の虹に感動して、近くに住む長女の家へ電話をしたそうだ。そして、長女や孫たちは2階の窓から東の空を眺めて 「スゴイね〜」 と、やっぱり感動したそうだ。その虹は、その日の夜のNHKニュースや翌日の朝刊でも紹介されていたほどの、滅多に見ることのできない素晴らしい虹だったのだ。 今の子供は…、子供でさえ、ゲーム機などに夢中でめったに車外の景色を眺めることがなくなった。私が子供のころ(昭和20年代〜30年代のこと)は、たいていの子供は電車の座席に座るとすぐにくるりと向きを変えて、後ろ向きになったものだった。移りゆく車外の景色に心がときめいたのだ。そしてそのあと必ず…、隣りの乗客に靴の泥をつけるからと、お母さんに叱られたものだ。 特にここ5〜6年前頃から、ドアーの窓際に立っていても、外を見ないで(携帯などを操作しながら)内側を向いている乗客が多くなったように感ずる。車外を眺めると、路線の近くにビルなどが多くなったので、目がチカチカしてしまうのだろうか。それとも、有名な人気俳優が有名なテレビや映画の場面でドア−の内側を向いて立っていたのだろうか…。ドアーを背にして内側を向くということは、他の乗客と顔を付け合わせることになってしまうということだが、それについては全く無頓着のようだ。車内の座席で化粧をする若い女性が目立つ昨今だが、“他人さまから見られることの恥ずかしさ”という感性が、いつの間にかこの国から消えつつあるのだろうか。ただ単に“他人の目を気にしなくなった”ということであれば、それはそれでいいことなのかもしれないが…。 無気味なり山手線の昼下がり あいつもこいつもスマホすりすり |
* ご意見ご感想は当サイトのBBS(掲示板)をご利用ください。
このページのトップへ↑
ホームへ
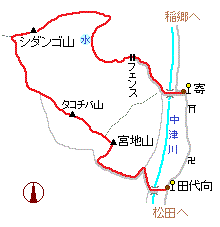
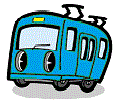 *** コラム ***
*** コラム ***