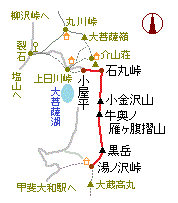|
No.288 北小金沢連嶺 平成23年(2011年)7月14日 |
||||||
…JR中央本線・塩山駅-《タクシー40分》-小屋平〜石丸峠1930m〜狼平〜小金沢山(雨沢の頭)2014m〜牛奥ノ雁ケ腹摺山1990m〜川胡桃沢ノ頭1940m〜黒岳1988m〜白谷ノ丸1920m〜湯ノ沢峠1650m・避難小屋-《タクシー50分》-はやぶさ温泉(入浴)-《タクシー10分》-塩山駅 【歩行時間:
4時間50分】 |
 狼平を通過  小金沢山の登り  小金沢山の山頂にて  牛奥ノ雁ケ腹摺山山頂  黒岳の山頂  黒岳の広葉樹林 |
柔軟体操をしながら、「バス停があるってことは、ここまでバスで来れる、っていうこと?」 とSさんが不審な表情で訊いてきた。 「土・日・祝しか運行していないんですよ」 と私。先月、大菩薩峠から石丸峠経由でこの小屋平へ下山した私なので[→大菩薩嶺]、一応そこいらの事情は知っているのだ。シーズンとか週末ならば、実際、JR甲斐大和駅前からの乗合バス(大菩薩上日川峠線・運賃は950円)、っていう手があるのだが…。
「平日のほうが山が静かだから…」 とT君が助け舟。なにやかやで、カラマツ林の山道を和気藹々と登り始めたのは9時40分頃。小屋平の標高はすでに約1585m。稜線(石丸峠)までの標高差は350メートル足らずだ。
おなじみの背の低いミヤコザサが広がり、右手前方に小金沢山(雨沢ノ頭)のピラミッド型の山容が見えてくる。眼下にはこの山域の景観におけるニューフェース・大菩薩湖(上日川ダム)がその地位を主張している。生憎の曇り空で、富士山や南アルプスは姿を見せていない。
石丸峠から狼平(おおかみだいら)にかけてはこの山稜屈指の開けて明るい処だ。ニガナ類(苦菜・キク科)やミツバツチグリ(三葉土栗・バラ科キジムシロ属)などの黄色くて小さな花が少しだけ咲いている。コメツガなどの木陰へ入るととても涼しい。狙いどおり、東京の喧騒と暑さはここでは無縁のものだ。(しめしめ)
小金沢山への登りは苔むした黒木の深森(自然林)で、奥秩父のそれにも似た幽趣がただよっている。三等三角点のある山頂は東側(奥多摩側)が開けていて、休憩するにはもってこいだが、この日はその方面に厚い雲がかかっていた。昼食後、山頂付近の樹種を少し観察してみた。コメツガ、イラモミ、シラビソなどのいわゆる黒木(この場合、亜高山性の常緑針葉樹をさす)の他にはダケカンバ、ナナカマド、ミネカエデ、カラマツ、ツツジ類などがこの森の主役たちのようだ。サラサドウダンやベニバナ(?)ツクバネウツギの花期は終わって、その花びらがあちこちに落ちている。色艶の衰えたハクサンシャクナゲの老花が必死に枝先にしがみついている。
小金沢山から先も、鬱蒼とした樹林と展望に恵まれた明るい笹原が交互に現れる“気持ちのよい尾根道”だった。シラビソが目立ち始め、牛奥ノ雁ケ腹摺山付近ではイラモミ(*)が優勢な林も通過する。黄緑色のそのイラモミの新葉が美しい。なお、牛奥ノ雁ヶ腹摺山(うしおくのがんがはらすりやま)は、日本で最も長い山名(音数で14音)であるらしい。
ミヤコザサの草原では、なんとあのウスユキソウ(薄雪草・キク科)が所々に咲いている。これはいいものを見た、と私たちは大喜びだ。しかし、立ち止まっていると羽虫類が顔の周りを飛び交って、それが煩い。…何気に、遠雷が聞こえる。何時の間にか奥多摩方面の雲が黒くなっている…。
心は急くのだが足がなかなか前へ進まない。常日頃の鍛錬を怠っているT君が特にバテ始めたが、T君と私より10歳も年上のSさんは元気だ。秘けつを訊くと、「今回初めて使ってみたダブルストックがいいみたい」 との回答だった。ふぅ〜ん、ダブルストックかぁ。私も今度試してみようかと思ったけれど、両手がふさがっていると、写真を撮るときなど仕舞ったり出したりが面倒臭そう…。
などと考えている場合ではない。遠雷が鳴り止まない。川胡桃沢ノ頭(かわくるみさわのあたま)を通り過ぎて黒岳への登りにさしかかる。岩っぽい個所もでてきた。なかなか前へ進まない足を一生懸命前へ出す。大峠からの道が左から合わさると間もなく、樹林に囲まれてひっそりとした黒岳の山頂へ着いた。高みの中央には一等三角点の標石が突き出ていて、ここでも小さな羽虫が煩く飛び回っている。
天空から薄日が差してきたりして、どうやら落雷の心配はなさそうだ。時間的な目安もたってまずは一安心だ。黒岳から少し下った雰囲気のよい林内に山梨県の案内板が立っていて、「やまなしの森林100選・黒岳の広葉樹林」と書いてある。ミズナラ、ダケカンバ、オオイタヤメイゲツ、ハウチワカエデ、ヤマザクラ、ナナカマド、オオカメノキ、ブナ(少し)などの落葉広葉樹にシラビソやコメツガなどの針葉樹が交ざる、なるほどここも素晴らしい森だ。林床ではカニコウモリが小さな蕾の花をつけて群落し、バイケイソウは来たるべき花の時季をじっと待っている。
さらになだらかに下ると草原が開け、花崗岩が散在する白谷ノ丸(しらやのまる)と呼ばれる小ピークを通過する。ここいら辺りのお花畑がこれまた素晴らしかった。ウスユキソウがあちこちに群落している。ハナチダケサシ(花乳茸刺・ユキノシタ科)、ヤハズハハコ(矢筈母子・キク科)、咲き始めのシモツケ(下野・バラ科)やヨツバヒヨドリ(四葉鵯・キク科)など、見ごたえがあった。
膝が痛いと言っていたT君。Sさんに借りたエアーサロンパスを吹っかけて、私が貸したインドメタシンの軟膏を塗ったら、あっという間に痛みが取れたとのことで、よかったよかった。疲れた身体と関節痛・筋肉痛には花の景色とインドメタシンが特効薬なのだ。
雑木林の道や背の高いスズタケの道をずんずん下って午後4時50分頃、ひょっこりと道標が現れて、その右手が湯ノ沢峠の小さな避難小屋と少し離れて建つログ調のトイレだった。避難小屋の左奥からの下山道(山道)もあるが、私たちは予定通りここからタクシーを呼ぶことにする。しかしヤバイ! 携帯電話が「圏外」を示している。まいったなぁ〜。やっぱり稜線上から電話しておけばよかった、と後の祭りだ。
冷たくて美味しい湧水の流れる水場でゴクンゴクンと水を飲んだりして、電波を求めてだらだらと林道を下ること約20分。ようやく携帯電話がタクシー会社に通じる。塩山から迎えに来るので40分はかかるという。私たち3人は道端に座り込んでタクシーを待った。しかしその時間がとても短く感じたほど、私たちの会話はずっと弾んでいた。
 イラモミの新葉 |
* 今回の北小金沢連嶺縦走は、交通費を使い放題使った“大名登山”ですが、景色の良さや木陰に入ったときの涼しさなど、中高年の中級ハイカーには特にお勧めの夏コースです。(もちろん残雪の春や紅葉の秋もいいと思います。) “黒木の原生林と明るい草原が織りなす”変化に富んだ尾根歩きはほんとうにステキでした。ガイドブックなどには “藪漕ぎ状態や道の分かりずらい箇所がある” と書かれているものもありますが、よく整備されていて比較的歩きやすい縦走路でした。もう少し早い時間に下山して、「天目山温泉」に立ち寄ってからバスで甲斐大和駅へ、というのがオーソドックスな帰宅コースだと思います。
なお、今回の山行で支払ったタクシー料金の合計は17,400円でした。3人のパーティーでしたので一人分は5,800円です。「特急あずさ」の往復運賃が7,800円でしたから、交通費の合計は一人13,600円です。(単独行ならば25,200円) 日帰りとしては確かに“バカ高い”かもしれません…。

湯上りに、ラストオーダー(20時)ぎりぎりまでビールを飲んだり“そば定食”などを食べたりした。ここの源泉を使って料理しているらしく、何を食べてもおいしかった。従業員さんたちの対応もとても感じよく、まったりと時を過ごすことができた。塩山駅までタクシーで約10分(1,520円)。
帰路の車窓からは南の空に皓々と小望月(こもちづき・14夜の月)が浮かんでいた。
→No.311「湯の沢峠から大蔵高丸とハマイバ丸」
 牛奥ノ雁ヶ原摺山から黒岳へ |
 草原にはウスユキソウの群落 |
このページのトップへ↑
ホームへ