|
3泊4日で日光の秋を歩く(前編) No.340 細尾峠から夕日岳(前日光) 平成27年(2015年)10月29日 |
||||
|
→ 地理院地図(電子国土Web)の該当ページへ 私の父が生まれ育ったのは栃木県小山市の片田舎で、近くに名前も水もきれいな思川(おもいがわ)が流れている。その故郷の川岸をもう一度歩いてみたい、と、うわ言のようにつぶやく父の日々が続いた。思い余って、父の実家を継いでいる(私とは従兄の関係の)Sさん夫婦に相談したら、今はちょうど農閑期なので、数日間なら(父を)あずかってもいいよ、と言われた。で、そのお言葉に甘えることになった。 と…、なんか、登山とは全然関係のないイントロで恐縮だが、このことが今回の(本当に久しぶりの)私達夫婦の泊まりがけの山旅に繋がったのだ。 …父を田舎に送り届けてから、その足で私達は日光へ向かった。  ●第1日目(10月28日・登山前日): 中禅寺湖畔を散歩したり、日光三名瀑の一つ・湯滝を見物したりして過ごし、日光中禅寺温泉に宿をとる。 ●第1日目(10月28日・登山前日): 中禅寺湖畔を散歩したり、日光三名瀑の一つ・湯滝を見物したりして過ごし、日光中禅寺温泉に宿をとる。ホテル花庵の南窓からは二荒山神社中宮祠の赤い大鳥居が近くに見えていて、中禅寺湖の対岸には(明後日に登る予定の)社山〜黒檜岳の山並みもよく見えている。そして西窓の障子を開けると、男体山が首が痛くなるほどの角度で大きく聳えている。暮れなずむそれらの(高級ホテルからの)景色を、私達はずっと見ていた。
まだ紅葉の美しい「いろは坂」をマイカーで下り、右折して朝もやの国道122号線を南西へ進む。カーナビの案内に従って、長いトンネル(日足トンネル)を抜けてから左折して旧道(長い長い峠道)を北東へ向かい、高度を上げる。ホテル花庵(中禅寺湖の北東岸)からは30分ほどのドライブで、標高約1190mに位置する登山口の細尾峠に到着する。…少し広くなっている路肩に駐車して、仕度して歩き始めたのは午前9時10分頃だった。 東へ向かって尾根道を登る。ミズナラとヤシオツツジなどのツツジ類の目立つ林相だが、ハウチワカエデ、チドリノキ(少し)、(3出複葉の)タカノツメ、イヌブナ(少し)、ブナ(少し)、ハリブキ、ヤシャブシ、コシアブラ(少し)、ナナカマド(少し)、リョウブ、シデ類などもしっかりと自己主張している。林床は、この山域でもおなじみのミヤコザサだ。 ゆっくりと歩いたつもりだが、あっという間に(50分ほどの歩程で)三等三角点(点名:石沢)のある薬師岳1420mの山頂へ着いた。しかし残念。朝霧がなかなか晴れず、展望を得ることができない。 自然林の明るい尾根道を南へ進むとダケカンバも目立ち始め、黄葉を少し残した所々のカラマツ林にも風情がある。やがて霧が晴れてきて、樹林の隙間からは男体山・女峰山や皇海山、そして高原山などもチラチラと見えだした。 私達が歩いている今回の快適なトレイルは「禅頂行者の道」と名付けられている古道で、日光男体山開山で有名なあの勝道上人も歩いた修行の道でもあるという。つまり私達は今、勝道上人と同じ眺めを得ているのだ。とはいえ、ちょっとしたピークを4つ〜5つは越えていくこの尾根歩きは、常日頃の鍛錬不足の私達にとってはけっこうきついアップダウンだ。夕日岳への分岐(三ツ目)は直進して、まず地蔵岳に登ってみる。 地蔵岳の山頂部は広くなだらかで、ミズナラ、ダケカンバ、カラマツ(南側)、タカノツメ、ホオノキ、ツツジ類などの樹木に囲まれてひっそりとしている。そんな樹種をメモりながら少し奥へ進むと、立方体の大石(高さ70〜80センチ)が足元にある…。「お〜ぃ、来てみな。灯篭みたいな変な石があるよ〜」 と佐知子に声をかけた。…近寄って、その立方体の石の廻りをぐるっと回った彼女が 「これって地蔵堂じゃぁないのぉ。だから地蔵岳なのよ」 と大声で笑った。石の裏側(ほんとうはこちらが表側)を覗いてびっくりした。これは石祠で、その中にはお地蔵さま(勝道上人の石像かも)が入っているのだ。私も大笑いだった。 三ツ目に戻ってから右折して、主稜から東へ離れて聳える夕日岳1526mへ登り返す。しかしこちら側は霧が発生していて何も見えない。夕日岳山頂の二等三角点(点名:河原小屋)標石の傍らにどっかと腰をおろして、菓子パンで昼食にしたが、とうとう何も見えない。この北側は開けているので日光連山などの眺めは良いはずだが、それがちょっと残念だ。 夕日岳の山頂部にたくさんある白っぽい小石を拾ってルーペで観察してみた。品のいい凝灰岩、といった感じだが、これが溶結凝灰岩(流紋岩質凝灰岩?)なのかもしれない。植生も地蔵岳や薬師岳と似たりよったりだが、五葉のツツジ(ヤシオツツジ)が特に多いのと、つるつる樹肌のナツツバキ(シャラノキ)が山頂部の中央にぽつんと立っていたのが印象に残った。 来た道を北へ戻る。薬師岳の肩の少し手前(歩程にして約15分)の道端に、往路では気が付かなかった(宝暦十四年と彫られた)石祠とその左隣に不動明王(金剛童子?)の石像があるのを発見した。これらもやはり、ササを背にして南を向いていたから往路では見逃した、のかもしれない。 薬師岳の肩で小考した。再び薬師岳の山頂を目指すか、どうするか。標高差は30m〜40m程度なのでたいしたアルバイトではないが、やっぱり疲れた私達は“巻き道”を選んで左折した。しかしこの巻道がけっこうなくせ者で、崩壊箇所を通過したり、落ち葉が被さって道が分かりにくかったり、…と、少し冒険っぽかった。まぁ、赤テープや黄・赤の道標(例の正方形のプレート)を見逃さなければ問題はないので、変化を楽しんだりして、かえって良いアクセントになったと思う。 細尾峠に戻り着いたのは午後3時半頃。山中で出遭ったのは2組3名のハイカーだけ。思川源流域の、静かな夕日岳だった。 今夜からは同じ中禅寺温泉の、懐かしの「日光山水」に宿をとってある。「ホテル花庵」からは300mほど西に位置しており、やっぱり中禅寺湖が部屋の窓から大きく見渡せる好ロケーションだ。 * 私達が歩いた薬師岳から地蔵岳への主稜線は栃木県の日光市と鹿沼市との境界線上にあるが、この地蔵岳1483mから更に南西へ(古峰ヶ原峠〜粕尾峠方面へ)向かってその境界線を(直線距離にして)10Km近くも進むと、もうひとつの地蔵岳1274mが聳えている。 この薬師岳から二つの地蔵岳へ続く山稜の西側の沢は渡良瀬川に集約されている。そして、大雑把な見方だが、その山稜の東側が(東)大芦川で、その少し下流で父の故郷の川・思川(おもいがわ)に吸収されている。つまり、(主稜から東へ離れて聳える)夕日岳に降った雨のすべては思川に流れ込んでいるのだ。 …思川は下流で渡良瀬川と合流して、坂東太郎(利根川)に吸収されて太平洋へ注いでいる。 佐知子の歌日記より 青空にうかぶ白雲つかもうと ダケカンバの枝八方に伸ぶ 白雲が幕を引くよにたれこめて 男体山の半身隠す
このページのトップへ↑ ホームへ |
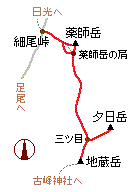








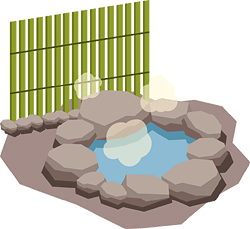 今回の山旅では中禅寺湖の入り口(北東岸)に位置する中禅寺温泉に3連泊しましたが…、諸々の都合で2軒のホテル…初日の高級な「ホテル花庵」と比較的にリーズナブルな(2・3日目の)「日光山水」を…期せずして利用することになりました。で、その差は(宿泊料金に比して)いかほどのものだったか、いかほどもなかったような…、などといった感想をもちました。
今回の山旅では中禅寺湖の入り口(北東岸)に位置する中禅寺温泉に3連泊しましたが…、諸々の都合で2軒のホテル…初日の高級な「ホテル花庵」と比較的にリーズナブルな(2・3日目の)「日光山水」を…期せずして利用することになりました。で、その差は(宿泊料金に比して)いかほどのものだったか、いかほどもなかったような…、などといった感想をもちました。