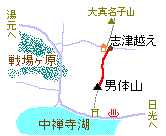|
No.107 男体山2486m 平成12年(2000年)6月24日〜25日 |
|||||
《マイカー利用》 …日光見物・戦場ヶ原散策…中禅寺温泉(泊)-《車》-志津越え(志津峠)・志津小屋〜男体山・奥宮[往復] |
 戦場ヶ原  中禅寺温泉「日光山水」 後日(H27年10月)撮影 |
自然研究路の湿原の中に、取り外された木道の古い板が積み重なって放置されていたが、少し目障りに感じた。レンゲツツジの花期は終わっていたが、広い緑の湿原の中にワタスゲの純白の綿毛が点々と咲いていた。戦場ヶ原にもやっと夏が来たんだな、と思った。
しっとりとした日光散策を楽しんで、この日は予約の中禅寺温泉に宿をとった。
* この15年後の秋(H27年10月)、夕日岳登山及び社山・黒檜岳登山の際に再び「日光山水」に宿泊する機会を得ました。宿泊料は同じ(2食付き)12,000円で、サービスや料理も、相変わらず充分に満足のいくものでした。これからも中禅寺湖畔に宿をとるときはこの宿に決めようね、と佐知子とも話しました。少し気になったのは、露天風呂の(源泉の)湯量が随分と少なくなったような、そんな印象を受けたことです…。[後日追記]
![]() 戦場ヶ原自然研究路 : 私達の山旅日記の該当項です。参照してみてください。
戦場ヶ原自然研究路 : 私達の山旅日記の該当項です。参照してみてください。
6月25日(男体山登山): 中禅寺温泉の宿、午前4時起床。昨夜は7時半にはもう寝ていたから、睡眠は十分だ。本日は「奥日光パークマラソン」の行われる日とのことで、マラソンに参加するという同宿のグループ数組と共に、宿の計らいで早朝6時に朝食をとることができた。
 志津小屋  イワカガミ  抜け落ちた太刀 |
裏男体林道と志津林道の分岐点(志津越え=志津乗越=志津峠)の片隅に車を停め、軽快に歩き出したのは午前7時頃だった。深い霧のため視界は悪いが、幸い雨は降っていない。佐知子のザックに付いているキーホルダーのバカチョン温度計によると、気温約13℃だ。小鳥たちが盛んに囀っている。
笹の道を少し歩くと立派な丸太造りの無人小屋(志津小屋・志津宮社務所)に着く。傍らに鳥居と小さな社が建っている。社務所の案内板によると、ここは海抜1785m、フルネームは「二荒山(ふたらさん)神社志津宮」といい、御祭神は大国主命(オオクニヌシノミコト)とその家族[后神の田心姫命(タゴリヒメノミコト)と御子神の味耜高彦根命(アジスキタカヒコネノミコト)・舌をかみそうな名前の神様だ]とのことだ。この一帯は日光連山の中心であるため、昔から日光修験道(峯修行)の重要な拠点とされていたらしい。社に向かって手を合わせ、先を急ぐ。
樹林の道は徐々に険しくなってくる。三合目付近の何ヶ所かにゴゼンタチバナがたくさん咲いていた。思わず足を止め、シャッターを切った。四合目の標柱の傍で1回目の小休止…、といっても私達の小休止はだいたい何時も15分間以上になってしまう。細めのダケカンバ(若木かな…)の目立つ山道、その暗褐色の樹皮の皮目が美しい。山はまだ新緑だ。
四合目を少し過ぎた辺りから山頂近くまで、登山道沿いのあちこちに濃桃色のイワカガミが今を盛りと咲いている。オシャレで可憐なイワカガミの思いがけない群落に、何度も立ち止まった。
七合目で2回目の小休止。ここにもイワカガミがたくさん咲いていた。
八合目の辺りから道は火山性の赤ザレとなる。白い蕾をつけたシャクナゲが目立ち始めた。
山頂に着いたのは午前10時丁度。気温約12℃、西の微風。人影は少ない。細長く広い山頂部はホワイトアウトで、展望は得られなかった。山頂部中央、三角点標石の少し先、大岩のある処が頂上のようだ。この岩上に赤城山の方を向いた太刀が立っている、とのことだったが、太刀は倒れてしまっていた。どうやら、つい最近のカミナリに打たれたらしい。岩の下に落ちていた錆びた太刀は長さ5メートル近くはあっただろうか、思っていたよりもずっと大きい。試しに持ち上げてみようとしてみたけれど、重たくて殆ど動かなかった。
山頂部をさらに先へ進み、二荒山神社奥宮で柏手を打つ。社の傍で宿で握ってもらったオニギリを食べ、午前10時50分、下山開始、来た道を引き返す。途中1回休んで、志津越えに戻ったのは12時50分だった。何時の間にか霧雨が降っていた。
今回の山行、アプローチでマイカーを使い、標高差にして500メートル近くもズルをし、随分と楽をしてしまった。本来は二荒山神社中宮祠から、登山料(大人500円・小人300円)を支払って登山するものなのだろう。帰路、流石に気が引けて、二荒山神社中宮へ立ち寄ってお参りをした。お賽銭もめずらしくはり込んだ。何時もは一円玉か五円玉しか使わない佐知子が、ウン百円を賽銭箱に投げ込んだ、と言っていた。
神社脇の「旅の駅」で食べた湯葉の煮付けがまた美味しかった。
* 男体山(なんたいさん)の山名について: 二荒山(ふたらさん)、日光山、黒髪山(くろかみやま)、国神山(くにかみさん)、日光富士などとも呼ばれている。西暦782年、下野の僧勝道が開山、補陀落(ふだらく)山がのち二荒山とあらためられ、これを「にこう山」と読んで日光の地名になったといわれている。
* 男体山の標高変更について: 2003年(平成15年)10月7日の国土地理院の発表によると、日光男体山の標高が2メートル高くなって2486mになったそうです。今までは三角点2484mの標高をそのまま男体山の標高としていたのを、11mほど離れた地点(剣の立つ岩盤辺り)をもって最高標高値にした、とのことです。[後日追記]
 山頂の御神像(まだ真新しい) |
 ダケカンバの若い木の下で… |
|
*** コラム *** * 読売新聞の記事の要約: ・・・男体山はこれまで、直近の噴火時期が1万4千年〜1万5千年前とみられていたが、富山大の石崎泰男助教授(火山学)らが2005年秋、火口内にある火山灰や軽石を含む厚さ5〜20mの地層から樹木を採取して分析した結果、この地層が7000年前の噴火でできたものであることがわかったという。気象庁の火山噴火予知連絡会で正式に活火山と認定されれば、周辺自治体は、噴火を念頭に置いて防災計画を練り直していくことになりそうだ。・・・ * 日本の活火山の過去の火山活動による分類(ランク分け)について: 気象庁では、概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山を活火山としています。 活火山には現在活発に活動している火山から噴火の可能性はあるものの長期にわたり静穏な火山まで様々あります。そこで、過去の火山活動の度合いを最近100年間と過去1万年間の2つの期間で調べ、最も活動的な火山をAランク、次に活発な火山をBランク、残りの火山はCランクと、3つのランクに平成15年1月に分類したとのことです。[気象庁の公式サイト(日本の活火山分布)を参照して記述しました。] |

中禅寺湖の対岸(半月山の展望台)から眺めた男体山(撮影:H20年10月)
このページのトップへ↑
ホームへ