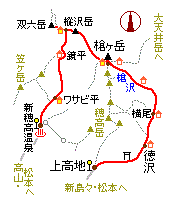 |
第1日目

ワサビ平小屋にて
第2日目

小池新道に入る

秩父沢を渡る
第3日目

慎重に!

西鎌尾根を進む

槍の肩に到着

槍ヶ岳の頂上
第4日目

槍ヶ岳山荘

槍沢を下る
|
高所順応しながらゆっくりと山頂へ
第1日=新宿駅前-《高速バス4時間35分》-平湯-《バス33分》-新穂高温泉〜ワサビ平小屋 第2日=ワサビ平小屋〜鏡平〜双六小屋 第3日=双六小屋〜樅沢岳2755m〜左俣岳2674m〜千丈沢乗越〜槍ヶ岳山荘〜槍ヶ岳 第4日=槍ヶ岳山荘〜(槍沢)〜横尾〜徳沢園〜上高地-《タクシー20分》-沢渡(入浴)-《タクシー35分》-新島々駅
【歩行時間: 第1日=1時間30分 第2日=6時間 第3日=6時間20分 第4日=7時間40分】
→ 国土地理院・地図閲覧サービスの該当ページへ
山の仲間たち(山歩会)をお誘いして槍ヶ岳へ行ってきた。西鎌尾根を上り槍沢を下る、というロングルートだ。高所順応のためもあり、上りに3日間をかけてゆっくりと歩いた。私は17年ぶりの7回目、妻の佐知子は3回目の槍ヶ岳だった。
第1日目(7月27日・曇): 新宿駅前から飛騨高山行きの高速バスに乗り平湯バスターミナルで降りる。平湯のレストランで昼食後、乗合バスで終点の新穂高温泉へ。ここ1〜2週間に降り続いた“豪雨”の影響だろうか、蒲田(がまた)川の水量は異常なくらい多くて、激しい波しぶきを上げて流れている。その蒲田川に沿った左俣林道を、植物観察などをしながらゆっくりと2時間ほど歩き、懐かしのワサビ平小屋に着いたのは4時少し前だった。
小屋の風呂でひと汗流してから夕涼みをしていたら、大阪に単身赴任をしているT君が、名古屋からの高速バスを利用して私たちの本隊に合流して 「いよッ!」 と挨拶した。これで今回参加の7名が揃い、ビールとジュースで乾杯して、明日からの英気を養った。
第2日目(7月28日・曇雨): 4時30分からの朝食を済ませてから、歩き始めたのは5時15分頃。北アルプスの山小屋も随分と朝が早くなったものだと思った。空模様がちょっと怪しい…。
ゴロ石を踏んだり枝沢や雪渓を渡ったりして小池新道を進み、快調に高度を上げる。道端にはキヌガサソウやサンカヨウなどがきれいに咲いている。行く手の上空には暗雲が立ち込めていて、雨が降ったり止んだりしているけれど、振り返るとすっきりとした青空が覗いていて、焼岳がよく見えている。
鏡平小屋で早めの昼食。T君だけが700円のカレーライスであとの6名は600円のラーメンだった。鏡池などからドカーンと見えるはずの槍ヶ岳などの景色は全く霧の中だった。しかし色々な花がよく咲いていて、目は飽きない。
本降りになり始めた午後2時頃、双六小屋に辿り着いた。双六岳往復の予定を取り止めて、小屋の談話室で夕飯までの時間を楽しく過ごした。
雨は降り止む気配が無く、その激しい雨音で夜中に何回も目が覚めた。
* 小池新道及び西鎌尾根に咲いていた高山植物: ゴゼンタチバナ、ツマトリソウ、コイワカガミ、マイヅルソウ、キヌガサソウ、サンカヨウ、ハクサンイチゲ、ミヤマダイモンジソウ、ミヤマキンポウゲ、シナノキンバイ、チングルマ(少)、ハクサンフウロ、ヨツバシオガマ、ハクサンチドリ、イワオウギ、クガイソウ、ニッコウキスゲ(少)、キンコウカ、コバイケイソウ(少)、クルマユリ(少)、ミヤマクロユリ、キバナノコマノツメ、ミヤマキスミレ、ツガザクラ、コメバツガザクラ、アオノツガザクラ、ウラジロタデ、ウサギギク、ハクサンシャクナゲ、キバナシャクナゲ(少)、イワギキョウ、チシマギキョウ、イブキジャコウソウ、ヤマハハコ、ミネウスユキソウ、ツメクサ類、ハイマツの赤い花・・・など
第3日目(7月29日・雨曇): 双六小屋の朝食後、気合を入れて歩き出したのは5時35分。未明までの激しい雨は収まったようだが、今日もパラパラ雨が降ったり止んだりしている。
霧の樅沢岳(もみさわだけ・2755m)を通り過ぎ、高山帯(ハイマツ帯と岩礫帯)のアップダウンを繰り返しながら、槍ヶ岳の西鎌尾根を進む。時折霧が晴れて近くの硫黄岳へ続く茶褐色の独特な岩稜線が左下に見えてくる。足元にはミネウスユキソウやタカネツメクサなどが可憐に咲いている。
それは風雨のなかで中食をとってから暫く進んだ、午前11時30分頃のことだった。突然目の前に大きな岩峰が出てきたので、先頭を歩いていた私は 「なんかかっこいい岩山があるからここで記念撮影をしようか…」 と云って、カメラを向けた。 「あれェ…?」 と思った。誰かが 「これって小槍?」 と云ったけれど、小槍はこんなに大きくないし、だいたい小槍はこの左側の出っ張りだよ、と云ったら、みんないっせいに 「じゃぁ、これって槍ヶ岳!」 疲れ始めていたメンバーたちは小躍りして喜んだ。
私はコースタイムを勘違いしていた。槍ヶ岳の肩に着くのはまだ少なくても30分以上はかかると思って、そのようにみんなに告げていたのだ。しかし、これがかえってよかったのかもしれない。想定外の突然の到着に喜びが倍増したようだ。
槍ヶ岳の肩(槍ヶ岳山荘)にザックを置いてから、正味1時間の山頂往復をした。生憎のガスで展望は無かったけれど、二等三角点と木祠の狭い山頂は感動の坩堝(るつぼ)だった。3000メートル峰は初めてというご婦人メンバーの中には涙を流している人もいたようだ。
夕まづめ、短い時間だったけれど、四周の霧が晴れて展望が開けた。ここでも感動だった。
槍ヶ岳山荘も予想したほどは混んではおらず、ゆったりとできたのが何よりだった。
* 今回久しぶりに槍ヶ岳を登ってみて気がついたのは、山頂直下に長い鉄梯子が整備されて、山頂直前の北東側の怖い岩場(廻り込む)を通らなくなった、ということだった。平成元年に登ったときも(確か)長い鉄梯子はまだなかったもののルートが若干変更されていて、それほどの恐怖は感じなくなっていた。私が始めて槍ヶ岳へ登った昭和41年の頃は、それはもう本当に怖く感じたものだった…。
第4日目(7月30日・快晴): ヤッタァ! 快晴だ! 大パノラマだ! 未明から表へ出て、稜線上を大喰岳方面へ行ったり槍ヶ岳の中腹まで登ってみたり、北アルプス南部の大景観を思う存分楽しんだ。モルゲンロートに染まる岩肌や遠くの大雲海など、山の朝の移りゆく景色はまさしく「美のドラマ」だ。
午前6時、下山開始。槍沢を下る。前方正面の谷越しには一昨年にほぼ同メンバーで歩いた蝶・常念の稜線が見えている。途中、播隆上人が寝泊まりしたという「坊主の岩小屋」の前などでは立ち止まって、振り返って、槍ヶ岳の雄姿を目に焼き付ける。軽い高山病の症状で頭痛がすると云っていたメンバーもいたけれど、高度が下がるにしたがって全快したようだ。いつものようにニギニギしく、ひたすら下る。
大曲りを過ぎる辺りからは傾斜もゆるくなって歩きやすくなる。長い道のりの下山路だったけれど、楽しい会話をしながら歩いていたら、午後2時50分頃、案外あっけなく上高地のバスターミナルへ着いてしまった。
上高地からは少し贅沢をしてタクシーを利用した。途中、「さわんど温泉」で山の汗を流してから新島々駅へ向かった。
帰路の「スーパーあずさ」の車中。66歳の男性メンバーのSさんが 「この歳で槍ヶ岳へ登れるとは思わなかった。ありがとう」 と私に云ってくれた。私は、なんかそのとき涙が出てきて、それを隠すのに骨が折れた。
 表銀座縦走(燕岳〜大天井岳〜槍ヶ岳): 後日(平成20年8月)の山行記録です。 表銀座縦走(燕岳〜大天井岳〜槍ヶ岳): 後日(平成20年8月)の山行記録です。
 縦走登山(夏期)の注意点について: 今回の槍ヶ岳山行にあたって会員用(初心者用)に作成した「しおり」の一部です。参考にしてみてください。 縦走登山(夏期)の注意点について: 今回の槍ヶ岳山行にあたって会員用(初心者用)に作成した「しおり」の一部です。参考にしてみてください。
  さわんど温泉「上高地ホテル」: 夏のシーズンに沢渡(さわんど)までは一般の車両が入ることができるが、この上高地の玄関口に最近引湯された新しい温泉が「さわんど温泉」だ。平成10年に安房トンネル掘削に伴い大量に湧出した高温の温泉を約7Km引湯して誕生したらしい。日帰り専用も含めて数軒の温泉施設があるが、私たちがタクシーの運転手さんに紹介されたのは「上高地ホテル」だった。単純温泉(弱アルカリ性低張性高温泉)、掛け流し、岩風呂、露天風呂、無色透明。入浴料一人650円。シックでくつろげる風呂だった。上高地へ下山したときの帰路、途中下車して立ち寄るにはうってつけの温泉地だと思う。 さわんど温泉「上高地ホテル」: 夏のシーズンに沢渡(さわんど)までは一般の車両が入ることができるが、この上高地の玄関口に最近引湯された新しい温泉が「さわんど温泉」だ。平成10年に安房トンネル掘削に伴い大量に湧出した高温の温泉を約7Km引湯して誕生したらしい。日帰り専用も含めて数軒の温泉施設があるが、私たちがタクシーの運転手さんに紹介されたのは「上高地ホテル」だった。単純温泉(弱アルカリ性低張性高温泉)、掛け流し、岩風呂、露天風呂、無色透明。入浴料一人650円。シックでくつろげる風呂だった。上高地へ下山したときの帰路、途中下車して立ち寄るにはうってつけの温泉地だと思う。

このページのトップへ↑
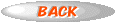 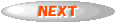

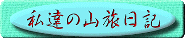
ホームへ
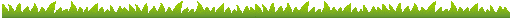
|















