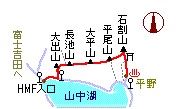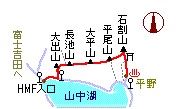 |

山中湖畔から富士山

ブナの冬芽

山道へ入る

石割山山頂にて

石割神社

ご神体に突入!

ミニラッセル…
|
富士山展望の雪道をミニ縦走
新宿-《高速バス約130分》-ホテルマウント富士入口〜大出山入口〜長池山1178m〜飯盛山〜大平山1296m〜イモ山〜大窪山1267m〜平尾山1290m〜石割山1413m〜石割神社奥社〜一本松分岐〜平野温泉(入浴)-《タクシー10分》-山中湖バスターミナル-《高速バス約130分》-新宿 【歩行時間:
5時間30分(雪道・約40分間の道迷いを含む)】
→ 地理院地図(電子国土Web)の該当ページへ
新宿の高速バスターミナルから午前7時10分発の山中湖行きに乗る。バスは西へ向かって快調に走り、前方に見え隠れする白銀の富士山がどんどん大きくなってくる。日本晴れの富士見日和だ!
この富士急中央高速バスは割安で便利な人気の路線で、この日も満員状態だった。昨日の午前、思い立って座席確保のためインターネット予約を利用したのだが、既にこの便は三角印(残り座席が少ない)で、私達夫婦は滑り込みセーフだったのだ。
山中湖西岸の“ホテルマウント富士入口バス停”に着いたのはほぼ定時の9時20分頃だった。山中湖は大半が凍っていたが、未凍結部分の湖面には地元の方たちが大切に育てているという白鳥(コブハクチョウ)や雁(カナダガン)などが群れをなしていた。ときたま飛び立つ白鳥のツガイの姿など、富士山をバックにした巨大な名画を見ているようだ。その特に美しい瞬間を狙っているのだろうか、数名のカメラマンたちが湖岸の雪上に三脚を据えてじっとしている。
大出山入口バス停の交差点で湖岸の道を左(北の方向)へ曲がって間もなく、問題の二又にさしかかった。歩き始めてまだ20分足らずのアスファルトの地点である。路上の残雪が所々凍結しているので慎重に歩いていたのだが、足元ばかりを見ていたせいか、指導標をよく確認もせずにその二又を右手に進んだのが「道迷い」の始まりだった。
私達が進んだ右手の車道はその先で更に二手に分かれていた。多分こっちだろう、と、これもよく考えもせずに道なりの右手へ登り進んだが、この道は行き止まりになっていた。戻って左手へ進んでも矢張り積雪のため行き止まりで、道らしきもののない鬱蒼とした林が続いている。どうやらこの辺りは閑静な別荘地のようだ。 「ねぇ、なんか変じゃないのぉ…?」 と妻の佐知子が云っている。
地形図とコンパスを取り出してじっくりと調べたら、どうやら最初の二又で既に道を間違えていたことに気がついた。もうこの時点で私達は汗だくだったが、進むべき方向がはっきりと分かったので心は軽かった。タイムロスは40〜50分程度、だったろうか…。
レークサイド山中湖の少し先から指導標に従って山道へ入る。今冬は雪が多いとのことで心配していたのだが、雪の深さは30〜40センチ程度で、トレース(踏跡)もしっかりとしていてそれほど歩きにくくはない。さくさくとした純白の雪で、アイゼンはつけなくても何とかなりそうだ。ミズナラ、ブナ、シデ類、ヤマザクラ、アカマツ、モミ(ハリモミ?)などが疎に生える明るい天然性林や右手の(多分)カヤトの斜面など、とても気分のよい尾根道だ。いきなりの「道迷い」のダメージはあっという間に吹き飛んで、冬芽の観察や山座同定をする余裕も出てきた。
左手の三ツ峠山などの御坂の山々が、カラマツなどの樹林の隙間からよく見えている。その右手前の杓子山(しゃくしやま)から鹿留山(ししどめやま)と連なる台形状の山並が意外と近くて大きい。
左からの東海自然歩道と合流して、長池山、飯盛山と快調にアップダウンする。雪上のあちこちにはウサギやタヌキなどの足跡(フィールドサイン)があり、その足跡の乱れなどで状況を推察したりして、興味は尽きない。
あずま屋や二等三角点やテレビ局のアンテナもある広い大平山の山頂で昼食にした。行く手(東面)の平尾山や石割山の左奥には、この道志山塊の盟主たる御正体山1682mが聳えている。そして何といっても、後方(西面)の山中湖上空に両翼を目いっぱい広げた富士山がバカでかい。足跡の無い新雪の山頂部を、オニギリをほおばりながら行ったり来たり、至福のひとときだ。何気に、富士山の右手には南アルプスの主峰たちが矢張り真っ白にズラッと並んでいる。
イモ山、大窪山と小ピークを過ぎ、右下に芙蓉台別荘地の景色が広がる鞍部から深い雪道を登り返すと平尾山の山頂で、このころから数組のハイカーとすれ違った。どうやらこのミニ縦走コースの主流は、東側の平野を基点にした石割山〜平尾山の周回コースのようだ。しかし富士山展望についてなら、長池山から大平山までの(西側の)山稜からのほうがスッキリとしていると思う。石割山から平尾山にかけての(東側の)稜線からの富士山展望は、至近距離の大平山などの山容が富士山の足元を隠してしまい、風景のバランスが悪いと思うのだが…、如何なものだろう。もっとも、その足元がスッキリとしない風景が返って良い、と云う人もいるかもしれないが…。
最後の登りで三等三角点のある石割山の山頂へ辿り着いた。その少し先にある鉄塔に向かって進むと、杓子山・鹿留山の全体像や御正体山へ続く山稜が一層はっきりと望める。振り返って眺める富士山や南アルプスなどの西面の景色もおさらいしてから、南へ向かって下山を開始する。
ミズナラやブナやスズタケの明るい自然林を下って間もなく、石割山の山名の由来でもあるという石割神社奥社へ着いた。参拝してからご神体(大岩)の割れ目をくぐり抜けてみた。ザックを下ろさないと抜けられないほどの窮屈な隙間で、ご神水も湧いていたり、ちょっと面白かった。3回通るとご利益があるそうだが、私達は1回しか通らなかった。でも、3分の1くらいのご利益はあるかもしれない。解説板によると、ここは「天の岩戸」伝説を秘めた地であり、蜃気楼が現れる霊山でもあるらしい。
石割神社奥社から少し下ると、ご神木のカツラの巨樹が現れ、こちらにも立派な解説板が立っていた。近くにある“お釜石”から源流の水が湧き出しているとのことで、これが「桂川」の名前の由来であるらしい。桂川は相模湖へ流れ、相模川となって太平洋(相模湾)に注いでいる。
分岐の「一本松」には立派なあずま屋があり、そのまま真直ぐ(右手へ)長い階段を下るのが正規な登山道(参道)のようだが、私達は平野温泉「石割の湯」で下山後の入浴を楽しみたいので、左手の林道方向へ進む。しかし、この道にはまったくトレースがなかったので、ちょっとしたミニラッセルになってしまった。膝下の雪で、しかもなだらかな下りなのでなんということはないのだが、ずっと先頭を歩いていると矢張り疲れるので、佐知子と交代しながら下った。なんの傷跡もない純白で平らな雪面をザクッ・ザクッっと歩くのはとても気分がよく、「僕の前に道はない、僕の後ろに道は出来る…!」 などと高村光太郎を気取りながら歩いた。
記念碑の立つ源泉塔の脇を通り過ぎ、「石割の湯」へ下り着いたのは16時50分頃だった。道にも迷わずにもう少し早く歩くか下山後の入浴を端折れば、近くの平野バス停から17時20分発の新宿行き高速バスに楽々と乗ることができたのだが、私達にはそんなせわしない山旅は似合わない。アルカリ性の湯にゆっくりと浸かって山の汗を流し、大広間でおでんをつまみにビールを飲んで、それから予約したタクシーを利用(タクシー料金2,510円)して山中湖バスターミナルへ出て、同バス停18時30分発の高速バスに乗り込んだ。車窓の外はとっくに暮れていて、宵闇の西空に残る微かな薄明かりを背に、やっぱり大きな富士山が、私達に覆いかぶさるように黒々と聳えていた。
げっぷが出るほどたんまりと富士展望を楽しんだ今回の山旅だった。もう当分は富士山を見なくてもいい、とそのときは思うのだが、暫らく経つとまた無性に見たくなる山、それが富士山の富士山たる所以かもしれない。
 石割山ミニ縦走の写真集: 大きな写真でご覧ください。 石割山ミニ縦走の写真集: 大きな写真でご覧ください。
  平野温泉「石割の湯」: 平野バス停から歩いて約15分、石割山の南麓にある村営の日帰り温泉施設。僭越ながら、総合的にバランスの取れた優れた温泉施設だと拝察した。建物が木造でエキゾチックなのがいいし、内湯・外湯がそれぞれ石張りと檜枠造りの2種類あって贅沢感があるのがいい。和風の大広間などがゆったりとしていて、落ち着いてビールを飲んだり食事ができるのもとてもいい。地下1500mからの掘削に成功し、平成8年(1996年)にオープンしたらしい。泉質は高アルカリ性の単純泉とのことだ。パンフレットには明記されていなかったが、多分循環加熱だと思う。やわらかい湯で、湯上りからその日はずっと肌がすべすべしていた。ヌルヌル感はそれほどでもないが、きっと肌に良い微妙な成分配合なんじゃないかな、と素人考えだがそう思った。利用料は700円(この後、値上げされて800円)。公式HPに10%引きの割引券がある。いい温泉が少ないと思っていた富士山周辺だが、私の先入観が少し変化したように思う。山中湖村の努力とセンスにエールを送りたい。 平野温泉「石割の湯」: 平野バス停から歩いて約15分、石割山の南麓にある村営の日帰り温泉施設。僭越ながら、総合的にバランスの取れた優れた温泉施設だと拝察した。建物が木造でエキゾチックなのがいいし、内湯・外湯がそれぞれ石張りと檜枠造りの2種類あって贅沢感があるのがいい。和風の大広間などがゆったりとしていて、落ち着いてビールを飲んだり食事ができるのもとてもいい。地下1500mからの掘削に成功し、平成8年(1996年)にオープンしたらしい。泉質は高アルカリ性の単純泉とのことだ。パンフレットには明記されていなかったが、多分循環加熱だと思う。やわらかい湯で、湯上りからその日はずっと肌がすべすべしていた。ヌルヌル感はそれほどでもないが、きっと肌に良い微妙な成分配合なんじゃないかな、と素人考えだがそう思った。利用料は700円(この後、値上げされて800円)。公式HPに10%引きの割引券がある。いい温泉が少ないと思っていた富士山周辺だが、私の先入観が少し変化したように思う。山中湖村の努力とセンスにエールを送りたい。
 「石割の湯」のHP 「石割の湯」のHP


山中湖畔から富士山
|
素晴らしい雪景色でした!

兎と?(狸か狐か犬か…)の足跡
なにか…物語を感じさせるフィールドサインです。
弱肉強食の闘争か、ただのランデブーか・・・??
|

石割山へ向かう
|

石割山の山頂にて
 |
再び石割山へ
平成20年(2008年)3月23日 
山の仲間たち(山歩会)をお誘いして再び石割山へ行ってきました。朝早くの高速バスの予約が取れず、時間の関係で平野を基点にした短縮周遊コース(平野〜石割山〜大平山〜平野)を歩きました。
この日も眼前の富士山をたっぷりと眺めることができて、みなさんご満足のようでした。歩行時間は余裕の約3時間で、健脚のかたには少し物足りなかったかもしれません。2月にはあんなに積もっていた雪がもう殆ど融けていて、微かに春の芽吹きを感じました。
下山後に「石割の湯」でのんびりと入浴と食事を楽しんだのは云うまでもありません。
* コースについて補足: 石割山を中心とした登山コースには、本項でご紹介した大出山入口と平野(ひらの)を結ぶ縦走ルートが有力ですが、この他にも北西の内野側とのルートや健脚向けの杓子山や御正体山へ縦走するコース、及びそれらに派生する幾通りかのエスケープルートもあります。交通の便や季節やメンバーの体力などによって、いろいろなコース計画を立てることができるので、それも楽しみの一つです。
本文中にも書きましたが、石割山登山の主流はマイカー族に便利な平野を拠点にした石割山〜平尾山の周遊コースのようです。この場合の歩程は約3時間で、ガイドブックでおなじみの区分けによりますと“家族向き”ということになると思います。
歩く方向については“西行き”のほうが常に富士山を正面に眺めることができるので良いと思います。ただし、私の思うこのコースの真骨頂は下山後の平野温泉入浴にあります。高速バスなどの交通の便を考慮した縦走温泉ハイキングでしたら、断然“東行き”をお勧めします。
このページのトップへ↑
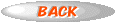 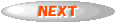

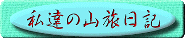
ホームへ
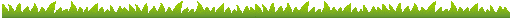
|