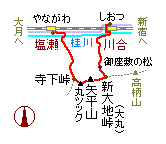 |

馬頭観音を通過

イカリソウ

山笑う…

大丸山から高柄山を望む

矢平山の山頂

丸ツック山を下る

寺下峠方面から矢平山
|
角度によって見え方が・・・

大地峠方面から矢平山を望む
後日(R5年5月)撮影
|
清々しい萌黄色に包まれて 山笑う
JR中央本線四方津駅〜川合橋〜御座敷の松〜大丸山(新大地峠)〜矢平山860m〜丸ツック山763m〜寺下峠〜沢底〜塩瀬大橋〜JR中央本線梁川駅 【歩行時間:
5時間20分】
→ 地理院地図(電子国土Web)の該当ページへ
新宿から高尾までは運賃の安い京王線を利用して、高尾からJR中央本線の普通列車に乗り換えた。ちょっとセコいが、これだと時間はほぼ同じで往復運賃は約700円の得になる。京王線ががんばっているというべきかJRががんばっていないというべきか、それはこの方面へ向かうときに何時も私達夫婦がヒソヒソと話し合うことである。
午前10時頃、山梨県へ入ってから二つ目の駅・四方津(しおつ)駅から私達は歩き始めた。分かりやすい指導標に従って桂川に架かる川合橋を渡る。ヤマブキがちょうど花の盛期で、山里のパステルカラーの新緑に優しいアクセントをつけている。目差す矢平山の方向に目をやると、木々の芽吹きを反映してその山腹は萌黄色(もえぎいろ)に染まっている。矢張り、思った通り、この山域はスギ・ヒノキの人工林が少なくて、コナラやモミジ類やシデ類などの落葉広葉樹の天然林(雑木林)が多いようだ。思わずニンマリとしてよく見ると、それらは一様な萌黄色ではなくて、所々のヤマザクラやミツバツツジの花色とも相まって、かなりの濃淡がある。このパッチ状の芽吹き色の美しさは、これから里の山々が鮮やかな新緑に染まるまでの数日間の、案外と短い“旬”の象徴でもある。遠くでキジが 「ケーン、ケーン」 と鳴いている。道端にはムラサキケマンやジシバリが咲いている。そしてなんと、ツクバネウツギがもう咲いている。今、この地は初夏に近い“春爛漫”なのだ。
山道へ入るとスミレ類の数が一層増えて、足元を間断なく飾る。ナガバノスミレサイシンも少し交じるが、その殆どは(多分)タチツボスミレのようだ。チゴユリ、フデリンドウ、キランソウ、ヒトリシズカなども可憐に咲いていて、鎌首をもたげたミミガタテンナンショウは不気味に自己主張している。そして幸運だったのは、イカリソウがちょうど花の盛期を迎えていたことだ。かつての和船で用いられた四本鉤(いかり)に似ているからというのがその名の由来であるらしい。淡い赤紫色の、何時までも見ていたいキュートな花だ。木々の芽吹きの形態や色彩が樹種によって異なるのも面白くて、山道は何処も彼処も飽きることがない。
大地(おおち)峠に近づくとスギ・ヒノキの植林地帯が現れて、間もなく車道の終点へポンと出る。立派な林道だが自動車の姿は無く、まだ建設中(施工中断かな?)のようだ。なんか拍子抜けしたような気持ちで指導標に沿って進むと、再び山道へ入った。
暫らく進むと再び分岐があって、巻き道もあったのだが、私達は真直ぐに登っていった。すると「大丸山」と手書きされた標柱が立つ小広いピークへ出たので、そこで大休止にした。東面が開けていて、至近距離の高柄山(たかつかやま・733m)が大きく格好良く見えている。春霞のため、東京タワーや六本木ヒルズも見えるという遠望には恵まれなかった。
帰宅してからガイドブックを読み直して分かったことだが、ここ(大丸山の山頂)がつまり新大地峠であるらしい。矢平山と甚之凾山との分岐点にもなっているこの先の旧大地峠とか、林道建設のどさくさで消えたのではないかとウワサされる(本来の)大地峠とかもあって、少々この“峠”はややこしい。
大丸山(新大地峠)から西へ向かって約40分、急坂を登り切ると三等三角点のある矢平山の山頂だった。目の高さにはモミジイチゴ、足元にはツルキンバイが咲く、こじんまりとした心安らぐピークだが、樹林に囲まれていて殆ど展望が無いのが残念だ。すっきりとした展望日和なら梢越しに富士山も見えるらしいが…。
矢平山から寺下峠へ向かう中間地点に丸ツック山というのがあるのだが、普通に歩いていたらその山頂は通過せずに北側の山腹を巻いてしまうと思われた。というのは、直登する道と右手の巻き道との分岐には指導標が無く、直登方向の足元には「通行不可」を示す倒木などが横たわっていたからだ。
私達は(試しに)その倒木を跨いで急坂を登ってみた。ほどなく丸ツック山の山頂と思われるなだらかなピークへ出たが、訪れるハイカーも少ないとみえて所謂荒れている感じだった。樹林に囲まれ鬱蒼としていて、山頂標識や基準点の類は何処を探しても見当たらない。この先に寺下峠方面へ続く山道があるはずだが、その踏み跡もかなり頼りないものだった。試しに少し先へ下ってみたが、ヤブ漕ぎ状態になりそうなので来た道を分岐まで引き返した。それは多分正解だったと思う。
時間にして20分間足らずのタイムロスだったが、丸ツック山の現状がなんとなく分かっただけでもこのアルバイトは有意義だった。矢平山も丸ツック山も、国土地理院発行の地形図にはその山名が載っていない(山名注記のない)マイナーな山だが、特に丸ツック山は、今後益々「忘れられた山」になってしまうんだろうな、と思った。
寺下峠から塩瀬の山里へ下る山道は5年前のゴールデンウイーク(秋山二十六夜山登山の下山後)に歩いたことがある。そのときの強烈な印象が、その新緑の美しさだった。じつは、今回の山行については、この季節のこのトレイルをもう一度歩いてみたかったのがそもそもの動機だった。前回の空を覆う明るくて鮮やかな緑色とは違い、今回は空が透けて見える芽吹きの淡い新緑だったが、どちらの新緑に軍配を上げるかは楽しくて難しい選択問題だ。
ふと振り返ると、その素晴らしい新緑の谷越しに、今さっき登った矢平山がこんもりと聳えている。暫らく足を止めてその山容を食い入るように眺めた。マイナーなはずだが、矢平山はピラミダルで大きくて、とても立派な山に見えた。
斜面のトラバース道の所々に崩壊箇所があり、ザラザラで少し歩きづらいが、トラロープが張ってあったりして危険は感じない。ひんやりとした感じのよい沢筋へ出て暫らく進むとアスファルトで、サトザクラ(八重桜)の咲く横瀬(よこぜ)の集落へ下りつく。桂川の絶景を眺めながら横瀬大橋を渡り、無人の梁川(やながわ)駅へ着いたのは午後4時45分だった。
そこそこに変化のあるコースにも大満足した私達だったが、なんといってもこの山域の美しい新緑にたっぷりと浸かることができたのが爽快だった。“山笑う”は草木の萌え立つ春の季語だというが、この日の矢平山は確かに私達に微笑んでいた。その微笑みを受けて、自分たちの全身が清々しい緑色に染まってしまったような、そんな感じがした。
 矢平山の春の花たち(写真集): 大きな写真でどうぞ。 矢平山の春の花たち(写真集): 大きな写真でどうぞ。
 高尾の湯「ふろッぴィ」: この日の帰路には中央線を高尾駅で途中下車して、無料送迎バスに乗って「ふろッぴィ」で山の汗を流してきました。
この日帰り温泉施設の詳細については高尾山・アラカルトの最下欄を参照してみてください。 高尾の湯「ふろッぴィ」: この日の帰路には中央線を高尾駅で途中下車して、無料送迎バスに乗って「ふろッぴィ」で山の汗を流してきました。
この日帰り温泉施設の詳細については高尾山・アラカルトの最下欄を参照してみてください。

この新緑の差がわかりますか?
出揃った新緑(左)と芽吹きの萌黄色(右)

5年前の5月3日に撮影→秋山二十六夜山
|

今回(4月23日)撮影
|
たまたま同じアングルで撮っていました。(寺下峠からの下山路にて)

 * この約1ヶ月後(平成20年5月18日・晴)、山の仲間たち(山歩会)をお誘いして再び同コースを歩きました。新緑はたけなわでしたが、春の花が終わって、全体的には前回(4月中旬)よりは咲いている花は少ないように感じました。しかし…、あえてその場所は書きませんが、道筋の数箇所にキンラン(ラン科:絶滅危惧Ⅱ類)がひっそりと咲いていたのにはちょっと感動しました。マイナーなコースなので歩く人が少ないのが幸いしたのかも知れません。どうかこのまま悪い人(盗掘者)に見つからないといいな、とみんなで話しました。 * この約1ヶ月後(平成20年5月18日・晴)、山の仲間たち(山歩会)をお誘いして再び同コースを歩きました。新緑はたけなわでしたが、春の花が終わって、全体的には前回(4月中旬)よりは咲いている花は少ないように感じました。しかし…、あえてその場所は書きませんが、道筋の数箇所にキンラン(ラン科:絶滅危惧Ⅱ類)がひっそりと咲いていたのにはちょっと感動しました。マイナーなコースなので歩く人が少ないのが幸いしたのかも知れません。どうかこのまま悪い人(盗掘者)に見つからないといいな、とみんなで話しました。
|
このページのトップへ↑
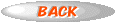 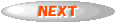

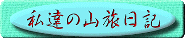
ホームへ
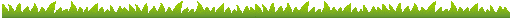
|


 * この約1ヶ月後(平成20年5月18日・晴)、山の仲間たち(山歩会)をお誘いして再び同コースを歩きました。新緑はたけなわでしたが、春の花が終わって、全体的には前回(4月中旬)よりは咲いている花は少ないように感じました。しかし…、あえてその場所は書きませんが、道筋の数箇所にキンラン(ラン科:絶滅危惧Ⅱ類)がひっそりと咲いていたのにはちょっと感動しました。マイナーなコースなので歩く人が少ないのが幸いしたのかも知れません。どうかこのまま悪い人(盗掘者)に見つからないといいな、とみんなで話しました。
* この約1ヶ月後(平成20年5月18日・晴)、山の仲間たち(山歩会)をお誘いして再び同コースを歩きました。新緑はたけなわでしたが、春の花が終わって、全体的には前回(4月中旬)よりは咲いている花は少ないように感じました。しかし…、あえてその場所は書きませんが、道筋の数箇所にキンラン(ラン科:絶滅危惧Ⅱ類)がひっそりと咲いていたのにはちょっと感動しました。マイナーなコースなので歩く人が少ないのが幸いしたのかも知れません。どうかこのまま悪い人(盗掘者)に見つからないといいな、とみんなで話しました。






