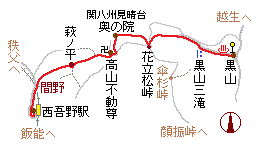|
No.315 高山不動尊・関八州見晴台 平成26年(2014年)1月23日 |
||
西武秩父線西吾野駅〜間野集落〜萩ノ平茶屋(廃屋)〜高山不動尊〜丸山〜関八州見晴台(奥の院)771m〜花立松峠〜黒山三滝〜黒山-《バス26分》-東武東上線越生駅 【歩行時間:
3時間40分】 |
 これが問題の道標だ!  人工林がメインの山道  チャノキ 葉身が11cmもありました  境内にある大イチョウ  境内に建つ廃校  高山不動尊の本堂  関八州見晴台(奥の院)  黒山三滝(男滝・女滝) |
周囲の地形からして、私達は私達の行きたい道(萩ノ平コース)の南側の林道を歩いているようだ。地図ではこの道は行き止まりになっているけれど、指導標もあったことだし、きっと高山不動尊へ続いている山道があるに違いない、とこれも根拠のない推論で、その林道をさらに登り詰めて行った。分岐から10分間ほども歩いただろうか、やっぱりこの道は行き止まりになっていた。なんなんだぁ〜? いったいどうなっているのよ〜?
後で分かったことだが、パノラマコースの指導標に従って北川を渡ってからすぐに右折をして、下流方向に歩かなければいけなかったらしい。私達は気を取り直して林道を戻り下って、そのムーミンの指導標の先にあった立派な道標に従って小さな橋を渡った。初志貫徹、萩ノ平コースだ。今度は間違いない。しかしもう汗だくだ。
* 西武秩父線の西吾野駅から高山不動尊へ向かうハイキングコースには、代表的なものでも3つのコースがある。私達が間違えて行きそこなったパノラマコースと、私達が実際に歩いた萩ノ平コースと、それらの北側に位置する不動滝コースだ。何れもボリュームにおいてそれほどの差はないと思うが、不動滝コースは車道部分が多いようなので、それが若干スポイルされる。
なお、高山不動尊の表参道は、ひとつ手前の吾野駅から大久保入りの流れに沿っていくものだが、やはり車道歩きに終始しているようだ。
2階建の“モダンな人家”が建ち並ぶこじんまりとした間野集落をあっという間に通り抜けると、ヒノキやスギの気持ちのいい林が続き、所々にコナラ、クリ、ハリギリ、アラカシ、モミ(幼木)などの雑木林も交ざる。林内にはヤブツバキ、ヒサカキ、イヌツゲ、アオキなどの照葉樹が目立ち、薄暗い奥まった処ではスダジイの幼樹がひそかに森の覇権を狙っている。そして、これは珍しいチャノキ(ツバキ科)があちこちに生えている。咄嗟に私は、母の実家がある田舎(千葉県山武市)の放置されたスギ林にも、たくさんのチャノキが自生していたのを思い出した。これも矢張り、里の茶畑の種子をネズミさんや鳥さんたちが運んできて、それが野性化したものだろうか。それとも、昔はこの辺りに人家とか畑などがあって、その名残なのかしら。栽培種と比べるとその葉っぱがとても大きいのは、薄暗い林床で必死になって光を求めて生き続けてきた、チャノキのたくましさだろうか。
廃屋と化した萩ノ平茶屋の脇を通り過ぎ、なだらかになってきた山道を暫く進むと、右手からパノラマコースが合流する。チャノキの話などをしながらさらに直進すると、高山不動尊(本堂)の下部にある広場に着いた。ここには樹齢約800年、幹回り10mという天然記念物の大イチョウ(子育て銀杏)がある。それを観察したり写真に撮ったりしてから、少し先へ進んでみると、人の気配のない小さな建物(廃校)がある。門柱には「飯能市立高山小学校」と書かれてある。これも帰宅してから調べて分かったことなのだが、明治7年に創立して昭和41年に閉校となったらしい。山奥の廃校が現存しているのは珍しいことだと思う。境内に建っていたから残ったのか、その歴史は知らないけれど、子供がたくさんいた古き良き時代の遺物であることには違いない。妙に郷愁を誘う情景だ。
大イチョウのある広場から石階段を上がって、立派な本堂(常楽院不動堂)にお参りする。この高山不動は真言宗智山派の寺院で、654年に開山、江戸末期に再建されたという。高幡、成田とともに関東三大不動尊のひとつに数えられているそうだ。参拝にも力が入る。
それから右に道をとって、奥武蔵グリーンラインを歩き、地味な丸山の山頂を通過して、道標に従って再び山道を登ると、そこが本コースの最高点・関八州見晴台771mだった。中央に木祠(高山不動尊の奥ノ院)のある、感じのよいピーク広場で、なんといっても360度の展望が素晴らしい。ぐるっと広場を一回りして、4方向に設置されている展望図と見比べながら、少し靄っている関東平野や、すっきりと見えている奥武蔵、奥多摩、奥秩父などの山々を指呼して悦に入る。特に武甲山とその右奥の両神山の個性ある山容が印象的だ。富士山の純白な山頂部が、御前山(奥多摩)の右奥からチョコっと顔を出している。
ピーク広場のベンチに腰掛けて昼食のオニギリを食べているときに、高校生と思われる若いカップルに声を掛けられた。観光案内誌の地図を私達に見せて 「ここはどこでしょうか?」 と聞いてきたのだ。話を聞いてみると、彼らは顔振峠にある見晴台へ行くつもりで黒山バス停から登ってきたらしい。 「顔振峠見晴台は正反対の方向だよ。ここはここ…、そう、関八州見晴台というところだよ」 と説明したら、若い二人はかなり驚いていた。今朝のコースアウトがあるので、私達はあまり云えた義理じゃないけれど、彼らの方向音痴も相当なものだ。今回の予定コースを赤く塗った25000図のコピーの1枚を彼らに渡して、私達と反対コースで歩くといいでしょう、と教えてあげた。超若い二人は感謝して、この山頂でゆっくり休憩することもなく、そそくさと私達が登ってきた道を下っていった。再び静かになって暫くして、「平日なのに、彼ら、学校をさぼったのかなぁ」 と私がつぶやいたら、「試験休みとか、きっとそんなところよ」 と佐知子が笑って答えた。それにしても、最近はほんとうに山に若い人が増えたものだ。
関八州見晴台から東の方向へ尾根道を下る。それから舗装されたグリーンラインの一角(林道猿岩線)を歩き、花立松ノ峠で左へVターンして、頼りない道標に従って恐々と山道を右へ下る。見慣れた日本の山の(心安らぐ)風景…典型的なV字谷が前方に見下ろせる。
「日照水」と呼ばれる水場を過ぎてからも林道と山道を交互に辿ると、そこが黒山三滝の男滝・女滝だった。気分よく観光して、少し下ってもう一つの滝(天狗滝)も見物する。平日なので、茶店などはどこも閉鎖されていて、それが静けさを増幅して、とてもよかった。
黒山三滝は、以前二人で歩いたことのある懐かしのスポットであるはずだが、よく話し合っても、そのときの思い出を思い出すことができない。これも帰宅してから自分のこのホームページの“No.9「顔振峠から大高取山」の項”を久しぶりに読んでみてはっきりとしたのだが、私達夫婦は間違いなく19年前(平成7年2月11日〜12日)にこの地を訪れている。忘却とは忘れ去ることなり…。
黒山バス停のベンチで20分間ほど待ち、14時27分発の越生駅行きのバスに乗る。乗客は私達の二人だけだ。下山後の立ち寄り入浴は次回の楽しみにして、きょうはまっすぐに帰路につく。
で、夕方の5時前には東京都大田区の自宅に帰ることができた。父が、二階の炬燵でテレビの相撲を見ながら、お地蔵様のようにじっとして、ウトウトしていた。
今回のトレイルは、累積標高差600m以上はあっただろうか、正月ボケの身体には丁度いいボリュームだった。アスファルトとコンクリートだらけのコース、と思っていたのだが、意外と山道だったので、それもとてもよかったと思う。
佐知子の歌日記より
あやしげな案内板に道迷い 二十五分のロスタイムなり
山頂に観光雑誌もちながら ここはどこかとたずねるアベック
下山後の入浴はせず帰宅する 手締めをしない宴会のような

関八州見晴台から西面を望む : 奥多摩〜奥武蔵(武甲山方面)
関八州=武蔵、相模、下総、上総、安房、上野、下野、常陸
 関八州見晴台にて  ネコノメソウ |
再び 高山不動尊・関八州見晴台
平成26年3月29日 ![]()
山の仲間たち(山歩会)をお誘いして、再び同コースを歩いてきました。2月の大雪の影響か、スミレ類などの春の草花は未だほとんど咲いておらず、下山時の沿道にネコノメソウがきれいに咲いていたのが強く印象に残りました。例の早春の小花…オオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、ホトケノザ、タネツケバナ…は相変わらずあちこちに咲いていましたが…。木の花ではヤブツバキが満開で、フサザクラ、キブシ、アブラチャンなどが見ごろを迎えていました。
初夏を思わせる暖かい日で、心もザックも軽かったのですが、春霞のため展望は(冬の快晴の日と比べると)イマイチでした。“花に嵐”といいますが、あれもこれもはなかなかうまくいかないものです。
ふきのとうがたくさん採れたので、明日の朝は炊きたてのご飯にフキミソ(フキノトウの味噌和え)で…、う〜ん、たまりませんなぁ。
![]() ニューサンピア埼玉おごせ「梅の湯」: 帰路に、越生行きのバスを途中下車して立ち寄りました。埼玉県西部の越生町・越生梅林の近くに位置する(いわゆる何でもありの)総合レジャー施設で、日帰り入浴も受け付けています。
旧埼玉厚生年金休暇センター。 下山地の黒山バス停からは16分、越生駅までは10分の乗車時間でした。入浴料はフェイスタオル付きで780円。アルカリ性単純温泉とのことで、露天風呂は確かにヌルヌル感がありましたが、内湯は普通の湯に感じました。特に感想はありませんが(つまり可もなく不可もないということ)、この施設は宿泊や宴会などに力を入れているようで、日帰り入浴の私たちは少し疎外感を感じました。
ニューサンピア埼玉おごせ「梅の湯」: 帰路に、越生行きのバスを途中下車して立ち寄りました。埼玉県西部の越生町・越生梅林の近くに位置する(いわゆる何でもありの)総合レジャー施設で、日帰り入浴も受け付けています。
旧埼玉厚生年金休暇センター。 下山地の黒山バス停からは16分、越生駅までは10分の乗車時間でした。入浴料はフェイスタオル付きで780円。アルカリ性単純温泉とのことで、露天風呂は確かにヌルヌル感がありましたが、内湯は普通の湯に感じました。特に感想はありませんが(つまり可もなく不可もないということ)、この施設は宿泊や宴会などに力を入れているようで、日帰り入浴の私たちは少し疎外感を感じました。
和気藹々と、みんなと飲んだ風呂上がりの生ビールは、相変わらず最高でした。(^_^)/~
佐知子の歌日記より
関八州見晴台は春霞 ここちよい汗ふきつつ憩う
里あるき名残の梅の足元は おおいぬのふぐりの青い海
十四人の靴音ひびく里の道 つくしんぼうの行列は立つ
客引きの女のあとをジジババが リュックで歩く池袋の夜
ホームへ