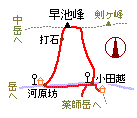|
No.65 早池峰山(はやちね・1917m) 平成10年(1998年)6月20日〜21日 |
|||||
《マイカー利用》 第1日=東北自動車道・紫波I.C-《車》-河原坊〜小田越山荘(薬師岳中腹まで散歩) 第2日=小田越山荘〜早池峰〜打石〜頭垢離〜(コメガモリ沢)〜河原坊-《車》-紫波I.C… |
 早池峰  八合目の鉄梯子  早池峰山頂 |
第1日目(6月20日): 河原ノ坊の駐車場から、雨のあがりかけた舗装道路を約50分間ほど歩き、小田越山荘に到着したのは12時10分だった。昼食のパンなどをかじり、1〜2時間睡眠。買ったばかりのシュラフは軽くて頼りなさそうだったが、なかなか具合が良い。風が強く、薬師岳の山頂アタックは断念したが、散歩がてらに花崗岩の目立つ登山道を途中まで歩いてみた。
雨後の新緑が目に痛いほどに新鮮だ。木道の切れた辺りから、お目当てのオサバグサの群落が続いていた。まるでオシダやシシガシラのような、四方に広がる緑鮮やかな葉が美しい。その真ん中から伸びた細い茎の先端には、小さな白い花が下向きにいくつも咲いている。「可憐」というのはこのようなことなんだろうな、と思った。
夕食は持参した霜降りの和牛ステーキだ。まことに旨かった。ボルドー産の赤ワィンもなかなかだ。7時過ぎにはもう、ぐっすりだった。
第2日目(6月21日): 午前5時40分、山荘発。雨の心配はなさそうだが、早池峰は依然雲の中だった。
アオモリトドマツは別名オオシラビソと呼ばれているが、なるほどシラビソにそっくりだ。シラビソより一回り小さい感じがするが、何故オオシラビソというのだろうか。(*)
樹林帯を過ぎ(高度約1300m)、蛇紋岩の岩礫性裸地地帯に入ると、最盛期にはチト早いが、それでも高山植物のオンパレードだ。ベニサラサドウダンが咲いている。岩陰のハヤチネウスユキソウが辛うじて咲いている。ミヤマアズマギク、ミヤマオダマキ、ミヤマシオガマ、ナンブイヌナズナ、イワカガミも咲いている。チングルマまで咲いている。(帰ってから佐知子が植物図鑑で調べたのだ。)
八合目の鉄梯子を過ぎ、稜線に出た頃から雲が少し切れてきた。山頂部からの展望は360度。南方にどっしりと薬師岳。東方の広い稜線上の先にピョコンと早池峰剣ヶ峰。北西方向に見えるはずの姫神山や岩手山は、残念ながら雲に隠れてとうとう見ることができなかった。
民話によると、岩手山と姫神山と早池峰は三角関係にあるのだそうで、早池峰と姫神山が晴れると岩手山が曇り、岩手山と姫神山が晴れると早池峰が曇るといわれている。とても面白い話だと思うが、山岳展望を楽しみにしている登山者にとってはえらい迷惑な話だ。
高山植物や、蛇紋岩の美しい深緑の縞模様などを観察しながら下山。河原ノ坊着は12時50分。ゴロ石の下山道は意外とタフだった。
ドライブにて東京の自宅へ到着したのは午後9時30分。山登りよりも車の運転の方が疲れた。
* オオシラビソ(アオモリトドマツ): マツ科モミ属。シラビソに似ていて、球果が大きいのでこの名がついた、とのことです。 後日、草津白根山へ行ったときに登山道沿いの解説板にそう書いてありました。
「シラビソとオオシラビソの違い」についてはNo.299国師ヶ岳と北奥千丈岳のコラム欄を参照してみてください。[後日追記]
|
再び早池峰山へ 平成22年(2010年)7月24日[後泊] |
東北自動車道・紫波I.C-《車》-岳-《バス》-小田越登山口〜早池峰〜打石〜頭垢離〜(コメガモリ沢)〜河原坊-《バス》-岳-《車》-台温泉(泊)… 【歩行時間: 5時間20分】
 八合目の鉄梯子 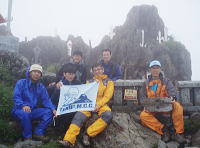 霧の山頂部 |
シーズン中は車両交通規制が布かれていて、岳から登山口まではシャトルバスを利用することになる。携帯用トイレの普及啓発など、地元の官民が一体となって早池峰山の自然環境保全に取り組んでいる現状を目の当たりにして、これはほんとうに素晴らしいことだと思った。
小田越登山口のバス停から歩き始めたのは8時40分頃、空模様がどうもよくない…。
今回の予定は小田越コースで上って河原坊コースで下る、12年前に私達夫婦が歩いたコースと同じだ。で、経験のある私が先頭に立ち、道案内の役を仰せつかった。時々小雨が降ってくる。濡れると滑りやすい蛇紋岩は要注意だ。
オオシラビソの林床にはカニコウモリが群生している。樹高の低いダケカンバやそれとよく似ているミヤマハンノキ、そしてハイマツなどが出てくると間もなく森林限界を超す。足元にはイブキジャコウソウ、ハクサンシャジン、キンロバイ、モミジカラマツ、ウメバチソウ、ミヤマオダマキ、タカネナデシコ、ホソバ(コバノ?・タカネ?)ツメクサ、ミヤマアキノキリンソウ、ミネウスユキソウなどが咲いている。当地特産のナンブトラノオ、ナンブトウウチソウ、そしてハヤチネウスユキソウも咲いている。私たちの歩く速度は極端に遅くなり、早池峰らしい花見山行だ。
山頂手前のお花畑にはミヤマアズマギク、チングルマ、ハクサンボウフウ、シナノキンバイ、ヨツバシオガマ、コバイケイソウなども咲いていた。しかし、花の特によい時季は6月中旬〜7月上旬とのことで、その盛りには少し遅い感も否めない。
ほとんどホワイトアウトの山頂で記念の集合写真(証拠写真)を撮り、いそいそと下山を開始したのだが、この下山道(河原坊コース)で登山経験の浅いメンバーの一人が岩場で滑落して怪我をしてしまうアクシデントに見舞われた。幸い大事には至らなかったものの、大変な山旅になってしまった。直接的な原因は浮き石に足を取られたことだが…、遠因として寝不足と疲れと油断があったのではないかと思われる。やはり夜行の強行軍は避けるべき、との反省を(今回も)してしまった。
歩きにくいゴロ石のコメガモリ沢を、クガイソウ、センジュガンピ、オオウバユリなどの花を愛でながら、さらにゆっくりと下って、ビジターセンターのある河原坊登山口へ着いたのは午後4時頃だった。この日の宿は花巻温泉郷の台温泉に決めてある。評判のよい温泉なので楽しみだ。

* 翌日の帰路、宮沢賢治記念館に立ち寄ってみた。今ちょうど「早池峰山と賢治」という企画展が催されていて、大変勉強になった。
・・・・・・・・・・
ここはコケモモと花咲くウメバチソウ
かすかな岩の輻射もあれば
雲のレモンのにほひもする
↑宮沢賢治の詩「早池峰山嶺」の最後の3行です。私はこの部分が特に好きです。
花名と「花咲く」については原文のひらがなを敢えてカタカナと漢字に書き直しました。
賢治さん、勝手なことをして、スミマセン。

ハヤチネウスユキソウ
 ミネウスユキソウ |
 ミヤマアズマギク |
ホームへ